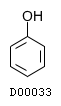医薬品情報
| 総称名 | パオスクレー |
|---|---|
| 一般名 | フェノール |
| 欧文一般名 | Phenol |
| 製剤名 | フェノール(Phenol)製剤 |
| 薬効分類名 | 内痔核硬化療法剤 |
| 薬効分類番号 | 2559 |
| ATCコード | C05BB05 |
| KEGG DRUG |
D00033
フェノール
|
| KEGG DGROUP |
DG00301
フェノール
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2023年6月 改訂(第1版)

|
2.禁忌 4.効能または効果 6.用法及び用量 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 11.副作用 14.適用上の注意 16.薬物動態 17.臨床成績 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| パオスクレー内痔核内注射用250mg | PAOSCLE INJ.250mg | 鳥居薬品 | 2559400A1033 | 3834円/管 | 処方箋医薬品注) |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
内痔核
6. 用法及び用量
通常、成人1回5mLを粘膜下に注射し、1部位に対する1回の注射量は1〜3mLとする。
症状に応じ、適宜増減する。
症状に応じ、適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
8.1 本剤の副作用は注射手技上発生することが多いので、下記の点に特に注意すること。
8.1.1 痔静脈内に誤って注入すると、まれに肝臓の油塞栓を生じることがあるので、注射筒に血液の逆流のないことを確かめるなど、特に注意すること。[14.1.1参照]
8.1.2 歯状線より下方に注入したり、薬液が歯状線下に浸潤すると、肛門部疼痛が、また、粘膜内に注入すると注射部のびらん・壊死等の症状があらわれることがあるので、歯状線より上部(直腸下部)の粘膜下に注入すること。[2.1参照]
8.1.3 前方に深く注入すると、まれに排尿障害、前立腺炎、尿道部疼痛等の症状があらわれることがあるので注意すること。
8.2 注射後、20分間程度医師の監督下に留め、患者の全身状態を観察すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
一般に生理機能が低下している。
11. 副作用
11.2 その他の副作用
| 0.1〜5%未満 | 0.1%未満 | 頻度不明 | |
| 投与部位 | 疼痛、びらん、肛門部不快感、腫脹、注射部出血 | 肛門部狭窄感 | 痔核嵌頓、血腫 |
| 循環器 | 徐脈 | 血圧低下 | |
| 消化器 | 悪心 | 嘔吐 | |
| その他 | 冷汗 | めまい | 悪寒、熱感 |
14. 適用上の注意
14.1 薬剤投与時の注意
14.1.1 注射針刺入時、血液の逆流のないことを確かめること。[8.1.1参照]
14.1.2 5〜20mmの二段針又は22〜23ゲージの70〜80mmの針を用いて、粘膜下組織に少量の薬液を注入し、痛みがなく、浮腫状の膨隆が起き、粘膜の小血管の走行が明瞭になってくることを確かめること(なお、深すぎれば疼痛があり、浅すぎれば白色貧血状の膨疹となるので、この場合は注入をやり直すこと)。
16. 薬物動態
16.2 吸収
パオスクレー0.2mL/kg(フェノール量として10mg/kg)をラットの肛門皮下に注射し局所貯留性を検討した。本剤中のフェノールは投与30分後には約75%以上、6時間後には96%以上が局所から消失した1)。
16.3 分布
パオスクレー4mL/kg(フェノール量として0.2g/kg)をラットに腹腔内投与し、1、4、24時間後における肝臓、腎臓、肺臓、心臓、消化管および血液のフェノール濃度を測定した。本剤中のフェノールは投与1時間後をピークに主に肝臓、腎臓、消化器、肺臓等に分布し、投与24時間後には検出されなかった。他の臓器に比較して肝臓に多く分布されたが、各臓器からの消失は速やかであった1)。
16.5 排泄
パオスクレー4mL/kg(フェノール量として0.2g/kg)をラットに腹腔内投与したところ、投与されたフェノールの約91%が24時間以内に尿中から排泄され、そのうちの約95%が結合型フェノールとして存在した。糞中には結合型フェノールとして約0.4%が認められた1)。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 国内臨床成績
| 疾患名 | 有効率(%)(有効例/症例数) |
| 内痔核 | 82.8(207/250) |
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. フェノール
22. 包装
5mL×10管
23. 主要文献
- 社内資料:パオスクレーのフェノールの吸収排泄実験
- 植村 剛, 臨床と研究, 49 (3), 824-827, (1972)
- 高野正博ほか, 診療と新薬, 12 (1), 133-144, (1975)
- 坂部孝ほか, 日本大腸肛門病学会雑誌, 23 (4), 31-33, (1971) »DOI
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
鳥居薬品株式会社
お客様相談室
〒103-8439
東京都中央区日本橋本町3-4-1
電話:0120-316-834
FAX:03-3231-6890
製品情報問い合わせ先
鳥居薬品株式会社
お客様相談室
〒103-8439
東京都中央区日本橋本町3-4-1
電話:0120-316-834
FAX:03-3231-6890
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
鳥居薬品株式会社
東京都中央区日本橋本町3-4-1