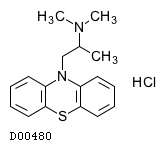医薬品情報
| 総称名 | ヒベルナ |
|---|---|
| 一般名 | プロメタジン塩酸塩 |
| 欧文一般名 | Promethazine Hydrochloride |
| 製剤名 | プロメタジン塩酸塩注 |
| 薬効分類名 | 抗ヒスタミン剤 |
| 薬効分類番号 | 4413 |
| ATCコード | D04AA10 R06AD02 |
| KEGG DRUG |
D00480
プロメタジン塩酸塩
|
| KEGG DGROUP |
DG00385
プロメタジン
DG01482
ヒスタミンH1受容体拮抗薬
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2025年12月 改訂(第2版 D39)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒベルナ注25mg | HIBERNA INJECTION | 田辺ファーマ | 4413400A1046 | 61円/管 | 処方箋医薬品注) |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
○麻酔前投薬
○人工(薬物)冬眠
○感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽
○皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、薬疹、中毒疹)
○枯草熱
○じん麻疹
○血管運動性浮腫
○振せん麻痺
○動揺病
5. 効能または効果に関連する注意
抗パーキンソン剤はフェノチアジン系化合物、ブチロフェノン系化合物等による口周部等の不随意運動(遅発性ジスキネジア)を通常軽減しない。場合によっては、このような症状を増悪、顕性化させることがある。
6. 用法及び用量
プロメタジン塩酸塩として、通常、成人1回5〜50mgを、皮下あるいは筋肉内注射する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ必要最小限に行うこと。
8. 重要な基本的注意
8.1 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
8.2 制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者
悪性症候群(Syndrome malin)が起こりやすい。[11.1.1参照]
9.1.2 開放隅角緑内障の患者
抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。
9.3 肝機能障害患者
肝機能障害を悪化させるおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
9.7.1 2歳未満の乳幼児
9.7.2 2歳以上の幼児、小児
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。2歳以上の幼児、小児を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
10. 相互作用
10.2 併用注意
| 抗コリン作用を有する薬剤 フェノチアジン系化合物 三環系抗うつ剤等 | 腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等)を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。なお、この悪心・嘔吐は本剤及び他のフェノチアジン系化合物等の制吐作用により不顕性化することもあるので、注意すること。 | 併用により抗コリン作用が強くあらわれる。 |
| 中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘導体・麻酔剤等 | 相互に中枢神経抑制作用を増強することがあるので、減量する等慎重に投与すること。 | ともに中枢神経抑制作用を有する。 |
| アルコール (飲酒) | 相互に中枢神経抑制作用を増強することがある。 | ともに中枢神経抑制作用を有する。 |
| 降圧剤 カルシウム拮抗剤 アンジオテンシンII受容体拮抗剤等 | 相互に降圧作用を増強することがあるので、減量する等慎重に投与すること。 | ともに降圧作用を有する。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 悪性症候群(Syndrome malin)(頻度不明)
抗精神病薬及び抗うつ剤との併用において、本剤及び併用薬の減量又は中止により、発熱、無動緘黙、意識障害、強度の筋強剛、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、体冷却、水分補給などの全身管理等の適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇があらわれることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下があらわれることがある。[9.1.1参照]
注)発現頻度は、再評価の結果を含む。
11.2 その他の副作用
| 0.1〜5%未満 | 頻度不明 | |
| 過敏症 | 発疹、光線過敏症 | |
| 肝臓 | 肝障害 | |
| 血液 | 白血球減少、顆粒球減少 | |
| 精神神経系 | 眠気、めまい、倦怠感、頭痛、耳鳴、視覚障害、不安感、興奮、神経過敏、不眠、痙攣 | |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、口渇、食欲不振、下痢、腹痛 | |
| 循環器 | 血圧上昇、低血圧、頻脈、起立性低血圧 | |
| その他 | 発汗、咳嗽、振戦 |
13. 過量投与
13.1 症状
傾眠、意識消失等の中枢神経抑制、低血圧、口渇、瞳孔散大、呼吸障害、錐体外路症状等である。その他、幻覚、痙攣等の中枢神経興奮作用があらわれることがある。
13.2 処置
アドレナリンは更に血圧低下を引き起こすおそれがあるので使用しないこと。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤投与時の注意
14.1.1 筋肉内注射時
局所の発赤、発熱、腫脹、壊死、化膿等がみられることがある。また、組織・神経などへの影響を避けるため、下記の点に注意すること。
・同一部位への反復注射は行わないこと。また、幼児又は小児には特に注意すること。
・神経走行部位を避けるよう注意すること。
・注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合には、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
健康成人6例に本剤50mgを筋肉内投与したときの最高血中濃度(Cmax)は48.26ng/mL、半減期(t1/2)は9.76時間であった1)(外国人のデータ)。
| Cmax(ng/mL) | tmax(h) | AUC0-24h(ng・h/mL) | t1/2(h) |
| 48.26±12.26 | 3.00±1.26 | 627.13±156.69 | 9.76±3.41 |
16.4 代謝
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
18.1.1 抗ヒスタミン作用
プロメタジンは、ヒスタミン受容体と結合して不活性複合体を作ることにより遊離ヒスタミンが組織細胞と結合するのを防ぎ、鼻閉、鼻汁を改善する。
18.1.2 抗コリン作用
抗コリン作動薬の作用部位は線条体におけるコリン作動性終末であり、受容体へのアセチルコリンの取り込みを阻害する事によるとされている。
18.2 動物での作用
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. プロメタジン塩酸塩
20. 取扱い上の注意
外箱開封後は遮光して保存すること。
22. 包装
[1mL×50管]
23. 主要文献
- Schwinghammer TL,et al., Biopharm Drug Dispos., 5 (2), 185-194, (1984) »PubMed
- 中村克徳,他, 臨床薬理, 27 (1), 57-58, (1996) »DOI
- 久保田利秋, 新薬と臨床, 8 (6), 491-493, (1959)
- Kopera J,et al., Br J Pharmacol Chemother., 9 (4), 392-401, (1954) »PubMed
- Hitomi M,et al., Arzneimittelforschung., 22 (6), 953-961, (1972) »PubMed
- Courvoisier S,et al., Arch Int Pharmacodyn Ther., 92 (3-4), 305-361, (1953) »PubMed
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
田辺ファーマ株式会社
くすり相談センター
〒541-8505
大阪市中央区道修町3-2-10
電話:0120-753-280
製品情報問い合わせ先
田辺ファーマ株式会社
くすり相談センター
〒541-8505
大阪市中央区道修町3-2-10
電話:0120-753-280
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
田辺ファーマ株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10