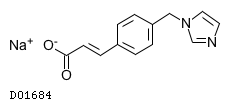医薬品情報
| 総称名 | オザグレルNa |
|---|---|
| 一般名 | オザグレルナトリウム |
| 欧文一般名 | Ozagrel Sodium |
| 薬効分類名 | トロンボキサン合成酵素阻害剤 |
| 薬効分類番号 | 2190 |
| KEGG DRUG |
D01684
オザグレルナトリウム
|
| KEGG DGROUP |
DG01256
オザグレル
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年1月 改訂(第1版)

|
2.禁忌 4.効能または効果 6.用法及び用量 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 14.適用上の注意 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 20.取扱い上の注意 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 (後発品) | Ozagrel Na Injection Bag"TAKATA" | 高田製薬 | 3999411G5066 | 881円/袋 | 処方箋医薬品 |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
○クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善
○脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善
6. 用法及び用量
<クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善>
通常成人に、オザグレルナトリウムとして1日量80mgを24時間かけて静脈内に持続投与する。投与はクモ膜下出血術後早期に開始し、2週間持続投与することが望ましい。なお、年齢、症状により適宜増減する。
<脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善>
通常成人に、オザグレルナトリウムとして1回量80mgを2時間かけて1日朝夕2回の持続静注を約2週間行う。なお、年齢、症状により適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 脳塞栓症のおそれのある患者
心房細動、心筋梗塞、心臓弁膜疾患、感染性心内膜炎及び瞬時完成型の神経症状を呈する患者
脳塞栓症の患者は出血性脳梗塞が発現しやすいため、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。
9.1.2 出血している患者
9.1.3 出血の可能性のある患者
脳出血の既往歴のある患者、重症高血圧患者、重症糖尿病患者、血小板の減少している患者等
出血を助長する可能性がある。
9.1.4 心臓、循環器系機能障害のある患者
(生理食塩液に関する注意)
循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。
9.2 腎機能障害患者
(生理食塩液に関する注意)
水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
一般に生理機能が低下している。
10. 相互作用
10.2 併用注意
| 抗血小板剤 チクロピジン アスピリン等 血栓溶解剤 ウロキナーゼ アルテプラーゼ等 抗凝血剤 ヘパリン ワルファリン アルガトロバン等 | これらの薬剤と併用することにより出血傾向の増強をきたすおそれがある。 観察を十分に行い、減量するなど用量を調節すること。 | 本剤は血小板凝集能を抑制するため、類似の作用を持つ薬剤を併用することにより作用を増強する可能性がある。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 出血
<クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善>
<脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善>
11.1.2 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫、冷感等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
11.1.3 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
著しいAST・ALTの上昇等を伴う重症な肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
11.1.4 血小板減少(頻度不明)
11.1.5 白血球減少、顆粒球減少(いずれも頻度不明)
発症時には発熱や悪寒等がみられることが多いので、これらの症状があらわれた時は本症を疑い血液検査を行うこと。
11.1.6 腎機能障害(頻度不明)
重篤な腎機能障害(急性腎障害等)があらわれることがある。腎機能障害時には血小板減少を伴うことが多い。
11.2 その他の副作用
| 0.1%〜3%未満 | 頻度不明 | |
| 過敏症 | 発疹、蕁麻疹、紅斑 | 喘息(様)発作、そう痒 |
| 循環器 | 上室性期外収縮、血圧下降 | |
| 血液 | 貧血 | |
| 肝臓 | AST・ALT、LDH、アルカリホスファターゼ、ビリルビンの上昇等 | |
| 腎臓 | BUN、クレアチニン上昇 | |
| 消化器 | 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振、膨満感 | |
| その他 | 発熱、頭痛、注射部の発赤・腫脹・疼痛 | CK上昇、胸内苦悶感、ほてり、悪寒・戦慄、関節炎、CRP上昇 |
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 カルシウムを含む製剤と混合すると白濁するので、注意すること。
14.1.2 使用後の残液は使用しないこと。
14.1.3 液が澄明でないもの、着色したものは使用しないこと。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
オザグレルナトリウムは、アラキドン酸カスケード中のトロンボキサンA2(TXA2)合成酵素を選択的に阻害してトロンボキサンTXA2の産生を抑制し、TXA2による血小板凝集能を抑制すると共に、プロスタサイクリンの産生を促進して、両者のバランス異常を改善する。また、脳血管攣縮や脳血流量低下の抑制作用も認められているが、これらに関する詳細な機序は確定していない1)。
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. オザグレルナトリウム
20. 取扱い上の注意
20.1 外袋は遮光性の包材を使用しているので、使用直前まで開封しないこと。また、開封後は速やかに使用すること。
20.2 外袋から取り外さず使用すること。本剤は光によりわずかに分解することがある。
20.3 次の場合は使用しないこと。
・外袋が破損している場合。
・外袋の内側に水滴や薬液の漏出が認められる場合。
・薬液に着色や混濁が認められる場合。
・排出口をシールしているフィルムがはがれている場合。
20.4 使用時には排出口をシールしているフィルムをはがすこと。
20.5 穿刺の際にはゴム栓の刺針部(凹部)にまっすぐ刺すこと。斜めに刺すと、排出口内壁を削り、削り片が薬液中に混入したり、排出口側壁を刺通し、液漏れを起こすことがある。
なお、同一箇所を繰り返し刺さないこと。
なお、同一箇所を繰り返し刺さないこと。
20.6 通気針は不要である。
20.7 連結管(U字管)による連続投与は行わないこと。
20.8 容器の目盛はおよその目安として使用すること。
22. 包装
200mL×10袋(ソフトバッグ)
23. 主要文献
- 日本薬局方解説書編集委員会編, 第十八改正日本薬局方解説書, C-1234-1238, (2021)
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
高田製薬株式会社
文献請求窓口
〒336-8666
さいたま市南区沼影1丁目11番1号
電話:0120-989-813
FAX:048-816-4183
製品情報問い合わせ先
高田製薬株式会社
文献請求窓口
〒336-8666
さいたま市南区沼影1丁目11番1号
電話:0120-989-813
FAX:048-816-4183
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
高田製薬株式会社
さいたま市西区宮前町203番地1