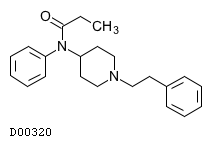医薬品情報
| 総称名 | ラフェンタ |
|---|---|
| 一般名 | フェンタニル |
| 欧文一般名 | Fentanyl |
| 製剤名 | フェンタニル貼付剤 |
| 薬効分類名 | 3日用安定放出型がん疼痛治療 |
| 薬効分類番号 | 8219 |
| ATCコード | N02AB03 |
| KEGG DRUG |
D00320
フェンタニル
|
| KEGG DGROUP |
DG00791
フェンタニル
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年12月 改訂(第2版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラフェンタテープ1.38mg | Lafenta Tapes 1.38mg | 日本臓器製薬 | 8219700T6028 | 781.3円/枚 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品 |
| ラフェンタテープ2.75mg | Lafenta Tapes 2.75mg | 日本臓器製薬 | 8219700T7024 | 2092.7円/枚 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品 |
| ラフェンタテープ5.5mg | Lafenta Tapes 5.5mg | 日本臓器製薬 | 8219700T8020 | 4004.1円/枚 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品 |
| ラフェンタテープ8.25mg | Lafenta Tapes 8.25mg | 日本臓器製薬 | 8219700T9027 | 5643.5円/枚 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品 |
| ラフェンタテープ11mg | Lafenta Tapes 11mg | 日本臓器製薬 | 8219700U1021 | 7405円/枚 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品 |
1. 警告
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
2.1 本剤の成分に対し過敏症のある患者
2.2 ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者[10.1参照]
4. 効能または効果
非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛(ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る)
中等度から高度の疼痛を伴う各種がん
5. 効能または効果に関連する注意
本剤は、他のオピオイド鎮痛剤が一定期間投与され、忍容性が確認された患者で、かつオピオイド鎮痛剤の継続的な投与を必要とするがん疼痛の管理にのみ使用すること。
6. 用法及び用量
本剤は、オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する。通常、成人に対し胸部、腹部、上腕部、大腿部等に貼付し、3日毎(約72時間)に貼り替えて使用する。初回貼付用量は本剤投与前に使用していたオピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案して、1.38mg(12.5μg/hr)、2.75mg(25μg/hr)、5.5mg(50μg/hr)、8.25mg(75μg/hr)のいずれかの用量を選択する。
その後の貼付用量は患者の症状や状態により適宜増減する。
その後の貼付用量は患者の症状や状態により適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
7.1 初回貼付用量
初回貼付用量として、本剤11mg(100μg/hr)は推奨されない。本邦において、初回貼付用量として8.25mg(75μg/hr)を超える使用経験はない。
初回貼付用量を選択する下記換算表は、経口モルヒネ量90mg/日(注射の場合30mg/日)、経口オキシコドン量60mg/日(注射の場合30mg/日)、フェンタニル又はフェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤の場合、フェンタニル量として0.6mg/日(25μg/hr)、フェンタニル注射剤0.5mg/日に対して本剤2.75mg(フェンタニル0.6mg/日;25μg/hr)へ切り替えるものとして設定している。なお、初回貼付用量は換算表に基づく適切な用量を選択し、過量投与にならないよう注意すること。
初回貼付用量を選択する下記換算表は、経口モルヒネ量90mg/日(注射の場合30mg/日)、経口オキシコドン量60mg/日(注射の場合30mg/日)、フェンタニル又はフェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤の場合、フェンタニル量として0.6mg/日(25μg/hr)、フェンタニル注射剤0.5mg/日に対して本剤2.75mg(フェンタニル0.6mg/日;25μg/hr)へ切り替えるものとして設定している。なお、初回貼付用量は換算表に基づく適切な用量を選択し、過量投与にならないよう注意すること。
| 本剤3日貼付用量 | 1.38mg | 2.75mg | 5.5mg | 8.25mg |
| 定常状態における推定平均吸収速度 | 12.5μg/hr | 25μg/hr | 50μg/hr | 75μg/hr |
| 定常状態における推定平均吸収量注1) | 0.3mg/日 | 0.6mg/日 | 1.2mg/日 | 1.8mg/日 |
| モルヒネ経口剤 | <45mg/日 | 45〜134mg/日 | 135〜224mg/日 | 225〜314mg/日 |
| モルヒネ注射剤 | <15mg/日 | 15〜44mg/日 | 45〜74mg/日 | 75〜104mg/日 |
| オキシコドン経口剤 | <30mg/日 | 30〜89mg/日 | 90〜149mg/日 | 150〜209mg/日 |
| オキシコドン注射剤 | <15mg/日 | 15〜44mg/日 | 45〜74mg/日 | 75〜104mg/日 |
| フェンタニル経皮吸収型製剤(3日貼付型製剤) | 2.1mg | 4.2mg | 8.4mg | 12.6mg |
| フェンタニル経皮吸収型製剤(1日貼付型製剤) | 0.84mg | 1.7mg | 3.4mg | 5mg |
| フェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤注2) | 1mg | 2mg | 4mg | 6mg |
| フェンタニル注射剤 | <0.3mg/日 | 0.3〜0.8mg/日 | 0.9〜1.4mg/日 | 1.5〜2.0mg/日 |
7.2 初回貼付時
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に初めて切り替えた場合、初回貼付24時間後までフェンタニルの血中濃度が徐々に上昇するため、鎮痛効果が得られるまで時間を要する。そのため、下記の使用方法例を参考に、切替え前に使用していたオピオイド鎮痛剤の投与を行うことが望ましい。
| 切替え前のオピオイド鎮痛剤の投与回数 | 切替え時のオピオイド鎮痛剤の用法例 |
| 1日1回投与 | 投与12時間後に本剤の貼付を開始する。 |
| 1日2〜3回投与 | 本剤の貼付開始と同時に1回量を投与する。 |
| 持続投与 | 本剤の貼付開始後6時間まで継続して持続投与する。 |
患者により上記の使用方法例では、十分な鎮痛効果が得られない場合がある。患者の状態を観察し、本剤の鎮痛効果が得られるまで、適時オピオイド鎮痛剤の追加投与(レスキュー)により鎮痛をはかること。1回の追加投与(レスキュー)量として、本剤の切替え前に使用していたオピオイド鎮痛剤が経口剤の場合は1日投与量の1/6量を、注射剤の場合は1/12量を目安として投与すること。この場合、速効性のオピオイド鎮痛剤を使用することが望ましい。
7.3 用量調整と維持
7.3.1 疼痛増強時における処置
本剤貼付中に痛みが増強した場合や疼痛が管理されている患者で突出痛(一時的にあらわれる強い痛み)が発現した場合には、直ちにオピオイド鎮痛剤の追加投与(レスキュー)により鎮痛をはかること。1回の追加投与(レスキュー)量として、本剤の切替え前に使用していたオピオイド鎮痛剤が経口剤の場合は1日投与量の1/6量を、注射剤の場合は1/12量を目安として投与すること。この場合、速効性のオピオイド鎮痛剤を使用することが望ましい。
7.3.2 増量
鎮痛効果が得られるまで患者毎に用量調整を行うこと。鎮痛効果が十分得られない場合は、追加投与(レスキュー)されたオピオイド鎮痛剤の1日投与量及び疼痛程度を考慮し、1.38mg(12.5μg/hr)及び2.75mg(25μg/hr)から増量する場合は1.38mg(12.5μg/hr)とし、それ以上の貼付用量の場合は25〜50%を目安として貼替え時に増量する。なお、本剤の1回の貼付用量が33mg(300μg/hr)を超える場合は、他の方法を考慮すること。
7.3.3 減量
連用中における急激な減量は、退薬症候が生じることがあるので行わないこと。副作用等により減量する場合は、十分に観察を行いながら慎重に減量すること。
7.4 投与の中止
7.4.1 本剤の投与を必要としなくなった場合には、退薬症候の発現を防ぐために徐々に減量すること。
7.4.2 本剤の投与を中止し、他のオピオイド鎮痛剤に変更する場合は、本剤剥離後の血中フェンタニル濃度が50%に減少するのに17時間以上かかることから、他のオピオイド鎮痛剤の投与は低用量から開始し、患者の状態を観察しながら適切な鎮痛効果が得られるまで漸増すること。
8. 重要な基本的注意
8.1 本剤を中等度から高度のがん疼痛以外の管理に使用しないこと。
8.2 本剤の使用開始にあたっては、主な副作用、具体的な使用方法、使用時の注意点、保管方法等を患者等に対して十分に説明し、理解を得た上で使用を開始すること。特に呼吸抑制、意識障害等の症状がみられた場合には速やかに主治医に連絡するよう指導すること。また、本剤使用中に本剤が他者に付着しないよう患者等に指導すること。[14.1.3、14.1.6、14.2.1-14.2.9、14.3.1-14.3.3参照]
8.3 重篤な呼吸抑制が認められた場合には、本剤を剥離し、呼吸管理を行う。呼吸抑制に対しては麻薬拮抗剤(ナロキソン、レバロルファン等)が有効であるが、麻薬拮抗剤の作用持続時間は本剤より短いので、観察を十分に行い麻薬拮抗剤の繰り返し投与を考慮すること。[11.1.2参照]
8.4 他のオピオイド鎮痛剤から本剤への切替え直後に、悪心、嘔吐、傾眠、浮動性めまい等の副作用が多く認められることがあるため、切替え時には観察を十分に行い、慎重に投与すること。なお、これらの副作用は経時的に減少する傾向がみられる。
8.5 他のオピオイド鎮痛剤から本剤に切り替えた場合には、患者によっては、あくび、悪心、嘔吐、下痢、不安、振戦、悪寒等の退薬症候があらわれることがあるので、患者の状態を観察しながら必要に応じ適切な処置を行うこと。[11.1.1参照]
8.6 本剤を増量する場合には、副作用に十分注意すること。
8.7 連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。また、乱用や誤用により過量投与や死亡に至る可能性があるので、これらを防止するため観察を十分行うこと。[9.1.6、11.1.1参照]
8.8 連用中における投与量の急激な減量は、退薬症候があらわれることがあるので行わないこと。[11.1.1参照]
8.9 重篤な副作用が発現した患者については、本剤剥離後のフェンタニルの血中動態を考慮し、本剤剥離から最低でも24時間観察を継続すること。
8.10 本剤貼付中に発熱又は激しい運動により体温が上昇した場合、本剤貼付部位の温度が上昇しフェンタニル吸収量が増加するため、過量投与になり、死に至るおそれがあるので、患者の状態に注意すること。また、本剤貼付後、貼付部位が電気パッド、電気毛布、加温ウォーターベッド、赤外線灯、集中的な日光浴、サウナ、湯たんぽ等の熱源に接しないようにすること。本剤を貼付中に入浴する場合は、熱い温度での入浴は避けさせるようにすること。[1.、9.1.5参照]
8.11 眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
8.12 鎮痛剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 慢性肺疾患等の呼吸機能障害のある患者
呼吸抑制を増強するおそれがある。[11.1.2参照]
9.1.2 喘息患者
気管支収縮を起こすおそれがある。
9.1.3 徐脈性不整脈のある患者
徐脈を助長させるおそれがある。
9.1.4 頭蓋内圧の亢進、意識障害・昏睡、脳腫瘍等の脳に器質的障害のある患者
呼吸抑制を起こすおそれがある。[11.1.2参照]
9.1.5 40℃以上の発熱が認められる患者
本剤からのフェンタニル放出量の増加により、薬理作用が増強するおそれがある。[1.、8.10参照]
9.1.6 薬物依存の既往歴のある患者
9.2 腎機能障害患者
代謝・排泄が遅延し、副作用があらわれやすくなるおそれがある。なお、腎機能障害患者を対象として有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.3 肝機能障害患者
代謝・排泄が遅延し、副作用があらわれやすくなるおそれがある。
9.5 妊婦
9.6 授乳婦
本剤使用中は授乳を避けさせること。
ヒトで母乳中へ移行することが報告されている。[16.3.3参照]
ヒトで母乳中へ移行することが報告されている。[16.3.3参照]
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
副作用の発現に注意し、慎重に投与すること。
フェンタニルのクリアランスが低下し、血中濃度消失半減期の延長がみられ、若年者に比べ感受性が高いことが示唆されている1)。
フェンタニルのクリアランスが低下し、血中濃度消失半減期の延長がみられ、若年者に比べ感受性が高いことが示唆されている1)。
10. 相互作用
相互作用序文
本剤は、主として肝代謝酵素CYP3A4で代謝される。[16.4参照]
薬物代謝酵素用語
CYP3A4
10.1 併用禁忌
| ナルメフェン塩酸塩水和物 セリンクロ [2.2参照] | 離脱症状を起こすおそれがある。また、鎮痛作用が減弱するおそれがある。ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者には投与しないこと。 | μオピオイド受容体への競合的阻害による。 |
10.2 併用注意
| 中枢神経抑制剤 フェノチアジン系薬剤 ベンゾジアゼピン系薬剤 バルビツール酸系薬剤等 全身麻酔剤 モノアミン酸化酵素阻害剤 三環系抗うつ剤 骨格筋弛緩剤 鎮静性抗ヒスタミン剤 アルコール オピオイド系薬剤 | 呼吸抑制、低血圧、めまい、口渇及び顕著な鎮静又は昏睡が起こることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。 | 相加的に中枢神経抑制作用が増強する。 |
| セロトニン作用薬 選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI) モノアミン酸化酵素阻害剤等 | セロトニン症候群(不安、焦燥、興奮、錯乱、発熱、発汗、頻脈、振戦、ミオクローヌス等)があらわれるおそれがある。 | 相加的にセロトニン作用が増強するおそれがある。 |
| CYP3A4阻害作用を有する薬剤 リトナビル イトラコナゾール フルコナゾール ボリコナゾール アミオダロン クラリスロマイシン ジルチアゼム フルボキサミン等 | 本剤の有効成分のAUCの増加、血中半減期の延長が認められたとの報告がある。呼吸抑制等の副作用が発現することがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。 | 肝CYP3A4に対する阻害作用により、本剤の有効成分の代謝が阻害される。 |
| CYP3A4誘導作用を有する薬剤 リファンピシン カルバマゼピン フェノバルビタール フェニトイン等 | 本剤の有効成分の血中濃度が低下し、治療効果が減弱するおそれがある。必要に応じて本剤の用量調整を行うこと。CYP3A4誘導作用を有する薬剤の中止後、本剤の有効成分の血中濃度が上昇し、重篤な呼吸抑制等の副作用が発現するおそれがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。 | 肝CYP3A4に対する誘導作用により、本剤の有効成分の代謝が促進される。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 依存性(頻度不明)
11.1.2 呼吸抑制(頻度不明)
11.1.3 意識障害(頻度不明)
意識レベルの低下、意識消失等の意識障害があらわれることがある。
11.1.4 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
11.1.5 痙攣(頻度不明)
間代性、大発作型等の痙攣があらわれることがある。
11.2 その他の副作用
| 5%以上 | 5%未満 | 頻度不明 | |
| 循環器 | 右脚ブロック | 高血圧、低血圧、頻脈、動悸、徐脈、チアノーゼ | |
| 精神神経系 | 傾眠 | めまい、味覚異常、頭痛、せん妄 | 不穏、不眠、不安、幻覚、いらいら感、健忘、錯乱、多幸症、うつ病、振戦、激越、錯感覚、感覚鈍麻、回転性めまい、無感情、注意力障害、記憶障害、錐体外路障害、痛覚過敏注)、アロディニア |
| 皮膚 | そう痒 | 貼付部位反応(そう痒、紅斑、発疹、湿疹、小水疱、皮膚炎)、発疹、紅斑、皮膚炎(接触性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎を含む)、湿疹、汗疹 | |
| 消化器 | 嘔気、排便回数増加、嘔吐 | 便秘、下痢、口渇、腹痛、胃部不快感、消化不良、イレウス、痔核、口内炎、食道運動障害 | |
| 肝臓 | 肝機能異常 | ||
| 泌尿器 | 尿閉、排尿困難 | ||
| 眼障害 | 縮瞳、霧視、結膜炎、複視 | ||
| 感染症 | 鼻咽頭炎、膀胱炎、帯状疱疹 | ||
| 臨床検査 | LDH増加、ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加、血中Al-P増加、血中尿素窒素上昇 | 白血球数減少、血小板数減少、血中カリウム減少、蛋白尿、血中ビリルビン増加、尿糖陽性、総蛋白減少、体重減少、白血球数増加 | |
| その他 | 倦怠感、転倒 | 発熱、発汗、しゃっくり、末梢性浮腫、性機能不全、勃起不全、無力症、筋痙縮、疲労、インフルエンザ様疾患、冷感、体温変動感、体熱感、薬剤離脱症候群、貧血、白血球増加症、食欲減退、耳鳴、背部痛、筋骨格痛、四肢痛、不正子宮出血、胸部不快感、胸痛、悪寒、異常感 |
13. 過量投与
13.1 症状
フェンタニルの過量投与時の症状として、薬理作用の増強により重篤な換気低下を示す。また、フェンタニルの過量投与により白質脳症が認められている。
13.2 処置
過量投与時には以下の治療を行うことが望ましい。
・換気低下が起きたら、直ちに本剤を剥離し、患者をゆり動かしたり、話しかけたりして目をさまさせておく。
・麻薬拮抗剤(ナロキソン、レバロルファン等)の投与を行う。患者に退薬症候又は麻薬拮抗剤の副作用が発現しないよう慎重に投与する。なお、麻薬拮抗剤の作用持続時間は本剤の作用時間より短いので、患者のモニタリングを行うか又は患者の反応に応じて、初回投与後は注入速度を調節しながら持続静注する。
・臨床的に処置可能な状況であれば、患者の気道を確保し、酸素吸入し、呼吸を補助又は管理する。必要があれば咽頭エアウェイ又は気管内チューブを使用する。これらにより、適切な呼吸管理を行う。
・適切な体温の維持と水分摂取を行う。
・重度かつ持続的な低血圧が続けば、循環血液量減少の可能性があるため、適切な輸液療法を行う。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤交付時の注意
14.1.1 オピオイド鎮痛剤が投与されていた患者であることを確認した上で本剤を交付すること。
14.1.2 包装袋を開封せず交付すること。
14.1.3 本剤の使用開始にあたっては、患者等に対して具体的な使用方法、使用時の注意点、保管方法等を患者向けの説明書を用いるなどの方法によって指導すること。[8.2、14.1.6、14.2.1-14.2.9、14.3.1-14.3.3参照]
14.1.4 患者等に対して、本剤を指示された目的以外に使用してはならないことを指導すること。
14.1.5 患者等に対して、本剤を他人へ譲渡してはならないことを指導すること。
14.2 薬剤貼付時の注意
14.2.1 体毛のない部位に貼付することが望ましいが、体毛のある部位に貼付する場合は、皮膚を傷つけないようにハサミを用いて除毛すること。本剤の吸収に影響を及ぼすため、カミソリや除毛剤等は使用しないこと。[8.2、14.1.3参照]
14.3 薬剤貼付期間中の注意
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
16.1.1 生物学的同等性試験
日本人健康成人男性30例を対象に本剤11mg(100μg/hr)とデュロテップMTパッチ16.8mg(100μg/hr)の生物学的同等性をクロスオーバー法により検討した結果、血漿中フェンタニル濃度から算出した薬物動態パラメータ(AUC0-144、Cmax)の製剤間比及びその90%信頼区間が生物学的同等性の許容域の範囲(80〜125%)内にあったことから、両製剤の生物学的同等性が確認された2)。
| AUC0-144(pg・hr/mL) | Cmax(pg/mL) | tmax(hr) | t1/2(hr) | |
| 本剤11mg | 125592±40870 | 1959±824 | 41.6±16.4 | 27.3±7.2 |
| デュロテップMTパッチ16.8mg | 129443±53616 | 1993±1052 | 39.2±16.9 | 29.1±9.1 |
16.1.2 用量比例性
日本人健康成人男性29例を対象に、本剤の1.38mg(12.5μg/hr)、2.75mg(25μg/hr)、5.5mg(50μg/hr)、8.25mg(75μg/hr)及び11mg(100μg/hr)を単回投与した際の貼付用量とAUC0-tの関係は下図のとおりであり、薬物動態パラメータ(AUC0-t、Cmax)と用量の関係をパワーモデルで検討した結果、傾きはそれぞれ1.07及び1.03であった3)。
本剤貼付用量と血漿中フェンタニル濃度のAUC0-t
本剤貼付用量と血漿中フェンタニル濃度のCmax
16.3 分布
16.3.1 組織への分布
放射性物質である3Hフェンタニルをラットに単回皮下投与したとき、放射能は全身に広く分布し、投与後1時間における放射能濃度はハーダー腺、肝臓、腎臓、顎下腺、膵臓、下垂体、胃、副腎、肺、小腸、骨髄、脾臓の順に高かったことが報告されている4)。
16.3.2 胎児移行性
16.3.3 乳汁移行性
16.3.4 血漿蛋白結合率
ヒト血漿蛋白結合率は84.4%(in vitro、平衡透析法、10ng/mL)であった6)。
16.4 代謝
16.5 排泄
健康成人に3Hフェンタニルを静脈内投与したとき、72時間までに投与量の76±3%が尿中に排泄され、そのほとんどが代謝物であり、未変化体は投与量の6.4±1.2%であった。糞中には投与量の1.2%±0.3%が未変化体として、7.8±1.0%が代謝物として排泄された8)。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 がん疼痛患者を対象としたオピオイド鎮痛薬からの治療切替試験
各種がん疼痛に対し、オピオイド鎮痛薬による治療で疼痛コントロールが安定して良好な患者を対象に、鎮痛治療を本剤に切り替えて、3日間を1回として計3回の9日間貼付した際、疼痛コントロール維持良好注1)例数は78/94例であり、疼痛コントロール維持良好率(95%信頼区間)は、83%(75〜91%)であった9)。
| 先行オピオイド鎮痛薬 | 評価対象例数 | 本剤の疼痛コントロール維持状態 | ||
| 良好 | 良好率 | |||
| 全体 | 94例 | 78例 | 83% | |
| 内訳 | 1日用フェンタニル貼付剤 | 34例 | 32例 | 94% |
| 3日用フェンタニル貼付剤 | 5例 | 3例 | 60% | |
| オキシコドン経口剤 | 38例 | 32例 | 84% | |
| その他注2) | 17例 | 11例 | 65% | |
注1)以下のa)からc)の基準を全て満たした場合、疼痛コントロール維持良好と判定した。
a)本剤へ切替え後、貼付第2回目から貼付第3回目の間に貼付用量に変更がないこと。ただし、フェンタニル経皮吸収型製剤から切り替えた場合は、切替え前の用量が本剤の貼付第1回目から貼付第3回目までを通して変更なく維持されていること。
b)過去24時間の大半を占める痛み(持続痛)につき、本剤貼付前3日間のNRS値の平均をベースライン値とし、ベースライン値及び本剤貼付第3回目の3日間の平均NRS値が共に3.0以下で、かつベースライン値からの変動幅はNRS値の平均で+2.0以内であること。
c)本剤貼付第3回目の3日間の平均レスキュー・ドーズ回数が2.0回以下であること。
注2)モルヒネ経口剤、モルヒネ注射剤、オキシコドン注射剤、フェンタニル注射剤を含む。
鎮痛治療を本剤に切り替えて、計3回の9日間貼付した際、全症例での持続痛のNRS値の3日間の平均は、本剤貼付前3日間は1.16、貼付第1回目は1.26、第2回目は1.28、第3回目は1.28で推移し、本剤貼付前からの上昇は認められず、持続痛に対する本剤の効果は治験期間を通して維持された。
1日あたりの持続痛のNRS値の推移
平均値±標準偏差
臨床試験での副作用発現頻度は18.1%(17/94例)であり、主な副作用は傾眠9.6%(9/94例)、そう痒3.2%(3/94例)、嘔気2.1%(2/94例)、嘔吐2.1%(2/94例)等であった9)。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
モルヒネと同様にμオピオイド受容体を介して鎮痛作用を示すものと考えられる10)。
18.2 鎮痛作用
本剤の主薬であるフェンタニルは、フェニルピペリジン系に関連する合成オピオイドであり、フェンタニルの鎮痛作用はモルヒネに比べて約100倍の力価である10)。
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. フェンタニル
22. 包装
ラフェンタテープ1.38mg
5枚(1包1枚入×5)
ラフェンタテープ2.75mg
5枚(1包1枚入×5)
ラフェンタテープ5.5mg
5枚(1包1枚入×5)
ラフェンタテープ8.25mg
5枚(1包1枚入×5)
ラフェンタテープ11mg
5枚(1包1枚入×5)
23. 主要文献
- Bentley JB,et al., Anesth Analg., 61 (12), 968-71, (1982) »PubMed
- 社内資料:An open-label,single-dose,randomized,twoperiod,cross-over bioequivalence study of a novel fentanyl patch 11.0mg and Durotep MT Patch 16.8mg in healthy Japanese male volunteers
- 社内資料:A randomized,open-label,three-period,tensequence,five-treatment,cross-over study to assess dose proportionality of single-dose administration of a novel fentanyl patch in healthy Japanese male volunteers
- 大塚宏之ほか, 薬理と治療, 29 (11), 865-76, (2001)
- Leuschen MP,et al., Clin Pharm., 9 (5), 336-7, (1990) »PubMed
- Meuldermans WEG,et al., Arch.Int.Pharmacodyn., 257 (1), 4-19, (1982)
- Feierman DE,et al., Drug Metab Dispos., 24 (9), 932-9, (1996) »PubMed
- McClain DA,et al., Clin.Pharmacol.Ther., 28 (1), 106-14, (1980) »PubMed
- 社内資料:がん疼痛患者を対象としたオピオイド鎮痛薬からNZL-228への治療切替試験
- たか折修二, グッドマン・ギルマン薬理書 第12版, 634-94, (2013), (廣川書店)
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
日本臓器製薬株式会社
くすりの相談窓口 受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日及び当社休日を除く
〒541-0046
大阪市中央区平野町4丁目2番3号
電話:フリーダイヤル 0120-630-093
06-6233-6085
06-6233-6085
FAX:06-6233-6087
製品情報問い合わせ先
日本臓器製薬株式会社
くすりの相談窓口 受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日及び当社休日を除く
〒541-0046
大阪市中央区平野町4丁目2番3号
電話:フリーダイヤル 0120-630-093
06-6233-6085
06-6233-6085
FAX:06-6233-6087
25. 保険給付上の注意
本剤は厚生労働省告示第75号(平成24年3月5日付)に基づき、1回30日分を限度として投薬する。
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町4丁目2番3号