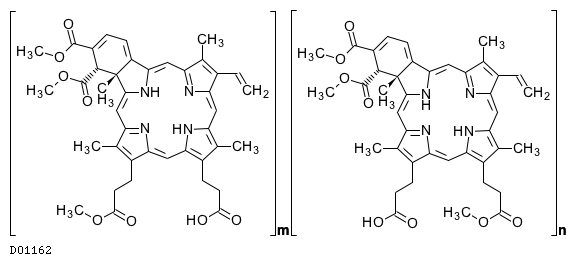医薬品情報
| 総称名 | ビスダイン |
|---|---|
| 一般名 | ベルテポルフィン |
| 欧文一般名 | Verteporfin |
| 製剤名 | 静注用ベルテポルフィン |
| 薬効分類名 | 加齢黄斑変性症治療剤(光線力学的療法用製剤) |
| 薬効分類番号 | 1319 |
| ATCコード | S01LA01 |
| KEGG DRUG |
D01162
ベルテポルフィン
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年10月 改訂(第2版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビスダイン静注用15mg | Visudyne | チェプラファーム | 1319401F1026 | 137276円/瓶 | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
1. 警告
1.1 本剤による光線力学的療法は、規定の講習を受け、光線力学的療法の安全性・有効性を十分に理解し、本剤の調製・投与及びレーザー照射に関する十分な知識・経験のある眼科専門医のみが実施すること。
1.2 本剤投与後48時間は皮膚又は眼を直射日光や強い室内光に暴露させないよう注意すること。本剤投与後48時間以内は光線に対して過敏になるため。[8.3.1参照]
1.3 本剤投与後48時間以内に緊急手術を要する場合は、できる限り内部組織を強い光から保護すること。本剤投与後48時間以内は光線に対して過敏になるため。
1.4 光照射により本剤を活性化させた場合に、視力低下等の高度の視覚障害が誘発されるおそれがあり、回復しなかった症例も認められていることから、本剤による光線力学的療法のリスクについても十分に患者に説明した上で、本治療を施行すること。[11.1.1参照]
1.5 本剤は特定の適切な眼科用光線力学的療法用レーザーにより光照射した場合にのみ、適正かつ安全に使用できることが確認されているので、本剤の光活性化の基準に適合しないレーザーは使用しないこと。光熱凝固のために使用されているレーザーを本剤の活性化に用いることはできない。基準に適合しないレーザーを用いた場合には、本剤の部分的光活性化による不十分な治療、あるいは逆に、過度の活性化により網膜等周辺正常組織の損傷を引き起こすおそれがある。
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
2.1 ポルフィリン症の患者[症状を増悪させるおそれがある。]
2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.3 眼底の観察が困難な患者[混濁の程度の強い白内障又は角膜混濁のある患者等では、眼底の観察が困難であり、また、対象となる病変部に適切な光照射エネルギー量が到達するかどうか不明であるため、本剤による適切な治療を施行することができない。]
4. 効能または効果
5. 効能または効果に関連する注意
Occult CNV(脈絡膜新生血管)又はminimally classic CNVを有する患者では、本剤の有効性(視力低下抑制)はプラセボと統計学的有意差がみられなかったとの成績があるので、これらの患者に本剤を適用することについてはリスクとベネフィットを勘案した上で判断すること。[17.3参照]
6. 用法及び用量
ベルテポルフィンとして6mg/m2(体表面積)を10分間かけて静脈内投与し、本剤投与開始から15分後にレーザー光[波長689±3nm、光照射エネルギー量50J/cm2(照射出力600mW/cm2で83秒間)]を治療スポットに照射する。
なお、3ヵ月毎の検査時に蛍光眼底造影で脈絡膜新生血管からのフルオレセインの漏出が認められた場合は、再治療を実施する。
なお、3ヵ月毎の検査時に蛍光眼底造影で脈絡膜新生血管からのフルオレセインの漏出が認められた場合は、再治療を実施する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤による光線力学的療法(本PDT)は、本剤の静脈内投与(第1段階)及び眼科用光線力学的療法用レーザー(非発熱性ダイオードレーザー)からのレーザー光照射によるビスダインの活性化(第2段階)の2つのプロセスからなる。
7.1 再治療
3ヵ月以内の間隔で再治療を実施しても、視力低下の維持においてさらなる有効性は認められなかったとの成績があるので、再治療の実施時期については、各患者の症状や検査成績の推移について慎重に検討した上で判断すること。[17.1.4参照]
7.4 病変サイズの測定
7.4.1 蛍光眼底血管造影及びカラー眼底写真によって病変の最大直径(GLD:greatest linear dimension)を測定する。
7.4.2 この測定には全てのclassic CNV及びoccult CNV、血液又は蛍光のブロック(blocked fluorescence)及び網膜色素上皮の漿液性剥離を含めること。また、眼底カメラは倍率2.4〜2.6の範囲内のものが望ましい。
7.4.3 蛍光眼底血管造影での病変のGLDについては、眼底カメラの倍率に関する補正を加えて、網膜病変のGLDを算定する。
7.5 スポットサイズの決定
7.5.1 治療スポットサイズは、網膜病変部に500μmの縁取りを行い、病変部を完全にカバーできるようにするために、GLDに1,000μmを加える。
7.5.2 ただし、治療スポットの鼻側縁端は、視神経乳頭の側頭側縁端から200μm以上離れた位置とする。視神経への障害を避けるため、視神経から200μm以内のレーザー照射を避けなければならない。病変部が視神経に極めて近い位置に存在する患者においては、病変部を完全にカバーできないため、視神経から200μm以内のCNVでの光活性化が起こらず、本剤の有効性は低下するおそれがある。
7.6 レーザー光照射
7.6.1 視力矯正用コンタクトレンズを使用している患者の場合、本PDTの前にコンタクトレンズをはずしてから治療を開始すること。
7.6.2 ベルテポルフィンの光による活性化は照射する総エネルギー量でコントロールする。
7.6.3 CNVの治療における照射エネルギー量はCNV病変1cm2あたり50Jである(照射出力600mW/cm2で83秒間照射することになる)。
7.6.4 事前に決定した治療スポットに適切にレーザー光を照射するためには、照射エネルギー量、照射出力、眼科用レンズの倍率、ズームレンズの設定が重要なパラメータとなる。レーザー照射手順の設定と操作については使用するレーザーシステムマニュアルに従い、用法及び用量に定めた照射条件を厳密に遵守すること。
7.6.5 689±3nmの波長を安定に出力できるレーザーを使用する。
7.6.6 レーザー光は適切な眼科用拡大レンズを使用し、光ファイバー及びスリットランプを介して単円スポットとして網膜に照射する。
7.6.7 必要な場合には、眼球運動防止のための球後麻酔を併用することができる。
7.7 両眼治療(臨床試験では両眼治療は行われていない。)
初回治療における両眼同時治療は避けること。なお、両眼に治療対象となる病変がある場合は、両眼同時治療の有益性と危険性を慎重に評価する必要がある。
7.7.1 過去に本PDTを施行した経験がなく、両眼に治療対象となる病変がある患者については、まず片眼(病変が進行している眼)にのみ本PDTを施行し、1週間以上観察した上で、特に安全性上問題がないと判断できる場合に限って、もう一方の眼への本PDTの施行を考慮すること。
7.7.2 過去に片眼に対して本PDTを施行し、特に安全性上問題がなかった場合において、両眼に治療対象となる病変がある患者については、最初に進行がより高度である眼の病変を対象として、用法及び用量に従い本PDTを施行すること。その後直ちにもう一方の眼の治療のためにレーザーを再設定し、本剤投与開始から20分以内(投与終了10分以内)に光照射を実施すること。
8. 重要な基本的注意
8.1 背部痛、胸痛等の筋骨格痛を引き起こすことがあるので、これらのリスクについても予め患者に対して十分な説明を行うとともに、本剤投与中は慎重に観察し、これらの症状が強くあらわれた場合には、直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。特に高血圧、アレルギーの既往がある場合には、重篤化するおそれがあるので注意すること。
8.2 本剤投与後、視覚異常、視力低下又は視野欠損等の視覚障害が発現することがあるので、このような症状が続いている間は高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう患者を十分指導すること。
8.3 患者指導
本PDTの実施にあたっては、患者に対して、以下の内容を十分指導すること。
8.3.1 本剤の投与を受けた患者は投与後48時間は光線過敏状態にあるため、投与後2日間は皮膚、眼等を直射日光、強い室内光(日焼けサロン、強いハロゲンランプ、手術室・歯科治療室で用いられる強力な医療用照明等)にさらさないよう注意する必要がある。[1.2、14.1.1参照]
8.3.2 本剤投与後2日以内の昼間に外出しなければならない場合は、皮膚や眼を強い光から保護しなければならず、保護用の衣服や濃いサングラスを着用する必要がある。
また、皮膚に残存しているベルテポルフィンは可視光線によって活性化されるので、紫外線用日焼け止め剤は光線過敏性反応から皮膚を保護するためには無効である。
また、皮膚に残存しているベルテポルフィンは可視光線によって活性化されるので、紫外線用日焼け止め剤は光線過敏性反応から皮膚を保護するためには無効である。
8.3.3 本剤投与3〜5日目も直射日光や強い光への暴露は避けることが望ましい。
8.3.4 室内光を浴びることにより“photo bleaching”といわれるプロセスを介して皮膚に残存しているベルテポルフィンの不活化が促進されるので、本PDT施行後は暗所にとどまらず積極的に室内光を浴びることが望ましい(但し、強いハロゲンランプ、窓からの直射日光あるいはこれらに相当する光線への暴露は避ける必要がある)。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 胆管閉塞のある患者
代謝又は排泄が遅延するおそれがある。
9.1.2 麻酔下にある患者
アトロピン及びケタミンで鎮静化したブタ又は麻酔ブタに臨床推奨用量の10倍以上の高用量(2mg/kg)を急速静脈内投与した試験で、補体活性化の結果と考えられる死亡を含む重篤な循環不全が認められている。これらの作用は抗ヒスタミン剤の前投与により減弱又は消失している。また、これらの作用は無麻酔ブタではみられず、無麻酔下、全身麻酔下を問わずイヌでは認められていない。
ヒトの血液を用いたin vitro試験において、10μg/mLの濃度(本剤投与患者の予想最高血中濃度の5倍を超える濃度)で軽度〜中等度の補体活性化が認められ、100μg/mL以上の濃度で有意な補体活性化が認められている。臨床試験では臨床的に意味のある補体活性化は報告されていないが、補体活性化によるアナフィラキシー発現の危険性を排除できない。
9.1.3 網膜血管増殖腫(Retinal Angiomatous Proliferation)の患者
当該患者に対する臨床成績はなく、有効性及び安全性は確立していない。
9.1.4 糖尿病性網膜症をはじめとする網膜症を合併している患者
当該患者に対する臨床成績はなく、有効性及び安全性は確立していない。
9.3 肝機能障害患者
代謝又は排泄が遅延するおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
また、動物実験(ラット)でベルテポルフィン10mg/kg/日以上(雌ラットのAUC0-∞に基づけば、ヒトでの投与量6mg/m2の約40倍以上の相当量)を器官形成期の母体に静脈内投与した試験で、胎児に肋骨の湾曲、無眼球症/小眼球症の発生率増加が認められている。妊娠ウサギの器官形成期にベルテポルフィン10mg/kg/日を静脈内投与した試験で、母体の体重増加の抑制、摂餌量の減少が認められている。
また、動物実験(ラット)でベルテポルフィン10mg/kg/日以上(雌ラットのAUC0-∞に基づけば、ヒトでの投与量6mg/m2の約40倍以上の相当量)を器官形成期の母体に静脈内投与した試験で、胎児に肋骨の湾曲、無眼球症/小眼球症の発生率増加が認められている。妊娠ウサギの器官形成期にベルテポルフィン10mg/kg/日を静脈内投与した試験で、母体の体重増加の抑制、摂餌量の減少が認められている。
9.6 授乳婦
授乳しないことが望ましい。母乳中へ移行することが報告されている。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
65歳以上と65歳未満の患者における薬物動態パラメータを確認した結果、AUCの平均値は65歳以上群は65歳未満群より有意に高いことが知られている。[16.6.2参照]
10. 相互作用
相互作用序文
本剤のヒトにおける薬物相互作用に関する試験は行われていない。
肝及び血漿のエステラーゼによってわずかに代謝されるが、肝ミクロゾームのチトクロームP450はベルテポルフィンの代謝には関与していないと考えられる。[16.4参照]
肝及び血漿のエステラーゼによってわずかに代謝されるが、肝ミクロゾームのチトクロームP450はベルテポルフィンの代謝には関与していないと考えられる。[16.4参照]
薬物代謝酵素用語
エステラーゼ
薬物代謝酵素用語
CYP
10.2 併用注意
| Ca拮抗剤 ポリミキシンB 放射線療法 | 本PDTの効果、副作用の増強が起こる可能性がある。 | ベルテポルフィンの血管内皮への取り込みを増大するため。 |
| 光線過敏性反応を起こす薬剤 テトラサイクリン系薬剤 スルホンアミド系薬剤 フェノチアジン系薬剤 スルホニルウレア系血糖降下剤 チアジド系利尿剤 グリセオフルビン | 光線過敏性反応の発生の可能性が増大するおそれがある。 | 共に光線過敏性反応を起こす可能性があるため。 |
| 活性酸素を消去する化合物又はラジカルに対してスカベンジャーとして作用する化合物 β-カロチン エタノール マンニトール | 本PDTの効果を低下させる可能性がある。 | 本PDTにより発生する活性酸素を捕捉するため。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 眼障害
重篤な視力低下(3.1%)、視覚異常(変視症、霧視等)(4.7%)、視野欠損(頻度不明)、硝子体出血(頻度不明)、網膜下出血(1.6%)、網膜剥離(頻度不明)、網膜色素上皮剥離(頻度不明)、網膜色素上皮裂孔(頻度不明)、網膜浮腫(頻度不明)、黄斑浮腫(頻度不明)[1.4参照]
11.1.2 アナフィラキシー、血管迷走神経反応(頻度不明)
失神、発汗、めまい、発疹、呼吸困難、潮紅、血圧の変化、心拍数の変化等の全身状態を伴うことがある。
11.1.3 痙攣(頻度不明)
11.1.4 脳梗塞(1.6%)、大動脈瘤(1.6%)、心筋梗塞(1.6%)
11.1.5 出血性胃潰瘍(頻度不明)
11.1.6 全身性の疼痛(頻度不明)
11.2 その他の副作用
| 5%〜10%未満 | 1%〜5%未満 | 頻度不明 | |
| 治療眼 | 視力低下 | 眼の異常感(眼違和感、眼瞼腫脹感)、彩視症、眼重感、中心性漿液性網脈絡膜症 | 視野障害(暗点、黒点等)、網膜又は脈絡膜血液非灌流、加齢黄斑変性の進行、結膜炎、眼痛、流涙障害、羞明、網膜虚血、白内障、眼の乾燥 |
| 注射部 | − | − | 疼痛、浮腫、炎症、血管外漏出、出血、変色、過敏性反応、水疱 |
| 消化器 | − | 悪心、膵炎 | 便秘、下痢、嘔吐、腹痛 |
| 内分泌・代謝系 | − | 血中コレステロール増加、血中カリウム増加 | 糖尿病、ケトーシス |
| 血液 | − | 好酸球増加症、異型リンパ球 | 貧血 |
| 肝臓 | − | AST、ALT上昇 | − |
| 過敏症 | − | 発疹、そう痒 | 光線過敏性反応、蕁麻疹 |
| 精神神経系 | − | 頭痛、めまい、痴呆、うつ病、パーキンソニズム、感覚減退 | 感覚鈍麻、感覚異常 |
| 循環器 | − | 動悸、不整脈 | 高血圧 |
| 泌尿器 | − | 糸球体腎炎、尿蛋白、血中クレアチニン増加、尿潜血陽性 | − |
| その他 | − | 注入に関連した背部痛(骨盤、肩帯又は胸郭への放散痛)、無気力、頚部違和感、筋硬直 | 発熱、胸痛、無力症、悪寒、インフルエンザ症候群、咳嗽増加、疼痛、非治療眼の視力低下 |
13. 過量投与
本剤の過量投与又はレーザー光の過量照射により正常な網膜血管の非灌流を招くことがあり、そのため高度の視力低下(永続的な視力低下を含む)を起こす可能性がある。
また、本剤の過量投与により患者の強い光に対する光線過敏状態の期間が延長する。このような場合は、過量投与の量に応じて、光線過敏性反応に対する予防措置を講ずる期間を延長する必要がある。
また、本剤の過量投与により患者の強い光に対する光線過敏状態の期間が延長する。このような場合は、過量投与の量に応じて、光線過敏性反応に対する予防措置を講ずる期間を延長する必要がある。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 光線過敏性反応を誘発する可能性があるので、注射液調製時又は投与時に薬液が眼や皮膚に触れないよう十分注意すること。万一、触れた場合は強い光から保護すること。[8.3.1参照]
14.1.2 本剤1バイアルに日局注射用水7mLを加えて溶解し、ベルテポルフィン2mg/mLを含有する7.5mLの溶液を調製する。バイアルから6mg/m2(体表面積)相当量のビスダイン溶液を吸引し、総量として30mLになるよう日局ブドウ糖注射液(5%)で希釈し、投与用注射液とする。[7.2参照]
14.1.3 本剤は生理食塩液中で沈殿するため、日局注射用水以外の溶解液(生理食塩液等)は使用しないこと。また、他剤との混注は行わないこと。[7.2参照]
14.1.4 溶解、希釈後は使用するまで遮光し、4時間以内に使用すること。[7.2参照]
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 薬液がこぼれた場合は雑巾等で拭き取ること。その際、薬液が皮膚や眼に触れないようにするため、ゴム手袋や防護用のメガネを使用することが望ましい。
14.2.2 投与速度
14.1.2の項に従って調製した投与用注射液の総量30mLを、適切なシリンジポンプとインフュージョン・ラインフィルターを用い、10分間(3mL/分)かけて静脈内に投与する。
14.2.3 本剤の静脈内投与を開始する前に静注ラインを確認し、投与後注意深くモニターする。[7.3参照]
14.2.4 高齢者は静脈壁がぜい弱である可能性が高いので、できるだけ大きな腕の静脈、できれば前肘静脈を用いることが望ましい。[7.3参照]
14.2.5 手背の細い静脈からの投与は避ける。[7.3参照]
14.2.6 本剤の血管外漏出がみられた場合には、直ちに投与を中止し、冷湿布を行うとともに、重度の局所的光過敏反応(日焼け等)が発現するおそれがあるので、腫脹や変色が消退するまで漏出部位を直射日光から完全に保護すること。[7.2参照]
14.3 薬剤交付時の注意[8.3参照]
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
健康成人にビスダイン3、6及び14mg/m2(体表面積)を10分間持続静脈内投与した場合の薬物動態パラメータは次のとおりであった。
| Tmax(h) | Cmax(μg/mL) | AUC0-∞(μg・h/mL) | T1/2(h) | |
| 3mg/m2 | 0.17 | 0.66 | 0.88 | 5.77 |
| 6mg/m2 | 0.17 | 1.32 | 1.75 | 5.72 |
| 14mg/m2 | 0.17 | 3.13 | 4.95 | 5.62 |
血漿中濃度−時間曲線下面積(AUC)及び最高血漿中濃度(Cmax)は、3〜14mg/m2(体表面積)で用量相関性を示した。ベルテポルフィンはその大部分が未変化体として肝臓より排泄される。排泄経路は糞便中排泄であり、尿中での回収率は投与量の0.004%未満である(日本人のデータ)。
海外データにおいても、薬物動態パラメータは3〜14mg/m2で、国内データと同様に用量相関性を示し、また、性別による影響は認められなかった1)。
海外データにおいても、薬物動態パラメータは3〜14mg/m2で、国内データと同様に用量相関性を示し、また、性別による影響は認められなかった1)。
16.4 代謝
動物実験の結果、ベルテポルフィンは肝及び血漿中エステラーゼによってわずかにジカルボン酸代謝物に代謝されることが確認されている。また、NADPH-依存肝酵素系(チトクロームP450アイソザイムを含む)はベルテポルフィンの代謝には関与していないと考えられた。[10.参照]
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 肝機能低下時
海外において、9名の軽度肝機能低下例(2種以上の肝機能検査項目で異常を呈した患者)及び8名の健康成人にビスダイン12mg/m2を45分間かけて持続静脈内投与し、血漿中ベルテポルフィン濃度をHPLCを用いて測定した。投与終了時点(45分後)でCmax(それぞれ1.41及び1.38μg/mL)に到達し、平均AUC0-tは軽度肝機能低下例では健康成人よりも42%高く(それぞれ4.60、3.25μg・h/mL、P=0.068)、この差は静注後1〜12時間持続した。しかしながら両者でCmax及びAUCに有意差はみられなかった。一方、軽度肝機能低下例の消失パラメータ(Kel及びT1/2)は健康成人での報告値と類似していた。T1/2は軽度肝機能低下例で19%の延長がみられたものの、その差の程度は小さく、軽度肝機能低下例においても薬物動態に顕著な違いはないものと考える(外国人のデータ)。
16.6.2 高齢者
65歳以上の患者と65歳未満の対象患者における薬物動態パラメータを共分散分析(ANCOVA)モデルにより解析することで、年齢による影響を検討した結果は次のとおりである。
| ベルテポルフィンの薬物動態パラメータ | 65歳未満 | 65歳以上 | 年齢層の影響※ P値 | ||
| 症例数 | 症例数 | ||||
| AUC0-t(μg・h/mL) | 2.66(24%) | 14 | 3.50(19%) | 7 | 0.022 |
| AUC0-∞(μg・h/mL) | 2.91(27%) | 14 | 3.70(21%) | 7 | 0.067 |
| Cmax(μg/mL) | 1.03(21%) | 14 | 1.14(20%) | 7 | 0.066 |
AUC0-t値は65歳以上群で高く(統計学的有意差あり、P=0.022)、AUC0-∞値にも同様の傾向が認められた(統計学的有意差なし、P=0.067)(外国人のデータ)。[9.8参照]
別の試験で、被験者にビスダイン6mg/m2を10分間持続静脈内投与した結果、平均血漿中濃度は、65歳以上群が65歳未満群に比し、統計学的に有意に高い成績が得られた。投与開始後10分の平均血漿中ベルテポルフィン濃度は、65歳以上群で1.51μg/mL(1.24〜1.82μg/mL)、65歳未満群で1.25μg/mL(0.37〜1.67μg/mL)であった(P=0.034)。持続静脈内投与開始後20分の平均ベルテポルフィン濃度は、65歳以上群で0.78μg/mL(0.51〜1.20μg/mL)、65歳未満群で0.56μg/mL(0.22〜1.12μg/mL)であり、両者の平均血漿中濃度の差は統計学的に有意であった(P=0.01)(外国人のデータ)。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 国内第III相試験
中心窩下CNVを伴う加齢黄斑変性症患者を対象にした非盲検非対照試験を実施した(対象患者数:64例)。本試験の主要評価項目はclassic CNVの進展率(ベースライン以降にclassic CNVの進展が認められた患者の比率)とした。12ヵ月後の結果はclassic CNVの進展率が18.8%、occult CNVの進展率が14.1%であった。また、副次的評価項目の1つである最高矯正視力については、ETDRSチャートでベースラインスコアと比較して12ヵ月後に平均で3.0文字の増加が認められた2)。[18.3参照]
副作用調査対象例数64例中27例(42.2%)に副作用が認められた。治療対象眼における主なものは視覚障害(視覚異常、視力低下)8例(12.5%)、眼の異常感2例(3.1%)等であり、全身性の主なものは頭痛3例(4.7%)等であった。
17.1.2 海外第III相試験
中心窩下にclassic CNVを有する加齢黄斑変性症患者を対象にしたプラセボ対照二重盲検試験(TAP試験)を実施した(合計登録患者数:609例、ビスダイン群402例、プラセボ群207例)。24ヵ月時点において、classic CNVの進展率はビスダイン群23.1%、プラセボ群53.6%、occult CNVの進展率はビスダイン群37.1%、プラセボ群50.7%、平均最高矯正視力はビスダイン群で13.4文字の低下、プラセボ群で19.6文字の低下であった。本試験の主要評価項目であるレスポンダーの比率(ETDRSチャートによる視力の低下が15文字(3ライン)未満の患者の比率)では、24ヵ月後でビスダイン群はプラセボ群より統計学的に有意に優れていた。治療群間の差は15.3%(ビスダイン群53.0%、プラセボ群37.7%、p<0.001)であった3)4)。[18.3参照]
副作用調査対象例数402例中192例(47.8%)に副作用が認められた。治療対象眼における主なものは視覚障害(視覚異常、視力低下、視野欠損)50例(12.4%)等であり、全身性の主なものは注射部位の副作用58例(14.4%)等であった。
17.1.3 海外第III相試験
視力が比較的良好な加齢黄斑変性症患者及びclassic CNVのないoccult CNV患者を対象にしたプラセボ対照二重盲検試験(VIP試験)を実施した(合計登録患者数:339例、ビスダイン群225例、プラセボ群114例)。24ヵ月間のフォローアップの結果、本試験の主な対象であるclassic CNVのないoccult CNV患者において、classic CNVの進展率はビスダイン群17.5%、プラセボ群38.0%、occult CNVの進展率はビスダイン群46.4%、プラセボ群56.5%、平均最高矯正視力はビスダイン群で19.0文字の低下、プラセボ群で25.5文字の低下であった。本試験の主要評価項目であるレスポンダーの比率(15文字未満)は、ビスダイン群45.2%、プラセボ群31.5%で、統計学的有意差がみられた(p=0.032)5)。[18.3参照]
副作用調査対象例数225例中96例(42.7%)に副作用が認められた。治療対象眼における主なものは視覚障害(視覚異常、視力低下、視野欠損)67例(29.8%)等であり、全身性の主なものは注射部位の副作用15例(6.7%)等であった。
17.1.4 海外第I/II相試験
中心窩下CNVを有する患者を対象に用量設定試験(合計登録患者数:142例)を実施したところ、治療後のclassic CNVの完全閉塞率が4週間後に低下し、再治療の必要性が示唆された。約4週間の間隔で2〜3回の再治療を受けた患者の視力の転帰(−1.0ライン、16週目:7例、20週目:2例)は1回のみの治療を受けた患者の視力の転帰(+0.4ライン、12週目:11例)と大きな差異が認められなかったため、本剤の再治療については、3ヵ月毎の検査結果により実施することとした6)7)。[7.1参照]
副作用調査対象例数142例中42例(30%)に副作用が認められた。治療対象眼における主なものは網膜下出血(新生又は増加)14例(10%)等であり、全身性の主なものは頭痛4例(3%)等であった。
17.2 製造販売後調査等
市販後臨床試験として、classic CNVのないoccult CNV患者を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験(VIO試験)を実施した(合計登録患者数:364例、ビスダイン群244例、プラセボ群120例)。24ヵ月の時点において、平均最高矯正視力はビスダイン群で14.8文字の低下、プラセボ群で17.8文字の低下となり、本試験の主要評価項目であるレスポンダーの比率は、ビスダイン群とプラセボ群との間に統計学的有意差はみられなかった(15文字未満:ビスダイン群53.3%、プラセボ群47.5%、p=0.300;30文字未満:ビスダイン群77.5%、プラセボ群75.0%、p=0.602)8)。
17.3 その他
海外のプラセボ対照比較試験の結果(上記17.1.2、17.1.3のサブグループ解析並びに17.2の試験結果)、predominantly classic CNVでは、本剤の有効性(視力低下抑制)はプラセボ群と比較して統計学的有意差がみられたが、minimally classic CNVでは統計学的有意差はみられなかった(TAP試験)。Occult CNV患者については、VIP試験では本剤の有効性はプラセボ群と比較して統計学的有意差がみられたが、市販後に本剤の有効性を確認する目的で実施されたVIO試験では統計学的有意差はみられなかった。[5.参照]
| 24ヵ月後におけるベースラインと比較した平均最高矯正視力の変化量(平均値±標準誤差) | 24ヵ月後におけるレスポンダーの比率※ | ||
| Predominantly classic CNV(TAP試験)#1 | ビスダイン群(n=159):−11.7±1.4 プラセボ群(n=83):−22.6±2.0 p<0.001 | ビスダイン群:59.1% プラセボ群:31.3% p<0.001 | |
| Minimally classic CNV(TAP試験)#1 | ビスダイン群(n=202):−14.9±1.4 プラセボ群(n=104):−17.0±1.7 p=0.340 | ビスダイン群:47.5% プラセボ群:44.2% p=0.584 | |
| Occult CNV | VIP試験#2 | ビスダイン群(n=166):−19.0±1.6 プラセボ群(n=92):−25.5±2.1 p=0.002 | ビスダイン群:45.2% プラセボ群:31.5% p=0.032 |
| VIO試験#3 | ビスダイン群(n=244):−14.8±1.3 プラセボ群(n=120):−17.8±1.6 p=0.138 | ビスダイン群:53.3% プラセボ群:47.5% p=0.300 | |
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
本PDTは2段階のプロセスからなっており、ベルテポルフィンの静脈内注入と眼科用光線力学的療法用レーザー(非発熱性ダイオードレーザー)による光照射の両治療が必要である。ベルテポルフィンは血漿中では主として低密度リポ蛋白(LDL)によって輸送され、内皮細胞のLDL-receptorと結合する。ベルテポルフィンは新生血管(CNVを含む)にある程度選択的に蓄積する。ベルテポルフィンがCNVにおいて酸素の存在下で光によって活性化されると反応性が高く、短寿命の一重項酸素と反応性酸素ラジカルが発生する9)10)11)。CNVでのベルテポルフィンの光による活性化により新生血管内皮が局所的に損傷を受け、その結果、血管閉塞が起こる12)13)14)。損傷した内皮はリポキシゲナーゼ経路及びシクロオキシゲナーゼ経路を介して、凝固促進因子や血管活性因子を遊離して、血小板凝集、フィブリンクロット(線維素塊)形成並びに血管収縮を招くことが確認されている。
18.2 標的組織への集積
18.3 CNV閉塞作用
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. ベルテポルフィン
21. 承認条件
本剤による光線力学的療法についての講習を受け、本剤使用にかかわる安全性及び有効性について十分に理解し、本剤の調製、投与、レーザーによる光照射に関する十分な知識・経験のある医師のみによって使用されるよう、必要な措置を講じること。
22. 包装
1バイアル
23. 主要文献
- 社内資料:第I相試験(2003年10月16日承認、申請資料概要 ヘ-37)
- The Japanese Age-Related Macular Degeneration Trial(JAT)Study Group, Am.J.Ophthalmol., 136 (6), 1049-1061, (2003)
- Treatment of Age-Related Macular Degeneration with Photodynamic Therapy(TAP)Study Group, Arch.Ophthalmol., 119 (2), 198-207, (2001)
- 社内資料:第III相試験(2003年10月16日承認、申請資料概要 ト-116)
- Verteporfin in Photodynamic Therapy Study Group, Am.J.Ophthalmol., 131 (5), 541-560, (2001)
- Miller,J.W.et al., Arch.Ophthalmol., 117 (9), 1161-1173, (1999) »PubMed
- Schmidt-Erfurth,U.et al., Arch.Ophthalmol., 117 (9), 1177-1187, (1999) »PubMed
- 社内資料:VIO試験(Visudyne in Occult study)
- Aveline,B.et al., Photochem.Photobiol., 59 (3), 328-335, (1994) »PubMed
- Fernandez,J.M.et al., J.Photochem.Photobiol.B Biol., 37 (1-2), 131-140, (1997)
- Hadjur,C.et al., Photochem.Photobiol., 65 (5), 818-827, (1997)
- Kramer,M.et al., Ophthalmology., 103 (3), 427-438, (1996) »PubMed
- Miller,J.W.et al., Arch.Ophthalmol., 113 (6), 810-818, (1995) »PubMed
- Schmidt-Erfurth,U.et al., Lasers Surg.Med., 17 (2), 178-188, (1995) »PubMed
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
チェプラファーム株式会社
メディカルインフォメーションセンター
〒101-0021
東京都千代田区外神田4丁目14-1
電話:0120-772-073
製品情報問い合わせ先
チェプラファーム株式会社
メディカルインフォメーションセンター
〒101-0021
東京都千代田区外神田4丁目14-1
電話:0120-772-073
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
チェプラファーム株式会社
東京都千代田区外神田4丁目14-1