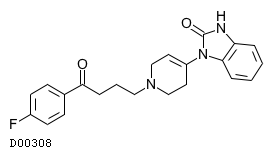医薬品情報
| 総称名 | ドロレプタン |
|---|---|
| 一般名 | ドロペリドール |
| 欧文一般名 | Droperidol |
| 製剤名 | ドロペリドール注射液 |
| 薬効分類名 | 麻酔用神経遮断剤 |
| 薬効分類番号 | 1119 |
| KEGG DRUG |
D00308
ドロペリドール
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年3月 改訂(第2版)

|
2.禁忌 4.効能または効果 6.用法及び用量 7.用法及び用量に関連する注意 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 14.適用上の注意 16.薬物動態 17.臨床成績 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 20.取扱い上の注意 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドロレプタン注射液25mg | DROLEPTAN Injection 25mg | アルフレッサファーマ | 1119401A1036 | 93円/mLV | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
○フェンタニルとの併用による、手術、検査、および処置時の全身麻酔並びに局所麻酔の補助
○ドロペリドールの単独投与による麻酔前投薬
6. 用法及び用量
○フェンタニルクエン酸塩との併用による場合
導入麻酔剤として投与する場合には通常成人ドロレプタン注射液0.1〜0.2mL/kg(ドロペリドールとして0.25〜0.5mg/kg)をフェンタニル注射液0.1〜0.2mL/kg(フェンタニルクエン酸塩として7.85〜15.7μg/kg)と共に緩徐に静注するか、またはブドウ糖液等に希釈して点滴静注する。
局所麻酔の補助として投与する場合には局所麻酔剤投与10〜15分後に通常成人ドロレプタン注射液0.1mL/kg(ドロペリドールとして0.25mg/kg)をフェンタニル注射液0.1mL/kg(フェンタニルクエン酸塩として7.85μg/kg)と共に緩徐に静注する。
なお、患者の年齢・症状に応じて適宜増減する。
○ドロペリドール単独で麻酔前投薬として投与する場合
通常成人ドロレプタン注射液0.02〜0.04mL/kg(ドロペリドールとして0.05〜0.1mg/kg)を麻酔開始30〜60分前に筋注する。
なお、患者の年齢・症状に応じて適宜増減する。
なお、患者の年齢・症状に応じて適宜増減する。
7. 用法及び用量に関連する注意
本剤の用法及び用量は、患者の感受性、全身状態、手術々式、麻酔方法等に応じてきめるが、一般にフェンタニルとの併用による導入麻酔・局所麻酔、また本剤単独投与による麻酔前投薬は通常次のとおり行われている。
7.1 導入麻酔剤として
アトロピン硫酸塩水和物など通常の麻酔前投薬に引き続き、本剤及びフェンタニルの1回量を緩徐に静注(点滴静注が安全で確実)する。なお症例により、同時にGO、GOF等の吸入麻酔やチアミラール等の静注用全身麻酔剤の併用も行われる。
7.2 局所麻酔の補助として
メピバカイン等による持続硬膜外麻酔の補助として本剤を併用する(症例によっては、全身麻酔や気管内挿管を必要としないで手術可能な例もある)。
7.3 麻酔前投薬として
通常麻酔開始30分〜1時間前に本剤1回量の筋注を行う。
投与後10〜30分後にはほとんどの例に十分な鎮静効果が得られる。
なお症例により、アトロピン硫酸塩水和物が併用される場合もある。
投与後10〜30分後にはほとんどの例に十分な鎮静効果が得られる。
なお症例により、アトロピン硫酸塩水和物が併用される場合もある。
8. 重要な基本的注意
8.1 本剤の使用に際しては、一般の全身麻酔剤と同様、必ず気道確保、呼吸管理等の蘇生設備の完備された場所で、麻酔医の管理の下に使用すること。
8.2 麻酔を行う際にはあらかじめ絶食をさせておくこと。
8.3 麻酔を行う際には原則として麻酔前投薬を行うこと。
8.4 麻酔中は気道に注意して呼吸・循環に対する観察を怠らないこと。
8.5 麻酔の深度は手術、検査に必要な最低の深さにとどめること。
8.6 麻酔前に酸素吸入器、吸引器具、挿管器具等の人工呼吸のできる器具を手もとに準備しておくことが望ましい。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 パーキンソン病等錐体外路系疾患の患者
過量投与により錐体外路症状を呈することがある。
9.1.2 心疾患のある患者(重篤な心疾患を有する患者、QT延長症候群のある患者を除く)
9.1.3 poor risk状態の患者
適宜減量すること。錐体外路系症状等の副作用が発現し易い。
9.1.4 褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者
異常な血圧上昇を起こすことがある。
9.2 腎機能障害患者
血中濃度が高くなるため、副作用発現の危険性が増加する。
9.3 肝機能障害患者
血中濃度が高くなるため、副作用発現の危険性が増加する。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
マウスに本剤を投与した試験(15・40mg/kg 妊娠7日目から6日 腹腔内)において、40mg/kg投与群に骨格(胸椎骨、肋骨)異常、生児平均体重の減少が認められている。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
9.7 小児等
新生児、乳児及び2歳以下の幼児には投与しないこと。小児等を対象とした臨床試験は実施していない。[2.6参照]
9.8 高齢者
減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。錐体外路系症状等の副作用が発現し易い。
10. 相互作用
10.2 併用注意
| 中枢神経系抑制剤 バルビツール酸系薬剤、向精神薬、麻薬性鎮痛剤等 MAO阻害剤 | 中枢神経抑制作用が増強され覚醒が遅延することがある。 | 相加的に中枢神経抑制作用が増強される。 |
| β-遮断剤 | 血圧降下、頻脈等の心毒性が増強されるおそれがある。 | 本剤の心血管系に対する作用がβ-遮断剤により増強される。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 血圧降下(頻度不明)
血圧降下があらわれた場合には輸液を行い、更に必要な場合は昇圧剤(アドレナリンを除く)の投与を行うこと。なお、本剤を腰椎麻酔、硬膜外麻酔に併用すると、更に血圧降下を招くおそれがあるので、このような場合には慎重に投与すること。
11.1.2 不整脈(頻度不明)、期外収縮(頻度不明)、QT延長(頻度不明)、心室頻拍(Torsades de pointesを含む)(頻度不明)、心停止(頻度不明)
11.1.3 ショック(頻度不明)
11.1.4 間代性痙攣(頻度不明)
11.1.5 悪性症候群(頻度不明)
体温上昇、筋硬直、不安、混乱、昏睡、CK上昇等があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。ダントロレン、ブロモクリプチン、ECTが効果的であったとの報告がある。
11.2 その他の副作用
| 1%以上 | 1%未満 | 頻度不明 | |
| 過敏症 | − | − | そう痒、紅斑、じん麻疹 |
| 呼吸器 | 呼吸抑制 | − | − |
| 循環器 | − | − | 起立性低血圧注)、頻脈、徐脈、血圧上昇 |
| 精神神経系 | − | 頭痛、気分動揺、不眠 | せん妄、傾眠、錐体外路症状、覚醒遅延、ふるえ、めまい、興奮 |
| 肝臓 | − | − | AST上昇、ALT上昇 |
| その他 | 悪心・嘔吐、発汗、咽頭痛 | 喘鳴、吃逆、四肢冷感、体温降下、嗄声 | 喀痰排出増加、喀痰排出困難、発熱、口渇 |
14. 適用上の注意
14.1 薬剤投与時の注意
筋肉内注射にあたっては、組織・神経などへの影響を避けるため、次の点に配慮すること。
・神経走行部位を避けるよう注意して注射すること。
・繰り返し注射する場合には、同一注射部位を避けること。
・注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き部位をかえて注射すること。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
健康男性3例に3H-ドロペリドール5mgを静注投与した場合、ドロペリドールの血漿中濃度は投与後30分で約30ng/mLに低下し、以後緩やかに漸減した。また、健康男性9例に3H-ドロペリドール5mgを筋注投与した場合、吸収は速く、その血漿中濃度の推移は静注と類似していた1)(外国人データ)。
16.3 分布
ラットに3H-ドロペリドール1.6mg/kgを皮下注し、臓器中の放射活性を測定した結果、肝・腎では投与後30分、血液その他の臓器では15分後に最高値を示し、いずれの臓器においても急速に低下し、蓄積傾向は認められなかった。
16.5 排泄
健康男性3例に3H-ドロペリドール5mgを静注投与した場合、投与後96時間以内に投与量の約75%相当の代謝物及び1%未満の未変化体が尿中に排泄された2)(外国人データ)。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
<フェンタニルとの併用による、手術、検査、および処置時の全身麻酔並びに局所麻酔の補助>
17.1.1 国内臨床試験
1,413例について、導入麻酔、維持麻酔及び局所麻酔の補助の目的で、臨床試験が実施された結果、すぐれた鎮静効果と鎮痛効果が認められた。主な副作用は、悪心・嘔吐(5.2%)、発汗(4.1%)、咽頭痛(3.6%)、粘液分泌過多(2.5%)であった。
<ドロペリドールの単独投与による麻酔前投薬>
17.1.2 国内臨床試験
147例について臨床試験が実施された結果、通常麻酔開始20分〜1時間前にドロペリドールとして2.5〜5mgずつ筋注又は点滴静注するとき、鎮静効果は97.2%(143/147例)、催眠効果は69.6%(87/125例)に認められた。副作用は2.7%(4/147例)に認められた。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
ドーパミン拮抗作用(D2受容体)、ヒスタミン拮抗作用、セロトニン拮抗作用を有する。
18.2 鎮静作用
18.3 効果の発現と持続
通常用量では、作用は静注後2〜3分であらわれ、周囲に全く無関心となるMineralizationの状態が約30分続くが、鎮静状態はなお6〜12時間持続する。
18.4 制吐作用
18.5 α-受容体遮断作用
18.6 麻酔の補助
18.6.1 本剤はイヌの静脈内投与で、チオペンタールの麻酔時間を延長させることが認められている。
18.6.2 本剤は前記の作用から、麻酔用神経遮断剤として、運動反射抑制、精神的無関心、自律神経系の安定化を伴った神経遮断状態をもたらすので、麻酔前投薬としてのみでなく、鎮痛剤フェンタニル注射液(フェンタニルクエン酸塩)との併用により、いわゆるNeuroleptanalgesia注)の状態を得ることができ、特に大手術及び長時間にわたる手術時に使用されている2)3)。
注)Neuroleptanalgesiaの特長は、意識の消失なしに鎮痛効果と鎮静効果の得られることで、無痛状態を得ると同時に、安静、周囲の環境に対する無関心、自律神経系の安定、さらに高度の非被刺激性が得られ、精神科領域でいうMineralizationの状態(無生物のように情動表出のなくなった状態)となり、この状態では、患者は手術に伴う苦痛もなく、患者と術者との間に意志の疎通のある状態で手術を行うことができる。
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. ドロペリドール
20. 取扱い上の注意
外箱開封後は遮光して保存すること。
22. 包装
10mL[1バイアル]
23. 主要文献
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
アルフレッサファーマ株式会社
製品情報部
〒540-8575
大阪市中央区石町二丁目2番9号
電話:06-6941-0306
FAX:06-6943-8212
製品情報問い合わせ先
アルフレッサファーマ株式会社
製品情報部
〒540-8575
大阪市中央区石町二丁目2番9号
電話:06-6941-0306
FAX:06-6943-8212
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
アルフレッサファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号