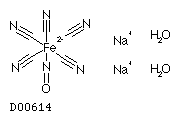医薬品情報
| 総称名 | ニトプロ |
|---|---|
| 一般名 | ニトロプルシドナトリウム水和物 |
| 欧文一般名 | sodium nitroprusside hydrate |
| 製剤名 | ニトロプルシドナトリウム水和物注射液 |
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| 薬効分類番号 | 2149 |
| ATCコード | C02DD01 |
| KEGG DRUG |
D00614
ニトロプルシドナトリウム水和物
|
| KEGG DGROUP |
DG03231
血圧降下薬
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2021年8月 改訂(効能変更)(第1版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニトプロ持続静注液6mg | NITOPRO CONTINUOUS INTRAVENOUS SOLUTION | 丸石製薬 | 2149401A1030 | 616円/管 | 毒薬, 処方箋医薬品注) |
| ニトプロ持続静注液30mg | NITOPRO CONTINUOUS INTRAVENOUS SOLUTION | 丸石製薬 | 2149401A2036 | 2429円/管 | 毒薬, 処方箋医薬品注) |
1. 警告
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
2.1 脳に高度な循環障害のある患者[脳循環が抑制されるおそれがある。]
2.2 甲状腺機能不全の患者[代謝物のチオシアンにより甲状腺機能が低下する場合がある。][9.1.2参照]
2.3 レーベル病(遺伝性視神経萎縮症)、たばこ弱視あるいはビタミンB12欠乏症の患者[シアンの解毒処理能力が低下している場合がある。]
2.4 重篤な肝機能障害のある患者[9.3.1参照]
2.5 重篤な腎機能障害のある患者[9.2.1参照]
2.6 高度な貧血の患者[血圧低下により貧血症状(めまい等)を悪化させるおそれがある。]
2.7 ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤(シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル)又はグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤(リオシグアト)を投与中の患者[10.1参照]
4. 効能または効果
6. 用法及び用量
本剤は、5%ブドウ糖注射液で希釈し、ニトロプルシドナトリウム水和物として0.06〜0.1%(1mL当たり0.6〜1mg)溶液を持続静注する。
<手術時の低血圧維持>
通常、成人には1分間に体重1kg当たりニトロプルシドナトリウム水和物として0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節する。通常、2.5μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。なお、最高投与速度は3μg/kg/分を限度とする。また、開始投与速度は年齢、症状により適宜減量する。
<手術時の異常高血圧の救急処置>
通常、成人には1分間に体重1kg当たりニトロプルシドナトリウム水和物として0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的値まで血圧を下げ、以後血圧をモニターしながら投与速度を調節する。通常、2.0μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血圧が得られ、それを維持することができる。なお、最高投与速度は3μg/kg/分を限度とする。また、開始投与速度は年齢、症状により適宜減量する。
<急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)、高血圧性緊急症>
通常、小児には1分間に体重1kg当たりニトロプルシドナトリウム水和物として0.5μg/kg/分の投与速度で投与を開始し、過度の血圧低下に注意しながら徐々に増量して目的とする血行動態を得るまで循環動態をモニターしながら投与速度を調節する。通常、3.0μg/kg/分以下の投与速度で目的とする血行動態が得られ、それを維持することができる。なお、最高投与速度は10μg/kg/分を限度とする。また、開始投与速度は年齢、症状により適宜減量する。
7. 用法及び用量に関連する注意
<効能共通>
<急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)、高血圧性緊急症>
8. 重要な基本的注意
8.1 低血圧を必要とする手術ではECG、導尿等により、心機能や腎機能を監視すること。
8.2 呼吸抑制があらわれることがあるので、呼吸管理に注意すること。また、本剤の投与により動脈血酸素分圧(PaO2)が低下することがあるので、本剤の投与中はPaO2又は動脈血酸素飽和度(SaO2)の監視を行い、必要に応じて吸入酸素濃度(FiO2)の調節を行うこと。なお、PaO2低下時に酸素吸入が行われていない場合は投与を中止し、速やかに酸素吸入を行うこと。[11.2参照]
8.3 投与終了後は、患者の血圧が完全に回復するまで管理を行うこと。
8.4 本剤の投与で代謝物によるシアン中毒を生じるおそれがあるので、血圧や心拍数の他に、心電図、血液ガス及び酸塩基平衡をモニターすること。本剤の使用に際しては日局 チオ硫酸ナトリウム水和物、日局 亜硝酸アミル又は亜硝酸ナトリウム注)をあらかじめ用意し、救急処置の準備をしておくことが望ましい。また、硬膜外麻酔等施行時の局所麻酔薬の副作用や全身麻酔覚醒時の症状の中には、頭痛、めまい、嘔気、嘔吐等のように、シアン中毒時の自覚症状と類似するものがあるので、これらの症状があらわれた場合も血液ガス及び酸塩基平衡等を観察し、シアン中毒を疑わせる場合は同様の処置を行うこと。血中シアン濃度の上昇には個人差があり、特に肥満患者においては高値を示すことがあるので、投与速度に注意し、慎重に投与すること。なお、外国ではニトロプルシドナトリウム水和物の過量投与によるシアン中毒の死亡例も報告されている。[1.3、7.2、9.1.6、11.1.3、13.1参照]
注)亜硝酸ナトリウムについては医薬品として市販されていない。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 頭部外傷又は脳出血による血腫などの頭蓋内圧亢進症の患者
頭蓋内圧を上昇させる。
9.1.2 甲状腺機能の低下した患者
代謝物のチオシアンにより甲状腺機能が低下する場合がある。[2.2参照]
9.1.3 心機能障害のある患者
冠循環が抑制されるおそれがある。
9.1.4 著しく血圧の低い患者
血圧低下をさらに悪化させるおそれがある。
9.1.5 本剤の添加剤カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物に対し過敏症の既往歴のある患者
9.1.6 極度な肥満の患者
9.2 腎機能障害患者
9.3 肝機能障害患者
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で、乳汁中に移行することが報告されている。
9.7 小児等
<手術時の低血圧維持、手術時の異常高血圧の救急処置>
小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
9.8.1 75歳以上の高齢者
75歳以上の高齢者を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。[7.1参照]
9.8.2 75歳未満の高齢者
手術患者を対象にして行われた臨床試験において、手術時の低血圧維持における主投与速度の平均は高齢者(65歳以上)で1.14μg/kg/分、非高齢者で1.45μg/kg/分と高齢者で遅かった。また、手術時の異常高血圧の救急処置においても、主投与速度の平均は高齢者で0.65μg/kg/分、非高齢者で1.36μg/kg/分と高齢者で遅かった。このように、高齢者では降圧維持に必要な投与速度が非高齢者に比べて遅く、本剤の血圧低下作用が強くあらわれやすいと考えられるので、低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
また、手術時の低血圧維持の臨床試験において、高齢者にPaO2低下等の副作用発現率が高い傾向が認められているので注意すること。[7.1参照]
また、手術時の低血圧維持の臨床試験において、高齢者にPaO2低下等の副作用発現率が高い傾向が認められているので注意すること。[7.1参照]
10. 相互作用
10.1 併用禁忌
| ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤 シルデナフィルクエン酸塩(バイアグラ、レバチオ)、バルデナフィル塩酸塩水和物(レビトラ)、タダラフィル(シアリス、アドシルカ、ザルティア) [2.7参照] | 併用により、降圧作用が増強することがあるため、本剤投与前、投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服用しないよう十分に注意すること。 | 本剤はcGMPの産生を促進し、一方、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤はcGMPの分解を抑制することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強する。 |
| グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤 リオシグアト(アデムパス) | 併用により、降圧作用が増強することがあるため、本剤投与前、投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服用しないよう十分に注意すること。 | 本剤とグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤は、ともにcGMPの産生を促進することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強する。 |
10.2 併用注意
| 吸入麻酔剤(セボフルラン等) | 血圧低下が増強されることがあるので、本剤の用量を調節するなど注意すること。 | 吸入麻酔剤の降圧作用及び圧反射機能の抑制作用によると考えられる。 |
| 降圧作用を有する薬剤(ニカルジピン塩酸塩、プラゾシン塩酸塩、エスモロール塩酸塩等) | 血圧低下が増強されることがあるので、本剤の用量を調節するなど注意すること。 | 他の降圧作用を有する薬剤との相乗・相加作用によるものと考えられる。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 過度の低血圧(0.1〜5%未満)
11.1.2 リバウンド現象(0.1〜5%未満)
必要に応じて降圧剤を投与するなど適切な処置を行うこと。特に、手術時の異常高血圧の救急処置に用いる場合に起こりやすいので注意すること。[7.3参照]
11.1.3 シアン中毒(頻度不明)
11.2 その他の副作用
| 5%以上 | 0.1〜5%未満 | 頻度不明 | |
| 循環器 | 頻脈、不整脈、心電図異常 | ||
| 呼吸器 | PaO2低下注) | ||
| 肝臓 | 肝機能検査値異常(ビリルビン上昇、AST上昇、ALT上昇 等) | ||
| 血液 | 一酸化炭素ヘモグロビン増加 | ||
| その他 | 代謝性アシドーシス |
13. 過量投与
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 本剤は強力な降圧作用を有するので、必ず希釈して用いること。
14.1.2 調製後は速やかに使用し、残液は廃棄すること。
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 本剤の投与には必ずシリンジポンプを使用すること。一時的な大量注入により過剰な低血圧が生ずる危険を防ぐため、投与ラインは屈曲しないように適度な長さのものを使用し、また、三方活栓を介して本剤を投与する時は、注射部位からできるだけ近位に三方活栓を設置すること。
14.2.2 投与終了後は投与ラインの残存液にも注意すること。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
健常人6例に0.5、1.0及び2.0μg/kg/分を各20分間ずつ投与し、1時間静脈内持続投与した時、未変化体の血漿中濃度は投与速度の増加に伴って上昇し、投与終了後は速やかに減少した。半減期は約1分であった1)。
未変化体の血漿中濃度
| 0.5μg/kg/分 終了時の濃度(μg/mL) | 1.0μg/kg/分 終了時の濃度(μg/mL) | 2.0μg/kg/分 終了時の濃度(μg/mL) | T1/2(min.sec) | AUC0→∞(μg・min/mL) |
| 0.0068±0.0011 | 0.0168±0.0032 | 0.0376±0.0082 | 1m02s±0m15s | 1.278±0.200 |
16.3 分布
血漿蛋白結合率
ヒト血清 83.1〜84.7%2)
16.4 代謝
代謝物としてシアンが生成されたが、更に速やかに生体内に存在するチオシアンに代謝され、シアンの半減期は約12分であった1)。
16.5 排泄
未変化体及びシアンの尿中排泄は認められず、チオシアンの尿中排泄量の増加が認められた1)。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
<手術時の低血圧維持>
17.1.1 国内第III相比較試験
全身吸入麻酔による手術施行患者173例を対象に、ニトロプルシドナトリウム水和物(SNP、87例)あるいはニトログリセリン(NTG、86例)の静脈内持続投与を行った。SNPは0.5μg/kg/分の投与速度で開始し、原則として3.0μg/kg/分を超えない範囲で血圧を調節した。降圧効果(「下降」以上)はSNPで98.9%、NTGで89.3%、血圧調節性(「良い」以上)はSNPで86.0%、NTGで53.6%であり、いずれもSNPが統計的に有意に優れていた。SNPの副作用は、87例中2例(2.3%)にみられ、PaO2低下及びECG異常が各1例であった3)。
17.1.2 国内第III相一般臨床試験
低血圧麻酔施行患者120例を対象に、0.5〜2.5μg/kg/分で投与を開始し、原則として3.0μg/kg/分を超えない範囲で静脈内持続投与を行い、血圧を維持した。降圧効果(「下降」以上)は96.6%、血圧調節性(「良い」以上)は84.0%であった。副作用は120例中10例(8.3%)にみられ、すべてPaO2低下であった4)。
<手術時の異常高血圧の救急処置>
17.1.3 国内第III相比較試験
ニューロレプト麻酔による手術中に血圧が上昇した患者152例を対象に、SNP(77例)あるいはNTG(75例)の静脈内持続投与を行った。SNPは0.5μg/kg/分の投与速度で開始し、投与速度を調節し目標血圧を維持した。降圧効果(「下降」以上)はSNPで98.7%、NTGで94.6%であり、同等であった。また、血圧安定度(「良好」以上)はSNPで83.1%、NTGで79.7%であり、差はなかった。SNPの副作用は、77例中17例(22.1%)にみられ、PaO2低下が15例、リバウンドが3例であった5)。
17.1.4 国内第III相一般臨床試験
手術中に血圧が上昇した患者104例を対象に、0.3〜2.0μg/kg/分で静脈内持続投与を開始し、投与速度を調節し目標血圧を維持した。降圧効果(「下降」以上)は95.2%、血圧安定度(「良好」以上)は77.9%であった。副作用は、104例中5例(4.8%)にみられ、PaO2低下が4例、リバウンドが1例であった6)。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
18.2 人為低血圧効果
18.3 抗高血圧効果
セボフルラン麻酔下の高血圧自然発症ラット(SHR)にSNPを1.5〜6.0μg/kg/分の投与速度で1時間静脈内持続投与すると、SNP投与直後より血圧は速やかに低下し、投与量に応じた降圧効果が得られた13)。
18.4 主要臓器循環
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. ニトロプルシドナトリウム水和物
20. 取扱い上の注意
外箱開封後は、遮光して保存すること。
22. 包装
<ニトプロ持続静注液6mg>
2mL[10アンプル]
<ニトプロ持続静注液30mg>
10mL[10アンプル]
23. 主要文献
- 池田和之 他, 薬理と治療, 22 (7), 3183-3195, (1994)
- 長 敏夫 他, 薬理と治療, 22 (Suppl.8), S2227-S2230, (1994)
- 池田和之 他, 麻酔と蘇生, 30 (3), 205-215, (1994)
- 山本 亨 他, 麻酔と蘇生, 30 (3), 185-193, (1994)
- 清水禮壽 他, 麻酔と蘇生, 30 (3), 169-183, (1994)
- 坂部武史 他, 麻酔と蘇生, 30 (3), 195-203, (1994)
- M.Inoue et al., Arch.Int.Pharmacodyn., 311 (1), 104-121, (1991)
- 濱口政巳 他, 薬理と治療, 22 (Suppl.8), S2089-S2102, (1994)
- 古謝武志 他, 薬理と治療, 22 (Suppl.8), S2115-S2122, (1994)
- 馬越史歩 他, 薬理と治療, 24 (3), 537-547, (1996)
- 馬越史歩 他, 薬理と治療, 22 (Suppl.8), S2133-S2140, (1994)
- 濱口政巳 他, 薬理と治療, 23 (10), 2501-2521, (1995)
- 馬越史歩 他, 薬理と治療, 24 (3), 549-561, (1996)
- 高田文行 他, 薬理と治療, 22 (11), 4635-4641, (1994)
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
丸石製薬株式会社
学術情報部
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中2-4-2
電話:0120-014-561
製品情報問い合わせ先
丸石製薬株式会社
学術情報部
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中2-4-2
電話:0120-014-561
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2