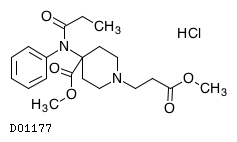医薬品情報
| 総称名 | レミフェンタニル |
|---|---|
| 一般名 | レミフェンタニル塩酸塩 |
| 欧文一般名 | Remifentanil Hydrochloride |
| 製剤名 | 静注用レミフェンタニル塩酸塩 |
| 薬効分類名 | 全身麻酔用・集中治療用鎮痛剤 |
| 薬効分類番号 | 8219 |
| ATCコード | N01AH06 |
| KEGG DRUG |
D01177
レミフェンタニル塩酸塩
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2022年8月 改訂(効能変更、用量変更)(第1版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 (後発品) | REMIFENTANIL FOR INTRAVENOUS INJECTION"DAIICHI SANKYO" | 丸石製薬 | 8219401D1030 | 935円/瓶 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品注) |
| レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 (後発品) | REMIFENTANIL FOR INTRAVENOUS INJECTION"DAIICHI SANKYO" | 丸石製薬 | 8219401D2036 | 2043円/瓶 | 劇薬, 麻薬, 処方箋医薬品注) |
1. 警告
本剤は添加剤としてグリシンを含むため、硬膜外及びくも膜下への投与は行わないこと。
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
2.1 本剤の成分又はフェンタニル系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者[10.1参照]
4. 効能または効果
○成人:全身麻酔の導入及び維持における鎮痛
○小児:全身麻酔の維持における鎮痛
○集中治療における人工呼吸中の鎮痛
6. 用法及び用量
<成人:全身麻酔の導入及び維持における鎮痛>
成人では他の全身麻酔剤を必ず併用し、下記用量を用いる。
麻酔導入
通常、レミフェンタニルとして0.5μg/kg/分の速さで持続静脈内投与する。なお、ダブルルーメンチューブの使用、挿管困難等、気管挿管時に強い刺激が予想される場合には、1.0μg/kg/分とすること。また、必要に応じて、持続静脈内投与開始前にレミフェンタニルとして1.0μg/kgを30〜60秒かけて単回静脈内投与することができる。ただし、気管挿管を本剤の投与開始から10分以上経過した後に行う場合には単回静脈内投与の必要はない。
麻酔維持
通常、レミフェンタニルとして0.25μg/kg/分の速さで持続静脈内投与する。なお、投与速度については、患者の全身状態を観察しながら、2〜5分間隔で25〜100%の範囲で加速又は25〜50%の範囲で減速できるが、最大でも2.0μg/kg/分を超えないこと。浅麻酔時には、レミフェンタニルとして0.5〜1.0μg/kgを2〜5分間隔で追加単回静脈内投与することができる。
<小児:全身麻酔の維持における鎮痛>
1歳以上の小児では他の全身麻酔剤を必ず併用し、下記用量を用いる。
麻酔維持
通常、レミフェンタニルとして0.25μg/kg/分の速さで持続静脈内投与する。なお、投与速度については、患者の全身状態を観察しながら、2〜5分間隔で25〜100%の範囲で加速又は25〜50%の範囲で減速できるが、最大でも1.3μg/kg/分を超えないこと。浅麻酔時には、レミフェンタニルとして1.0μg/kgを2〜5分間隔で追加単回静脈内投与することができる。
<集中治療における人工呼吸中の鎮痛>
通常、成人には、レミフェンタニルとして0.025μg/kg/分の速さで持続静脈内投与を開始し、患者の全身状態を観察しながら、適切な鎮痛が得られるよう、投与速度を適宜調節する。投与速度の調節は5分以上の間隔で、0.1μg/kg/分までは最大0.025μg/kg/分ずつ加速又は減速させ、0.1μg/kg/分を超える場合は25〜50%の範囲で加速又は最大25%の範囲で減速させるが、投与速度の上限は0.5μg/kg/分とする。投与終了時は、10分以上の間隔で、最大25%ずつ減速させ、0.025μg/kg/分を目安として投与終了する。
7. 用法及び用量に関連する注意
<効能共通>
<成人:全身麻酔の導入及び維持における鎮痛、小児:全身麻酔の維持における鎮痛>
7.2 本剤を単独で全身麻酔に使用しないこと。本剤は鎮静効果が弱いため、意識消失を得るためには他の全身麻酔剤を併用すること。
7.3 本剤を単回静脈内投与する場合は、30秒以上かけて行うこと。[11.1.1参照]
<集中治療における人工呼吸中の鎮痛>
7.4 単回静脈内投与は行わないこと。
8. 重要な基本的注意
<効能共通>
8.1 本剤は作用消失が急速であり投与中止5〜10分後には作用が消失する。そのため、本剤の投与中止前、若しくは直後に鎮痛剤を投与するなど適切な疼痛管理を行うこと。
8.2 まれにショックあるいは中毒症状を起こすことがあるので、本剤の投与に際しては、十分な問診により患者の全身状態を把握するとともに、異常が認められた場合には直ちに救急処置のとれるよう、常時準備しておくこと。
8.3 本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転や危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
8.4 本剤は強オピオイドであり呼吸循環への影響が予測されるため、必ず気道確保、呼吸管理等の蘇生設備の完備された場所で、心電図による監視、血圧の測定等、心機能をモニターすること。
<成人:全身麻酔の導入及び維持における鎮痛、小児:全身麻酔の維持における鎮痛>
8.5 本剤投与にあたっては、原則としてあらかじめ絶食させておくこと。
8.6 本剤の使用に際しては、一般の全身麻酔剤と同様、麻酔開始より患者が完全に覚醒するまで、麻酔技術に熟練した医師が専任で患者の全身状態を十分に監視すること。
8.7 患者の全身状態を観察しながら、本剤及び併用する全身麻酔剤の投与量に注意し、麻酔の深度は手術、検査に必要な最低の深さにとどめること。
<集中治療における人工呼吸中の鎮痛>
8.8 本剤の使用に際しては、集中治療に習熟した医師が患者の全身状態を注意深く継続して監視すること。
8.9 本剤投与中は挿管又は気管切開による気道確保を行うこと。
8.10 移送を伴う場合には、患者管理に熟練した医師の付き添いのもと、循環動態、呼吸等について継続的な監視体制が整った状況で投与し、循環動態の変動及び呼吸等に特に注意すること。
8.11 本剤投与中は至適鎮痛レベルが得られるよう患者の全身状態を観察しながら投与速度を調節すること。鎮痛レベル及び鎮静レベルの両方が至適レベルを満たしていない場合は、先に至適鎮痛レベルを満たすように本剤の投与速度を調節した後、鎮静剤併用の必要性の判断を含め、至適鎮静レベルを満たすように鎮静剤の投与速度を調節すること。
8.12 本剤は鎮静作用を有するため、他の鎮静剤と併用する際には鎮静剤の過量投与に注意すること。
8.13 長期投与後の急激な投与中止により、頻脈、高血圧等の離脱症状があらわれることがあるため、投与を中止する場合には、用法及び用量を遵守し、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 ASAIII、IVの患者
開始投与速度を減速し、その後調節すること。血液循環が抑制されるおそれがある。
9.1.2 衰弱患者、循環血液量減少のある患者
心血管系に影響を及ぼすおそれがある。
9.1.3 重症の高血圧症、心弁膜症等の心血管系に著しい障害のある患者
血圧低下や病状の悪化が起こりやすい。[11.1.4参照]
9.1.4 不整脈のある患者
徐脈を起こすことがある。[11.1.5参照]
9.1.5 慢性肺疾患等の呼吸機能障害のある患者
呼吸抑制を増強するおそれがある。[11.1.3参照]
9.1.6 薬物依存の既往歴のある患者
依存性を生じやすい。
9.1.7 痙攣発作の既往歴のある患者
痙攣が起こることがある。[11.1.8参照]
9.1.8 気管支喘息の患者
気管支収縮が起こることがある。
9.5 妊婦
9.5.1 妊産婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
9.5.2 本剤は胎盤を通過するため、分娩時の投与により新生児に呼吸抑制があらわれることがある。
9.6 授乳婦
授乳しないことが望ましい。動物実験(ラット)で乳汁移行が認められている。
9.7 小児等
<小児:全身麻酔の維持における鎮痛>
9.7.1 低出生体重児、新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していない。
<集中治療における人工呼吸中の鎮痛>
9.7.2 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
本剤の開始用量を減量するなど、患者の全身状態を観察しながら慎重に投与して調節すること。心血管系に影響を及ぼすおそれがあり、血圧低下等の副作用があらわれやすい。本剤の薬理学的作用に対する感受性が増大するとの報告がある2)。
10. 相互作用
10.1 併用禁忌
| ナルメフェン塩酸塩 セリンクロ [2.2参照] | 鎮痛作用が減弱するおそれがある。ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者には投与しないこと。緊急の手術等によりやむを得ず併用する場合には患者ごとに本剤の用量を漸増し、呼吸抑制等の中枢神経抑制症状を注意深く観察すること。手術等において本剤を投与することが事前にわかる場合には、少なくとも1週間前にナルメフェン塩酸塩の投与を中断すること。 | μオピオイド受容体への競合的阻害による。 |
10.2 併用注意
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 筋硬直(頻度不明)
11.1.2 換気困難(頻度不明)
筋硬直、喉頭痙攣により換気困難な状況に陥る可能性がある。異常が認められた場合には、筋弛緩剤の使用等適切な処置を行うこと。なお、喉頭痙攣がラリンジアルマスク使用中に出現し、換気困難となった症例が報告されているため、注意すること。
11.1.3 呼吸停止(頻度不明)、呼吸抑制(1.1%注))
11.1.4 低血圧(3.3%注))、血圧低下(頻度不明)
11.1.5 徐脈(1.1%注))
11.1.6 不全収縮、心停止(いずれも頻度不明)
徐脈に引き続いて不全収縮、心停止があらわれることがある(本剤と他の全身麻酔剤が併用されている場合、重篤な徐脈、不全収縮、心停止がみられることがあるので、十分な患者管理のできる状態で使用すること)。
11.1.7 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
本剤と他の全身麻酔剤が併用されている患者においてアレルギー、アナフィラキシーがあらわれることがある。
11.1.8 全身痙攣(頻度不明)[9.1.7参照]
注)国内第III相試験(集中治療における人工呼吸中の鎮痛)の発現頻度
11.2 その他の副作用
| 0.1〜5%未満注) | 頻度不明 | |
| 精神障害 | 譫妄、落ち着きのなさ | 幻視、激越 |
| 神経系障害 | 傾眠 | 振戦、鎮静 |
| 心臓障害 | 結節性調律、期外収縮、房室解離、洞房ブロック、心室無収縮、房室ブロック | |
| 血管障害 | 潮紅、高血圧 | |
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 徐呼吸、過換気 | |
| 胃腸障害 | 便秘、悪心 | 嘔吐、腹痛、腹部膨満 |
| 肝胆道系障害 | 肝機能異常 | |
| 皮膚及び皮下組織障害 | 発疹 | 紅斑、皮膚炎 |
| 腎及び尿路障害 | 乏尿 | |
| 全身障害及び投与局所様態 | 悪寒、冷感 | |
| 臨床検査 | 一回換気量増加 | ビリルビン増加、AST増加、LDH増加、ALT増加、血圧上昇、体温低下 |
| 傷害、中毒及び処置合併症 | 鎮静合併症 | 術後血圧上昇、創合併症 |
13. 過量投与
13.1 症状
筋硬直、呼吸抑制、血圧低下、徐脈等があらわれることがある。
13.2 処置
14. 適用上の注意
14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 注射液の調製方法
(溶解法)
レミフェンタニル濃度が1mg/mLになるように、バイアル内に注射用水、生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液を注入し、よく振盪して完全に溶解する。
(希釈法)
レミフェンタニルとして100μg/mL(20〜250μg/mL)になるように、生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈する。また、希釈後は安定性が低下するので、24時間以内に使用すること。注射用水は、溶液が等張とならないため希釈液として用いないこと。[14.2参照]
| 最終濃度 | 薬剤(1バイアル) | 溶解に必要な液量 | 希釈に必要な液量 | 溶解後総液量 |
| 100μg/mL | 2mgバイアル | 2mL | 18mL | 20mL |
| 5mgバイアル | 5mL | 45mL | 50mL |
14.1.2 配合変化
チオペンタールと混合すると沈殿を生じるので、別々の投与経路で使用するか、又は同一投与経路を使用する場合は経路内を生理食塩液等の中性溶液を用いて洗浄するなど、混合しないこと。
14.2 薬剤投与前の注意
本剤は投与前にプロポフォール等他の薬剤と混合しないこと。また、規定した溶解液及び希釈液のみを用い、調製すること。本剤を溶解し高pH(pH>6)になった場合には、含量の低下、分解物の増加が認められている。[14.1.1参照]
14.3 薬剤投与時の注意
14.3.1 投与経路
本剤は静脈内にのみ投与すること。
14.3.2 静注用ラインは専用のラインを使用し、静脈穿刺部若しくはその近位に接続すること。なお、本剤を持続静脈内投与する際には、必ずシリンジポンプ等を用いて行うこと。
14.3.3 血液/血清/血漿と同じ静注用ラインへ本剤を投与しないこと。血液由来の非特異的エステラーゼにより本剤が加水分解されるおそれがある。
14.4 薬剤投与後の注意
14.4.1 本剤の投与終了後、本剤を投与したラインを洗浄する際には、本剤の残液が急速静注されるおそれがあるので、十分注意すること。本剤を投与する際に用いた静注用ラインで他の薬剤を投与しないこと。
14.4.2 同一患者に対する一回の使用で残液がでた場合には、麻薬に関する所定の手続きにしたがって廃棄すること。
15. その他の注意
15.1 臨床使用に基づく情報
低体温による心−肺バイパスの間に、本剤のクリアランスが約20%低下したとの報告がある5)。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
16.1.1 成人(全身麻酔時)
日本人患者36例にレミフェンタニルとして0.25、0.5、1.0及び2.0μg/kgを1分間かけて単回静脈内投与したとき、また、日本人患者37例にレミフェンタニルとして0.125、0.25、0.5及び1.0μg/kg/分を持続静脈内投与したとき、動脈血液中未変化体濃度はそれぞれ2相性の消失を示した。各相における半減期は、単回静脈内投与時において0.6〜1.3分(t1/2α)及び6.7〜11.5分(t1/2β)、また、持続静脈内投与時においては1.3〜2.3分(t1/2α)及び12.6〜16.5分(t1/2β)であり、用量並びに投与方法にかかわらずほぼ一定であった。また、両投与方法における最高血液中濃度(Cmax)及び血液中濃度−時間曲線下面積(AUC)は各用量範囲において用量に比例して増加することが示された6)7)8)。
日本人患者にレミフェンタニルとして0.125、0.25及び0.5μg/kg/分を持続静脈内投与したときの動脈血液中未変化体濃度推移(平均値+標準偏差)
| 投与量(μg/kg/分) | Cmax(ng/mL) | t1/2α(min) | t1/2β(min) | AUC(ng・min/mL) | CL(mL/min/kg) | Vss(mL/kg) |
| 0.125(n=11) | 3.08±0.94 | 1.30±0.77 | 12.62±8.37 | 690.5±335.7 | 44.8±15.5 | 303±133 |
| 0.25(n=12) | 5.53±2.02 | 1.89±1.00 | 16.48±12.65 | 1235.4±703.7 | 55.4±35.1 | 406±296 |
| 0.5(n=12) | 11.23±2.99 | 1.59±0.86 | 15.01±11.04 | 1975.8±699.8 | 48.3±16.2 | 316±165 |
| 1.0(n=1) | 22.03 | 2.30 | 13.81 | 4978 | 45.4 | 296 |
16.1.2 成人(集中治療下)
集中治療において人工呼吸管理下で鎮痛が必要な20歳以上の患者(24例)に、レミフェンタニルとして0.025μg/kg/分で持続静脈内投与開始後、至適鎮痛レベルが得られるように0.5μg/kg/分を上限に投与速度を調節したときの動脈血液中未変化体濃度(平均値±標準偏差)は、投与終了時で1.098±0.6059ng/mL、投与終了後60分には0.02875±0.07245ng/mL(24例中20例で定量下限値未満)となり、動脈血液中未変化体濃度は速やかに低下した。また、薬物動態パラメータは下表の通りであった30)。
| t1/2(min) | AUC0-inf(ng・min/mL) | Cmax(ng/mL) | CL(mL/min/kg) | Vss(mL/kg) |
| 16.97±19.81 | 1726±2937 | 1.803±1.594 | 41.65±19.70 | 9600±16870 |
16.1.3 小児
日本人小児患者(1〜15歳、36例)に持続静脈内投与(開始用量:レミフェンタニルとして0.25μg/kg/分)開始後、定常状態(投与開始15分後以降、投与速度を変更した場合は10分間以上一定速度を維持している時点)の1時点で採血したとき、0.24〜0.26μg/kg/分の用量(33例)における動脈血液中未変化体濃度[中央値(範囲)]は4.76(0.57-8.96)ng/mLであった。クリアランス(CL)は、用量間で明らかな差は認められず、51.18(27.71-436.75)mL/min/kg[中央値(範囲)]であった9)。
| 用量(μg/kg/分) [n=1〜6歳、7〜15歳] | 上段:中央値、下段:[範囲] | |||
| 1〜6歳 | 7〜15歳 | 合計 | ||
| 動脈血液中未変化体濃度(ng/mL) | <0.24注1) [n=1、0] | 5.01 − | − − | 5.01 − |
| 0.24〜0.26 [n=15、18] | 4.33 [0.57-6.38] | 5.41 [3.62-8.96] | 4.76 [0.57-8.96] | |
| 0.26<注2) [n=2、0] | 11.18 [6.65-15.70] | − − | 11.18 [6.65-15.70] | |
| CL(mL/min/kg) | 全用量 [n=18、18] | 57.51 [39.39-436.75] | 46.11 [27.71-69.45] | 51.18 [27.71-436.75] |
16.3 分布
レミフェンタニル(2〜50ng/mL)の血漿蛋白結合率は71〜72%であり、アルブミンへの結合率は14〜16%、α1-酸性糖蛋白への結合率は38〜47%であった10)(in vitro)。
16.4 代謝
16.5 排泄
日本人健康成人男性6例にレミフェンタニルとして1.0μg/kgを1分間かけて単回静脈内投与したとき、投与後24時間までに投与量の約1%が未変化体として、約80%が脱メチル体代謝物として尿中に排泄された14)。
16.6 特定の背景を有する患者
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
<成人:全身麻酔の導入及び維持における鎮痛>
17.1.1 国内第III相試験
国内第III相試験167例(静脈麻酔剤併用二重盲検試験:麻酔導入は本剤1.0μg/kgを静脈内投与後、1.0μg/kg/分(高用量群)又は0.5μg/kg/分(低用量群)を持続静脈内投与。麻酔維持は0.5μg/kg/分(高用量群)又は0.25μg/kg/分(低用量群)を持続静脈内投与)及び80例(吸入麻酔剤併用非盲検試験:麻酔導入は本剤1.0μg/kgを静脈内投与後、0.5μg/kg/分を持続静脈内投与〔強い刺激が予想される場合は1.0μg/kg/分も可〕。麻酔維持は0.25μg/kg/分を持続静脈内投与)の全身麻酔施行患者において、気管挿管及び皮膚切開の刺激による反応率を評価した。気管挿管時及び皮膚切開時の反応率はそれぞれ11.3%、12.1%であった。副作用発現率は、65.9%(110/167例)及び71.3%(57/80例)であり、10%以上に発現した副作用は、静脈麻酔剤併用試験で血圧低下、徐脈、嘔気及び戦慄、吸入麻酔剤併用試験で血圧低下、悪心、徐脈、嘔吐及び悪寒であった21)22)。
| 気管挿管時 | 皮膚切開時 | ||||||
| 静脈麻酔剤併用試験 | 吸入麻酔剤併用試験 | 合計 | 静脈麻酔剤併用試験 | 吸入麻酔剤併用試験 | 合計 | ||
| 対象例数 | 167 | 80 | 247 | 167 | 80 | 247 | |
| 併用麻酔剤 | プロポフォール | プロポフォール | − | プロポフォール | セボフルラン | − | |
| 反応 | 22(13.2) | 6(7.5) | 28(11.3) | 29(17.4) | 1(1.3) | 30(12.1) | |
| 血行動態反応 | |||||||
| 収縮期血圧の上昇注1) | 19(11.4) | 3(3.8) | 22(8.9) | 27(16.2) | 1(1.3) | 28(11.3) | |
| 心拍数の上昇注2) | 9(5.4) | 3(3.8) | 12(4.9) | 2(1.2) | 0(0) | 2(0.8) | |
| 身体反応注3) | 0(0) | 1(1.3) | 1(0.4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 自律神経反応注4) | 0(0) | 1(1.3) | 1(0.4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| ASA分類別反応 | |||||||
| I | 9/87(10.3) | 4/42(9.5) | 13/129(10.1) | 9/87(10.3) | 1/42(2.4) | 10/129(7.8) | |
| II | 12/78(15.4) | 2/33(6.1) | 14/111(12.6) | 19/78(24.4) | 0/33(0) | 19/111(17.1) | |
| III | 1/2(50.0) | 0/5(0) | 1/7(14.3) | 1/2(50.0) | 0/5(0) | 1/7(14.3) | |
17.1.2 国内第III相試験
ASAIIIに分類される15例の全身麻酔施行患者を対象に、非盲検下で本剤1.0μg/kgを静脈内投与後、0.5μg/kg/分の持続静脈内投与〔強い刺激が予想される場合は1.0μg/kg/分も可〕により麻酔導入し、0.25μg/kg/分の持続静脈内投与で麻酔を維持した。その結果、気管挿管時及び皮膚切開時の反応率はそれぞれ46.7%、20.0%であり、国内第III相試験結果(17.1.1項)と比較して高い反応率であった。また、術後には、全例で早期抜管が可能であった。副作用発現率は73.3%(11/15例)であり、血圧低下が11例にみられた23)。
<小児:全身麻酔の維持における鎮痛>
17.1.3 国内第III相試験
1〜15歳の全身麻酔下の日本人小児患者80例を対象に、非盲検下で本剤0.25μg/kg/分の持続静脈内投与(必要時に1.0μg/kgの単回静脈内投与)により、麻酔を維持した。その結果、皮膚切開の刺激による反応が発現した患者の割合は11.3%(9/80例,95%信頼区間:5.3〜20.3%)であった。報告された反応の内訳は、収縮期血圧上昇注1)10.0%(8/80例)及び心拍数増加注2)2.5%(2/80例)であり、身体反応注3)及び自律神経性反応注4)は報告されなかった。また、手術中のレミフェンタニルの鎮痛効果に対する総合評価は全例で有効と判定された。副作用発現率は30.0%(24/80例)であり、主な副作用は心拍数減少(26.3%)であった24)。
注1)収縮期血圧がベースライン値(皮膚切開開始1〜5分前)より20%上昇し、1分間以上持続する。
注2)心拍数がベースライン値(皮膚切開開始1〜5分前)より20%上昇し、1分間以上持続する。
注3)体動、嚥下、顔をしかめる、開眼を観察できる。
注4)発汗、流涙、散瞳を観察できる。
<集中治療における人工呼吸中の鎮痛>
17.1.4 国内第III相試験
集中治療において人工呼吸管理下で鎮痛が必要な20歳以上の患者182例を無作為に割り付け(本剤群92例、フェンタニル群90例)、二重盲検下で至適鎮痛レベルが得られるように本剤群では0.025μg/kg/分で持続静脈内投与開始後、0.5μg/kg/分を上限に投与速度を調節し、フェンタニル群では1〜2μg/kgを緩徐に静注して0.1μg/kg/時で持続静脈内投与を開始後、2μg/kg/時を上限に投与速度を調節した。その結果、レスキュー鎮痛薬を使用しなかった被験者の割合は、本剤群で100.0%(92/92例)、フェンタニル群では97.8%(88/90例)であり、その群間差の95%信頼区間の下限値(−0.8%)が事前に規定した非劣性マージン(−15%)を上回ったことから、本剤群のフェンタニル群に対する非劣性が示された。本剤群の副作用発現頻度は13.0%(12/92例)であり、主な副作用は、低血圧3.3%(3/92例)、徐呼吸2.2%(2/92例)であった31)。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
レミフェンタニルは、μ-オピオイド受容体の選択的なアゴニストとして作用し、鎮痛作用を示すものと考えられる25)。
18.2 鎮痛作用
18.3 鎮静作用
麻酔下イヌにおいて、レミフェンタニル0.5μg/kg/分の持続静脈内投与により、脳波のデルタ波形の上昇が認められたことから、鎮静作用を有することが示された28)。
18.4 オピオイド受容体親和性
In vitro受容体結合試験において、レミフェンタニルはオピオイド受容体、特にμ-オピオイド受容体に高い親和性を示した(μ-、δ-及びκ-オピオイド受容体に対するIC50値は、それぞれ2.6nmol/L、66nmol/L及び6.1μmol/L)29)。
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. レミフェンタニル塩酸塩
20. 取扱い上の注意
高温下での本剤の保存は避けること(25℃以下での保存が望ましい)。
21. 承認条件
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
22. 包装
<レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」>
5バイアル
<レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」>
5バイアル
23. 主要文献
- Abernethy DR,et al., Clin Pharmacokinet., 7 (2), 108-124, (1982) »PubMed »DOI
- Minto CF,et al., Anesthesiology, 86 (1), 10-23, (1997) »PubMed
- Lang E,et al., Anesthesiology, 85 (4), 721-728, (1996) »PubMed »DOI
- Reid JE,et al., Br J Anaesth., 84 (3), 422-423, (2000) »PubMed »DOI
- Russell D,et al., Br J Anaesth., 79 (4), 456-459, (1997) »PubMed
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(2)1)[1])
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(2)2)[1])
- 槇田浩史,他, 麻酔と蘇生, 41 (4), 105-115, (2005)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2016年8月26日承認 申請資料概要 2.7.2.2.1.1)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 2(2)3))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ホ 1(4))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 2(3)4))
- Davis,P.J.,et al., Anesth.Analg., 95 (5), 1305-1307, (2002) »PubMed
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(6)1))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(3)3))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(3)1))
- Hoke,J.F.,et al., Anesthesiology, 87 (3), 533-541, (1997) »PubMed
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(3)2))
- Dershwitz,M.,et al., Anesthesiology, 84 (4), 812-820, (1996) »PubMed
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ヘ 3(3)4))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ト 3)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ト 4)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ト 5)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2016年8月26日承認 申請資料概要 2.7.6.3)
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ホ 1(3)2)[2])
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ホ 1(1)1))
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ホ 1(4)1))
- Hoke,J.F.,et al., J Pharmacol Exp Ther., 281 (1), 226-32, (1997) »PubMed
- 申請資料概要(アルチバ静注用2mg/アルチバ静注用5mg 2006年10月20日承認 申請資料概要 ホ(3)1))
- 申請資料概要(2022年8月24日承認、2.7.2.2)
- 申請資料概要(2022年8月24日承認、2.7.6.1)
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
丸石製薬株式会社
学術情報部
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中2-4-2
電話:0120-014-561
第一三共株式会社
製品情報センター
〒103-8426
東京都中央区日本橋本町3-5-1
電話:0120-065-132(がん・医療用麻薬専用)
製品情報問い合わせ先
丸石製薬株式会社
学術情報部
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中2-4-2
電話:0120-014-561
第一三共株式会社
製品情報センター
〒103-8426
東京都中央区日本橋本町3-5-1
電話:0120-065-132(がん・医療用麻薬専用)
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
26.2 販売元
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1