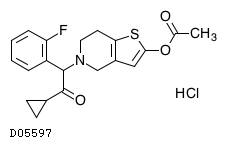医薬品情報
| 総称名 | エフィエント |
|---|---|
| 一般名 | プラスグレル塩酸塩 |
| 欧文一般名 | Prasugrel Hydrochloride |
| 製剤名 | プラスグレル塩酸塩製剤 |
| 薬効分類名 | 抗血小板剤 |
| 薬効分類番号 | 3399 |
| ATCコード | B01AC22 |
| KEGG DRUG |
D05597
プラスグレル塩酸塩
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2021年12月 改訂(効能変更、用法変更)(第3版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| エフィエント錠2.5mg | EFIENT TABLETS | 第一三共 | 3399009F3022 | 178円/錠 | 処方箋医薬品注) |
| エフィエント錠3.75mg | EFIENT TABLETS | 第一三共 | 3399009F1020 | 248.8円/錠 | 処方箋医薬品注) |
| エフィエント錠5mg | EFIENT TABLETS | 第一三共 | 3399009F2026 | 326円/錠 | 処方箋医薬品注) |
| エフィエントOD錠20mg | EFIENT OD TABLETS | 第一三共 | 3399009F5025 | 999円/錠 | 処方箋医薬品注) |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
2.1 出血している患者(血友病、頭蓋内出血、消化管出血、尿路出血、喀血、硝子体出血等)[出血を助長するおそれがある。]
2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
4. 効能または効果
エフィエント錠2.5mg
○経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患
○虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制(脳梗塞発症リスクが高い場合に限る)
エフィエント錠3.75mg
○経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患
○虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制(脳梗塞発症リスクが高い場合に限る)
エフィエント錠5mg
エフィエントOD錠20mg
5. 効能または効果に関連する注意
エフィエント錠2.5mg
<効能共通>
5.1 <参考>
| 効能又は効果 | 錠2.5mg | 錠3.75mg | 錠5mg | OD錠20mg |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制 | ○ | ○ | − | − |
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
5.2 PCIが適用予定の虚血性心疾患患者への投与は可能である。冠動脈造影により、保存的治療あるいは冠動脈バイパス術が選択され、PCIを適用しない場合には、以後の投与を控えること。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
エフィエント錠3.75mg
<効能共通>
5.1 <参考>
| 効能又は効果 | 錠2.5mg | 錠3.75mg | 錠5mg | OD錠20mg |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制 | ○ | ○ | − | − |
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
5.2 PCIが適用予定の虚血性心疾患患者への投与は可能である。冠動脈造影により、保存的治療あるいは冠動脈バイパス術が選択され、PCIを適用しない場合には、以後の投与を控えること。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
エフィエント錠5mg
<効能共通>
5.1 <参考>
| 効能又は効果 | 錠2.5mg | 錠3.75mg | 錠5mg | OD錠20mg |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制 | ○ | ○ | − | − |
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
5.2 PCIが適用予定の虚血性心疾患患者への投与は可能である。冠動脈造影により、保存的治療あるいは冠動脈バイパス術が選択され、PCIを適用しない場合には、以後の投与を控えること。
エフィエントOD錠20mg
<効能共通>
5.1 <参考>
| 効能又は効果 | 錠2.5mg | 錠3.75mg | 錠5mg | OD錠20mg |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制 | ○ | ○ | − | − |
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
5.2 PCIが適用予定の虚血性心疾患患者への投与は可能である。冠動脈造影により、保存的治療あるいは冠動脈バイパス術が選択され、PCIを適用しない場合には、以後の投与を控えること。
6. 用法及び用量
エフィエント錠2.5mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
通常、成人には、プラスグレルとして3.75mgを1日1回経口投与する。
エフィエント錠3.75mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
通常、成人には、プラスグレルとして3.75mgを1日1回経口投与する。
エフィエント錠5mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。
エフィエントOD錠20mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
通常、成人には、投与開始日にプラスグレルとして20mgを1日1回経口投与し、その後、維持用量として1日1回3.75mgを経口投与する。
7. 用法及び用量に関連する注意
エフィエント錠2.5mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
7.1 抗血小板薬二剤併用療法期間は、アスピリン(81〜100mg/日、なお初回負荷投与では324mgまで)と併用すること。抗血小板薬二剤併用療法期間終了後の投与方法については、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。
7.2 PCI施行前に本剤3.75mgを5日間程度投与されている場合、初回負荷投与(投与開始日に20mgを投与すること)は必須ではない。本剤による血小板凝集抑制作用は5日間で定常状態に達することが想定される。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
エフィエント錠3.75mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
7.1 抗血小板薬二剤併用療法期間は、アスピリン(81〜100mg/日、なお初回負荷投与では324mgまで)と併用すること。抗血小板薬二剤併用療法期間終了後の投与方法については、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。
7.2 PCI施行前に本剤3.75mgを5日間程度投与されている場合、初回負荷投与(投与開始日に20mgを投与すること)は必須ではない。本剤による血小板凝集抑制作用は5日間で定常状態に達することが想定される。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
エフィエント錠5mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
7.1 抗血小板薬二剤併用療法期間は、アスピリン(81〜100mg/日、なお初回負荷投与では324mgまで)と併用すること。抗血小板薬二剤併用療法期間終了後の投与方法については、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。
7.2 PCI施行前に本剤3.75mgを5日間程度投与されている場合、初回負荷投与(投与開始日に20mgを投与すること)は必須ではない。本剤による血小板凝集抑制作用は5日間で定常状態に達することが想定される。
エフィエントOD錠20mg
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
7.1 抗血小板薬二剤併用療法期間は、アスピリン(81〜100mg/日、なお初回負荷投与では324mgまで)と併用すること。抗血小板薬二剤併用療法期間終了後の投与方法については、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。
7.2 PCI施行前に本剤3.75mgを5日間程度投与されている場合、初回負荷投与(投与開始日に20mgを投与すること)は必須ではない。本剤による血小板凝集抑制作用は5日間で定常状態に達することが想定される。
8. 重要な基本的注意
<効能共通>
8.1 本剤による血小板凝集抑制が問題となるような手術の場合には、14日以上前に投与を中止することが望ましい。なお、十分な休薬期間を設けることができない場合は重大な出血のリスクが高まるので十分に観察すること。また、手術後に本剤の再投与が必要な場合には、手術部位の止血を確認してから再開すること。[11.1.1、17.1.1参照]
8.2 出血を起こす危険性が高いと考えられる場合には、中止等を考慮すること。[11.1.1参照]
8.3 出血を示唆する臨床症状が疑われた場合には、直ちに血球算定等の適切な検査を実施すること。[11.1.1参照]
8.4 患者には通常よりも出血しやすくなることを説明し、異常な出血が認められた場合には医師に連絡するよう指導すること。また、他院(他科)を受診する際には、本剤を服用している旨を医師に必ず伝えるよう患者に指導すること。[11.1.1参照]
8.5 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)等の重大な副作用が発現することがあるので、投与開始後2ヵ月間は、2週間に1回程度の血液検査等の実施を考慮すること。[11.1.2参照]
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
8.6 初回負荷投与時に出血のリスクが高まる可能性があることを十分考慮すること。[11.1.1参照]
8.7 冠動脈造影前に初回負荷投与を行う場合は、本剤の血小板凝集抑制作用による出血のリスクが高まるので、穿刺部位等からの出血に十分注意すること。非ST上昇心筋梗塞患者を対象とした海外臨床試験において、海外での初回負荷用量をPCI施行時に単回投与した場合に比較し、冠動脈造影前及びPCI施行時に分割投与した場合に、更なる有効性は認められずPCI施行に関連した重大な出血リスクが増大したとの報告がある2)。[11.1.1参照]
8.8 ステント留置患者への本剤投与時には該当医療機器の電子添文の「警告」「有害事象」の項を必ず参照すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
<効能共通>
9.1.1 出血傾向及びその素因のある患者(頭蓋内出血の既往のある患者)
出血を生じるおそれがある。
9.1.2 高血圧が持続する患者
本剤投与中は十分な血圧コントロールを行うこと。出血のリスクが高まる。
9.1.3 他のチエノピリジン系薬剤(クロピドグレル等)に対し過敏症の既往歴のある患者
本剤投与後に血管浮腫を含む過敏症を発現するおそれがある。
9.1.4 低体重の患者(体重50kg以下)
<経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患>
9.1.5 脳梗塞又は一過性脳虚血発作(TIA)の既往歴のある患者
海外臨床試験で、臨床用量を超える高用量において出血の危険性が増大したとの報告がある。[17.1.2参照]
9.2 腎機能障害患者
9.2.1 高度の腎機能障害のある患者
出血の危険性が増大するおそれがある。
9.3 肝機能障害患者
9.3.1 高度の肝機能障害のある患者
凝固因子の産生が低下していることがあるので、出血の危険性が増大するおそれがある。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
動物実験(ラット)で胎児への移行が認められている。
動物実験(ラット)で胎児への移行が認められている。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有用性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。
動物実験(ラット)で乳汁中に移行することが認められている。
動物実験(ラット)で乳汁中に移行することが認められている。
9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者
生理機能が低下しているので、出血の危険性が増大するおそれがある。
10. 相互作用
10.2 併用注意
| 抗凝固剤 ワルファリン、 ヘパリン、 エドキサバン等 血小板凝集抑制作用を有する薬剤 アスピリン等 血栓溶解剤 ウロキナーゼ、 アルテプラーゼ等 | これらの薬剤との併用により、出血の危険性を増大させるおそれがある。 | 相互に抗血栓作用を増強することが考えられる。 |
| 非ステロイド性消炎鎮痛剤 ロキソプロフェン、 ナプロキセン等 | これらの薬剤との併用により、出血の危険性を増大させるおそれがある。 | 相互に抗血栓作用を増強することが考えられる。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 出血(1.0%)
11.1.2 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)(頻度不明)
TTPの初期症状(倦怠感、食欲不振、紫斑等の出血症状、意識障害等の精神・神経症状、血小板減少、破砕赤血球の出現を認める溶血性貧血、発熱、腎機能障害等)が認められた場合には、直ちに投与を中止し、血液検査(網赤血球、破砕赤血球の同定を含む)を実施し、必要に応じ血漿交換等の処置を行うこと。[8.5参照]
11.1.3 過敏症(頻度不明)
血管浮腫を含む過敏症があらわれることがある。
11.1.4 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
11.1.5 無顆粒球症、再生不良性貧血を含む汎血球減少症(頻度不明)
11.2 その他の副作用
| 1%以上 | 0.1〜1%未満 | |
| 血液 | 貧血、血小板数減少、好酸球数増加、白血球数減少 | |
| 出血傾向 | 皮下出血(8.3%)、鼻出血、血尿、血管穿刺部位血腫、皮下血腫、穿刺部位出血、歯肉出血、結膜出血、創傷出血 | 便潜血、痔出血、処置による出血、血腫、喀血、胃腸出血、網膜出血、出血、上部消化管出血、口腔内出血、カテーテル留置部位出血、紫斑、硝子体出血、出血性腸憩室、下部消化管出血、点状出血、血管偽動脈瘤、不正子宮出血 |
| 肝臓 | 肝機能障害 | γ-GTP上昇、ALP上昇、ALT上昇、AST上昇 |
| 腎臓 | 腎機能障害、尿蛋白増加 | |
| 精神神経系 | 浮動性めまい、味覚障害、しびれ、回転性めまい | |
| 消化器 | 下痢、便秘、悪心・嘔吐、胃食道逆流性疾患、腹痛、腹部不快感、胃炎、胃・十二指腸潰瘍 | |
| 過敏症 | 発疹、紅斑、蕁麻疹 | |
| 循環器 | 期外収縮、血圧上昇、狭心症 | |
| その他 | 尿酸上昇、末梢性浮腫、背部痛、血管穿刺部位腫脹、血中甲状腺刺激ホルモン増加、尿糖上昇、倦怠感 |
13. 過量投与
13.1 症状
本剤の過量投与により出血が生じるおそれがある。
13.2 処置
特異的な解毒剤は知られていないので、緊急措置が必要な場合は血小板輸血を考慮すること。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤交付時の注意
<製剤共通>
14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。
<OD錠>
14.1.2 OD錠は舌の上にのせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。
14.1.3 OD錠は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。
15. その他の注意
15.2 非臨床試験に基づく情報
マウスに2年間経口投与した試験で、雄マウスの300mg/kg/日以上、雌マウスの100mg/kg/日以上の投与群で、肝腫瘍の発現増加が認められたとの報告がある。一方、ラットに2年間経口投与した試験では腫瘍の発生は認められていないとの報告がある。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
16.1.1 プラスグレル錠
プラスグレルは経口投与後に速やかに代謝されるため、血漿中に本剤の未変化体は検出されず、活性代謝物R-138727の血漿中濃度を測定した。
健康成人に、投与1日目にプラスグレル20mg及び投与2〜7日目にプラスグレル3.75mgを1日1回経口投与したときの活性代謝物R-138727の血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータは次のとおりであった3)。
健康成人に、投与1日目にプラスグレル20mg及び投与2〜7日目にプラスグレル3.75mgを1日1回経口投与したときの活性代謝物R-138727の血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータは次のとおりであった3)。
20mg投与時(投与1日目)の活性代謝物R-138727の血漿中濃度推移
3.75mg投与時(投与7日目)の活性代謝物R-138727の血漿中濃度推移
| 投与量 | n | Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | AUClast(ng・hr/mL) | t1/2(hr) |
| 20mg(投与1日目) | 23 | 177.1±96.3 | 0.6±0.2 | 185.1±66.5 | 4.9±5.8 |
| 3.75mg(投与7日目) | 23 | 29.2±15.5 | 0.6±0.4 | 26.3±9.2 | 0.9±0.4 |
16.1.2 プラスグレルOD錠
健康成人男性にプラスグレルOD錠20mg1錠(水なし又は水で服用)又はプラスグレル錠20mg1錠(水で服用)を、クロスオーバー法で空腹時単回経口投与して活性代謝物R-138727の薬物動態パラメータを比較した。水なしで服用したとき、Cmax及びAUC0-12hの幾何最小二乗平均値の比の両側90%信頼区間は0.80〜1.25の範囲内であった。水で服用したとき、Cmax及びAUC0-12hの幾何最小二乗平均値の比は0.90〜1.11の範囲内で、かつ溶出試験で両製剤の溶出挙動は類似していた。したがって、プラスグレル錠20mgとプラスグレルOD錠20mgは生物学的に同等であることが確認された4)。
| 投与量 | n | Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | AUC0-12h(ng・hr/mL) | t1/2(hr) |
| OD錠20mg(水なしで服用) | 24 | 244±84.8 | 0.733±0.354 | 275±50.3 | 4.11±0.830 |
| 錠20mg(水で服用) | 24 | 258±113 | 0.729±0.194 | 280±63.7 | 4.02±1.09 |
| 投与量 | n | Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | AUC0-12h(ng・hr/mL) | t1/2(hr) |
| OD錠20mg(水で服用) | 24 | 218±91.2 | 0.583±0.374 | 230±57.7 | 3.95±1.13 |
| 錠20mg(水で服用) | 24 | 223±82.0 | 0.816±0.309 | 234±46.4 | 3.96±0.921 |
16.2 吸収
16.2.1 食事の影響
16.3 分布
ラットに14C-プラスグレルを単回経口投与した場合、組織中放射能濃度は多くの組織で投与1時間後に最高値を示し、胃、小腸、肝臓、腎臓及び膀胱では血液中よりも高い放射能濃度を認めた。これらに加え、投与72時間後では甲状腺及び大動脈でも血液中よりも高い放射能濃度を認めた。その他の組織では、血液中と同程度かそれ以下であった。また、反復投与した場合、投与14日目には組織への分布がほぼ定常状態に達した。
16.4 代謝
経口投与されたプラスグレル塩酸塩は、小腸細胞でヒトカルボキシルエステラーゼにより速やかにR-95913に代謝され、さらに小腸及び肝臓の薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)により代謝され、活性代謝物であるR-138727が生成する。in vitro試験からR-138727への代謝には、CYP3A及びCYP2B6が主たる酵素として関与することが示唆されている。
16.5 排泄
健康成人男性に14C-プラスグレル15mgを単回経口投与した場合、投与240時間以内に放射能の累積排泄率は95%以上に達し、放射能の約68%が尿中から、約27%が糞中から排泄された(外国人データ)。
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 腎機能障害患者
中等度腎機能障害患者(クレアチニンクリアランス30〜50mL/min)にプラスグレル60mg注)を単回経口投与したときの活性代謝物R-138727の薬物動態は、健康成人と比較して差は認められなかった。透析を必要とする末期腎機能障害患者では、健康成人と比較して活性代謝物R-138727のAUCが約31〜47%及びCmaxが約20〜52%低下した5)(外国人データ)。
16.6.2 肝機能障害患者
中等度肝機能障害患者(Child-Pugh分類B)に、投与1日目にプラスグレル60mg及び投与2〜6日目にプラスグレル10mgを1日1回経口投与したとき注)の活性代謝物R-138727の薬物動態は、健康成人と比較して差は認められなかった6)(外国人データ)。
16.6.3 高齢者
高齢者(75歳以上)に、投与1日目にプラスグレル20mg及び投与2〜7日目にプラスグレル3.75mgを1日1回経口投与したときの活性代謝物R-138727の薬物動態は、非高齢者と比較して差は認められなかった3)。
16.7 薬物相互作用
16.7.1 ケトコナゾール
プラスグレル塩酸塩とCYP3A阻害剤であるケトコナゾールを併用投与した場合の活性代謝物R-138727の薬物動態は、プラスグレル塩酸塩単独投与と比較してCmaxが初回負荷用量(60mg)投与時で約46%及び維持用量(15mg)投与時注)で約34%低下したが、AUC0-24hへの影響は認められなかった。また、血小板凝集抑制率(20μM ADP惹起)は初回負荷用量及び維持用量投与時のいずれもケトコナゾールの併用による影響を受けなかった7)(外国人データ)。
16.7.2 リファンピシン
CYP3A、CYP2B6の誘導剤であるリファンピシンの前投与(600mg/日)は、プラスグレル塩酸塩初回負荷用量(60mg)投与時及び維持用量(10mg)投与時注)のR-138727の曝露に影響を及ぼさなかった8)(外国人データ)。
16.7.3 ランソプラゾール、ラニチジン
注)本剤の承認用量は、経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患では初回負荷用量20mg、維持用量3.75mg/日、虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制では3.75mg/日である。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
<急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)>
17.1.1 国内第III相試験
PCIが適用される予定の急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)患者1,385例を対象とした国内第III相二重盲検比較試験における投与24週後までの主要心血管イベントの発現率は次のとおりであった11)。
| プラスグレル群b) | クロピドグレル群c) | ハザード比(95%信頼区間) | |
| 発現率(例数) | 9.3%(64/685) | 11.8%(80/678) | 0.773(0.557,1.074) |
副作用発現頻度は、プラスグレル群で47.7%(327/685例)、クロピドグレル群で39.5%(268/678例)であった。主な副作用は皮下出血で、プラスグレル群9.1%(62/685例)、クロピドグレル群7.7%(52/678例)であった。
冠動脈バイパス術(CABG)に関連しない、大出血及び小出血の発現率は、プラスグレル群で5.7%(39/685例)、クロピドグレル群で4.3%(29/678例)であった。このうち、PCIの合併症の発現率は、プラスグレル群で2.8%(19/685例)、クロピドグレル群で1.8%(12/678例)であった。
CABGに関連しない、大出血、小出血及び臨床的に重要な出血の発現率は、プラスグレル群で9.6%(66/685例)、クロピドグレル群で9.6%(65/678例)であった。なお、投与終了後14日以内にCABGが施行された患者での、大出血、小出血及び臨床的に重要な出血は、プラスグレル群で10例中9例に、クロピドグレル群で9例中7例に発現した。[8.1参照]
17.1.2 海外第III相試験
PCIが適用される予定の急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)患者13,619例を対象とした海外第III相二重盲検試験における主要心血管イベントの発現率は次のとおりであった12)。
| 発現率(例数) | ハザード比(95%信頼区間) | p値d) | |
| プラスグレル群b) | |||
| クロピドグレル群c) | |||
| 急性冠症候群全体 | 9.44%(643/6,813) | 0.812(0.732,0.902) | p<0.001 |
| 11.49%(781/6,795) | |||
| 不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞 | 9.30%(469/5,044) | 0.820(0.726,0.927) | p=0.002 |
| 11.23%(565/5,030) | |||
| ST上昇心筋梗塞 | 9.84%(174/1,769) | 0.793(0.649,0.968) | p=0.019 |
| 12.24%(216/1,765) |
有害事象発現頻度は、プラスグレル群で80.3%(5,416/6,741例)、クロピドグレル群で80.0%(5,374/6,716例)であった。主な出血性有害事象は挫傷で、プラスグレル群6.9%(468/6,741例)、クロピドグレル群3.9%(262/6,716例)であった。
CABGに関連しない、大出血及び小出血の発現率は、プラスグレル群で4.5%(303/6,741例)、クロピドグレル群で3.4%(231/6,716例)であった。なお、CABGが施行された患者での大出血の発現率は、プラスグレル群で11.3%(24/213例)、クロピドグレル群で3.6%(8/224例)であった。[9.1.5参照]
注)本剤の承認用量は、経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される虚血性心疾患では初回負荷用量20mg、維持用量3.75mg/日、虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制では3.75mg/日である。
<安定狭心症、陳旧性心筋梗塞>
17.1.3 国内第III相試験
安定狭心症、陳旧性心筋梗塞患者774例を対象とした国内第III相二重盲検試験における投与24週後までの主要心血管イベントの発現率は次のとおりであった13)。
| プラスグレル群b) | クロピドグレル群c)、d) | |
| 発現率(例数) | 4.1%(15/370) | 6.7%(25/372) |
副作用発現頻度は、プラスグレル群で43.2%(160/370例)、クロピドグレル群で39.8%(148/372例)であった。主な副作用は皮下出血で、プラスグレル群12.7%(47/370例)、クロピドグレル群9.1%(34/372例)であった。
CABGに関連しない、大出血、小出血及び臨床的に重要な出血の発現率は、プラスグレル群で5.4%(20/370例)、クロピドグレル群で6.2%(23/372例)であった。なお、投与終了後14日以内にCABGが施行された患者での、大出血、小出血及び臨床的に重要な出血は、プラスグレル群で3例中3例に、クロピドグレル群で1例中1例に発現した。
17.1.4 国内第II相試験
安定狭心症、陳旧性心筋梗塞患者422例を対象とした国内第II相二重盲検試験において、高齢(75歳以上)又は低体重(50kg以下)の患者での投与12週後までの主要心血管イベント(全死亡、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中、再入院を要する心筋虚血及び血行再建術の複合エンドポイント)の発現率は、プラスグレル2.5mg群a)で5.4%(2/37例)、プラスグレル3.75mg群b)で10.8%(4/37例)、クロピドグレル群c)、d)で11.1%(4/36例)であった。[7.4、9.1.4参照]
副作用発現頻度は、プラスグレル2.5mg群で32.4%(12/37例)、プラスグレル3.75mg群で48.6%(18/37例)、クロピドグレル群で44.4%(16/36例)であった。主な副作用は皮下出血で、プラスグレル2.5mg群0%(0/37例)、プラスグレル3.75mg群16.2%(6/37例)、クロピドグレル群11.1%(4/36例)であった。
CABGに関連しない、大出血及び小出血の発現率は、プラスグレル2.5mg群で0%(0/37例)、プラスグレル3.75mg群で2.7%(1/37例)、クロピドグレル群で2.8%(1/36例)であった。
a)アスピリン81〜100mg/日を併用し、プラスグレルを初回負荷用量20mg、維持用量2.5mg/日
b)アスピリン81〜100mg/日を併用し、プラスグレルを初回負荷用量20mg、維持用量3.75mg/日
c)アスピリン81〜100mg/日を併用し、クロピドグレルを初回負荷用量300mg、維持用量75mg/日
d)参考として設定した群であり、統計学的な比較対照群ではない。
<虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制>
17.1.5 国内第III相試験(虚血性脳血管障害患者)
虚血性脳血管障害患者3,747例を対象とした、国内第III相二重盲検試験における投与104週後までの脳心血管系イベントの発現率は、プラスグレル群で3.9%(73/1,885例)、クロピドグレル群で3.7%(69/1,862例)であった。クロピドグレル群に対するプラスグレル群のリスク比(95%信頼区間)は、1.045(0.757〜1.443)であり、95%信頼区間の上限値が事前に設定した非劣性限界値1.35を上回ったことから、クロピドグレル群に対するプラスグレル群の非劣性は検証されなかった。病型別の脳心血管系イベントの発現率は、次のとおりであった。
| 発現率(例数) | リスク比(95%信頼区間) | ||
| プラスグレル群c) | クロピドグレル群d) | ||
| 虚血性脳血管障害a)全体 | 3.9%(73/1,885) | 3.7%(69/1,862) | 1.045(0.757,1.443) |
| 大血管アテローム硬化 | 3.8%(21/553) | 4.8%(26/546) | 0.797(0.454,1.400) |
| 小血管の閉塞 | 3.3%(19/583) | 3.9%(23/593) | 0.840(0.463,1.526) |
| その他の原因によるもの | 0.0%(0/35) | 0.0%(0/49) | −(−,−) |
| 原因不明 | 4.6%(33/714) | 3.0%(20/674) | 1.558(0.903,2.687) |
副作用発現頻度は、プラスグレル群で32.7%(617/1,885例)、クロピドグレル群で31.4%(584/1,862例)であった。プラスグレル群での主な副作用は皮下出血7.4%(140/1,885例)及び鼻出血4.7%(89/1,885例)であった。
17.1.6 国内第III相試験(脳梗塞再発リスク因子を有する血栓性脳梗塞患者)
脳梗塞再発のリスク因子a)を有する血栓性脳梗塞患者b)234例を対象とした国内第III相二重盲検試験c)における投与48週後までの脳心血管系イベントd)の発現率は、プラスグレル群e)で6.8%(8/118例)、クロピドグレル群f)で7.1%(8/112例)であった。クロピドグレル群に対するプラスグレル群のリスク比(95%信頼区間)は、0.949(0.369〜2.443)であった。
副作用発現頻度は、プラスグレル群で11.7%(14/120例)、クロピドグレル群で14.9%(17/114例)であった。プラスグレル群での主な副作用は鼻出血3.3%(4/120例)及び皮下出血2.5%(3/120例)であった。
生命を脅かす出血、大出血及び臨床的に重要な出血の発現率は、プラスグレル群5.0%(6/120例)、クロピドグレル群3.5%(4/114例)であった16)。
a)高血圧症、脂質異常症、糖尿病あるいは慢性腎臓病の合併又は最終発作前の脳梗塞既往あり
b)TOAST分類における大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞のいずれかに該当
c)本試験の主たる目的はクロピドグレル群に対するプラスグレル群のリスク比の点推定値が1を下回ることの確認。目標症例数は、国内第III相試験(虚血性脳血管障害患者)の結果等から投与開始後48週間以内のクロピドグレル群での脳心血管系イベント発現率を4%と見積もり、クロピドグレル群に対するプラスグレル群の真のリスク比を0.4〜0.8と想定したとき、110例/群での当該リスク比の点推定値が1未満となる確率は81.2〜55.9%となることから250例(125例/群)と設定。
d)脳梗塞、心筋梗塞及びその他の血管死の複合エンドポイント
e)プラスグレルを3.75mg/日
f)クロピドグレルを75mg/日
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
18.2 抗血小板作用
各種実験動物(ラット、イヌ、サル)に経口投与したプラスグレルは、ADPにより惹起される血小板凝集を抑制した。
18.3 抗血栓作用
18.4 病態モデルにおける作用
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. プラスグレル塩酸塩
20. 取扱い上の注意
<OD錠>
錠剤表面に使用色素による赤色又は黄色の斑点がみられることがある。また、アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。
21. 承認条件
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
22. 包装
<エフィエント錠2.5mg>
(PTP:乾燥剤入り)
100錠(10錠×10)
<エフィエント錠3.75mg>
(瓶:バラ:乾燥剤入り)
100錠
(PTP:乾燥剤入り)
100錠(10錠×10) 140錠(14錠×10) 500錠(10錠×50) 700錠(14錠×50)
<エフィエント錠5mg>
(PTP:乾燥剤入り)
16錠(8錠×2) 80錠(8錠×10) 100錠(10錠×10)
<エフィエントOD錠20mg>
(PTP:乾燥剤入り)
5錠(5錠×1) 20錠(5錠×4)
23. 主要文献
- Kitagawa K,et al., Cerebrovasc Dis, 49 (2), 152-159, (2020) »PubMed
- Montalescot G,et al., N Engl J Med., 369 (11), 999-1010, (2013) »PubMed
- Hasunuma T,et al., Clin Drug Investig., 37 (7), 679-685, (2017) »PubMed
- 社内資料:日本人健康成人男性を対象としたプラスグレルOD錠とプラスグレル錠の生物学的同等性試験
- Small DS,et al., J Clin Pharm Ther., 34 (5), 585-594, (2009) »PubMed
- Small DS,et al., J Clin Pharm Ther., 34 (5), 575-583, (2009) »PubMed
- Farid NA,et al., Clin Pharmacol Ther., 81 (5), 735-741, (2007) »PubMed
- Farid NA,et al., Curr Med Res Opin., 25 (8), 1821-1829, (2009) »PubMed
- Small DS,et al., J Clin Pharmacol., 48 (4), 475-484, (2008) »PubMed
- Small DS,et al., Curr Med Res Opin., 24 (8), 2251-2257, (2008) »PubMed
- Saito S,et al., Circ J., 78 (7), 1684-1692, (2014) »PubMed
- Wiviott SD,et al., N Engl J Med., 357 (20), 2001-2015, (2007) »PubMed
- Isshiki T,et al., Circ J., 78 (12), 2926-2934, (2014) »PubMed
- Ogawa A,et al., Lancet Neurol., 18 (3), 238-247, (2019) »PubMed
- 社内資料:虚血性脳血管障害患者を対象とした国内第III相二重盲検試験
- 社内資料:脳梗塞再発リスク因子を有する血栓性脳梗塞患者を対象とした国内第III相二重盲検試験(2021年12月24日承認、CTD2.7.6.3)
- Niitsu Y,et al., Semin Thromb Hemost., 31 (2), 184-194, (2005) »PubMed
- Hasegawa M,et al., Thromb Haemost., 94 (3), 593-598, (2005) »PubMed
- Sugidachi A,et al., J Thromb Haemost., 5 (7), 1545-1551, (2007) »PubMed
- Sugidachi A,et al., J Cardiovasc Pharmacol., 58 (3), 329-334, (2011) »PubMed
- Niitsu Y,et al., Eur J Pharmacol., 579 (1-3), 276-282, (2008) »PubMed
- Ogawa T,et al., Eur J Pharmacol., 612 (1-3), 29-34, (2009) »PubMed
- Tomizawa A,et al., Thromb Res., 136 (6), 1224-1230, (2015) »PubMed
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
第一三共株式会社
製品情報センター
〒103-8426
東京都中央区日本橋本町3-5-1
電話:0120-189-132
製品情報問い合わせ先
第一三共株式会社
製品情報センター
〒103-8426
東京都中央区日本橋本町3-5-1
電話:0120-189-132
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1
26.2 技術提携
UBE株式会社