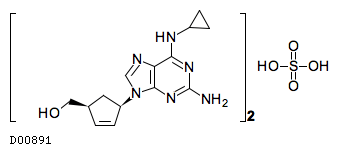医薬品情報
| 総称名 | ザイアジェン |
|---|---|
| 一般名 | アバカビル硫酸塩 |
| 欧文一般名 | Abacavir Sulfate |
| 製剤名 | アバカビル硫酸塩錠 |
| 薬効分類名 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 薬効分類番号 | 6250 |
| ATCコード | J05AF06 |
| KEGG DRUG |
D00891
アバカビル硫酸塩
|
| KEGG DGROUP |
DG03107
抗HIV薬
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年8月 改訂(第6版)
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザイアジェン錠300mg | Ziagen Tablets 300mg | ヴィーブヘルスケア | 6250014F1036 | 610円/錠 | 劇薬, 処方箋医薬品注) |
1. 警告
1.1 過敏症
1.1.1 海外の臨床試験において、本剤投与患者の約5%に過敏症の発現を認めており、まれに致死的となることが示されている。本剤による過敏症は、通常、本剤による治療開始6週以内(中央値11日)に発現するが、その後も継続して観察を十分に行うこと。[1.1.2-1.1.5、2.1、8.2、8.5、11.1.1、15.1.1参照]
1.1.2 本剤による過敏症では以下の症状が多臓器及び全身に発現する。
・皮疹
・発熱
・胃腸症状(嘔気、嘔吐、下痢、腹痛等)
・疲労感、倦怠感
・呼吸器症状(呼吸困難、咽頭痛、咳等)等
1.1.3 過敏症が発現した場合には、決してアバカビル含有製剤を再投与しないこと。本製剤の再投与により数時間以内にさらに重篤な症状が発現し、重篤な血圧低下が発現する可能性及び死に至る可能性がある。[1.1.1、1.1.2、1.1.4、1.1.5、2.1、8.2、8.5、11.1.1、15.1.1参照]
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
5. 効能または効果に関連する注意
5.1 無症候性ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症に関する治療開始については、CD4リンパ球数及び血漿中HIV RNA量が指標とされている。よって、本剤の使用にあたっては、患者のCD4リンパ球数及び血漿中HIV RNA量を確認するとともに、最新のガイドライン1)2)3)を確認すること。
5.2 本剤のHIV-2感染症患者に対する有効性・安全性は確認されていない。
6. 用法及び用量
通常、成人には他の抗HIV薬と併用して、アバカビルとして1日量600mgを1日1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜減量する。
7. 用法及び用量に関連する注意
7.1 HIVは感染初期から多種多様な変異株を生じ、薬剤耐性を発現しやすいことが知られているので、本剤は他の抗HIV薬と併用すること。[18.3参照]
7.2 本剤と他の抗HIV薬との併用療法において、因果関係が特定されない重篤な副作用が発現し、治療の継続が困難であると判断された場合には、本剤若しくは併用している他の抗HIV薬の一部を減量又は休薬するのではなく、原則として本剤及び併用している他の抗HIV薬の投与をすべて一旦中止すること。
8. 重要な基本的注意
8.1 本剤はHIV感染症治療の経験を有する医師が投与を行うこと。
8.2 本剤の再投与を考慮する際は、次のことに注意すること。[1.1.1-1.1.5、2.1、8.5、11.1.1、15.1.1参照]
・アバカビルによる過敏症に関連する症状は、再投与により初回より重篤な再発が認められる。重篤な血圧低下をきたし死に至る可能性があるので、本剤による過敏症が疑われた患者には、決して再投与しないこと。
・アバカビル含有製剤を中止した理由を再度検討し、アバカビルと過敏症との関連性が否定できない場合は再投与しないこと。
・投与中止前に過敏症の主な症状(皮疹、発熱、胃腸症状等)の1つのみが発現していた患者には、本剤の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ、必要に応じて入院のもとで投与を行うこと。
・過敏症の症状又は徴候が認められていなかった患者に対しても、直ちに医療施設に連絡できることを確認した上で投与を行うこと。
8.3 膵炎があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行うこと。
8.4 本剤を含む抗HIV薬の多剤併用療法を行った患者で、免疫再構築症候群が報告されている。投与開始後、免疫機能が回復し、症候性のみならず無症候性日和見感染(マイコバクテリウムアビウムコンプレックス、サイトメガロウイルス、ニューモシスチス等によるもの)等に対する炎症反応が発現することがある。また、免疫機能の回復に伴い自己免疫疾患(甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等)が発現するとの報告があるので、これらの症状を評価し、必要時には適切な治療を考慮すること。
8.5 本剤の使用に際しては、国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、患者又は患者に代わる適切な者に、次の事項についてよく説明し同意を得た後、使用すること。
・本剤はHIV感染症の根治療法薬ではないことから、日和見感染症を含むHIV感染症の進展に伴う疾病を発症し続ける可能性があるので、本剤投与開始後の身体状況の変化については、すべて担当医に報告すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重度の肝障害患者
9.3.2 中等度の肝障害患者
投与しないことが望ましいが、特に必要とする場合には慎重に投与すること。薬物動態は検討されていない。[16.6.2参照]
9.3.3 軽度の肝障害患者
薬物動態試験の結果、薬物動態に影響がみられたが、これら患者における推奨投与量は明らかとなっていない。[16.6.2参照]
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
動物において、本剤又はその代謝物は胎盤を通過することが示されている。動物(ラットのみ)において、本剤の500mg/kg/日又はそれ以上の投与量(ヒト全身曝露量(AUC)の32〜35倍)で、胚又は胎児に対する毒性(胎児の浮腫、変異及び奇形、吸収胚、体重減少、死産の増加)が認められたとの報告がある。
ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤(NRTI)を子宮内曝露又は周産期曝露された新生児及び乳児において、ミトコンドリア障害によると考えられる軽微で一過性の血清乳酸値の上昇が報告されている。また、非常にまれに発育遅延、てんかん様発作、他の神経疾患も報告されている。しかしながら、これら事象とNRTIの子宮内曝露、周産期曝露との関連性は確立していない。
動物において、本剤又はその代謝物は胎盤を通過することが示されている。動物(ラットのみ)において、本剤の500mg/kg/日又はそれ以上の投与量(ヒト全身曝露量(AUC)の32〜35倍)で、胚又は胎児に対する毒性(胎児の浮腫、変異及び奇形、吸収胚、体重減少、死産の増加)が認められたとの報告がある。
ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤(NRTI)を子宮内曝露又は周産期曝露された新生児及び乳児において、ミトコンドリア障害によると考えられる軽微で一過性の血清乳酸値の上昇が報告されている。また、非常にまれに発育遅延、てんかん様発作、他の神経疾患も報告されている。しかしながら、これら事象とNRTIの子宮内曝露、周産期曝露との関連性は確立していない。
9.6 授乳婦
授乳を避けさせること。一般に、HIVの乳児への移行を避けるため、あらゆる状況下においてHIVに感染した女性は授乳すべきでない。アバカビルの母体血漿中濃度に対する乳汁中濃度の比は0.9であることが報告されている4)(外国人データ)。
9.7 小児等
生後3ヵ月未満の乳児を対象とした臨床試験は実施していない。なお、小児等に対し本剤を投与した場合、本剤1日1回投与では、1日2回投与と比較して、曝露量が大きくなる可能性がある。[16.6.3参照]
9.8 高齢者
患者の肝、腎、及び心機能の低下、合併症、併用薬等を十分考慮し慎重に投与すること。
10. 相互作用
10.2 併用注意
| アルコール(飲酒) [16.4、16.7.1、16.7.2参照] | 本剤の代謝はエタノールによる影響を受ける。本剤のAUCが約41%増加したが、エタノールの代謝は影響を受けなかったとの報告がある14)。 | アルコールデヒドロゲナーゼの代謝基質として競合すると考えられている。 |
| メサドン塩酸塩 | メサドンのクリアランスが22%増加したことから、併用する際にはメサドン塩酸塩の増量が必要となる場合があると考えられる。なお、アバカビルの血中動態は臨床的意義のある影響を受けなかった(Cmaxが35%減少し、tmaxが1時間延長したが、AUCは変化しなかった)。 | 機序不明 |
| リオシグアト [16.7.2参照] | 本剤とリオシグアトの併用により、リオシグアトのAUCが増加するおそれがある。本剤との併用が必要な場合は、患者の状態に注意し、必要に応じてリオシグアトの減量を考慮すること。 | 本剤のCYP1A1阻害作用によりリオシグアトの代謝が阻害される。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 過敏症(頻度不明)
アバカビルの投与により発熱又は皮疹を伴う多臓器及び全身性の過敏症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、以下に示すような徴候又は症状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[1.1.1-1.1.5、2.1、8.2、8.5、15.1.1参照]
・皮膚
皮疹注1)(通常、斑状丘疹性皮疹又はじん麻疹)、多形紅斑
・消化器
嘔気注1)、嘔吐注1)、下痢注1)、腹痛注1)、口腔潰瘍
・呼吸器
呼吸困難注1)、咳注1)、咽頭痛、急性呼吸促迫症候群、呼吸不全
・精神神経系
頭痛注1)、感覚異常
・血液
リンパ球減少
・肝臓
肝機能検査値異常注1)(AST、ALT等の上昇)、肝不全
・筋骨格
筋痛注1)、筋変性(横紋筋融解、筋萎縮等)、関節痛、CK上昇
・泌尿器
クレアチニン上昇、腎不全
・眼
結膜炎
・その他
発熱注1)、嗜眠注1)、倦怠感注1)、疲労感注1)、浮腫、リンパ節腫脹、血圧低下、粘膜障害、アナフィラキシー
注1)過敏症発現患者のうち10%以上にみられた症状
11.1.2 膵炎(1.09%)
11.1.3 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(いずれも頻度不明)
11.1.4 乳酸アシドーシス(0.16%)、脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)(0.16%)
乳酸アシドーシス又は肝毒性が疑われる臨床症状や検査値異常が認められた場合には、本剤の投与を一時中止すること。特に、肝疾患の危険因子を有する患者においては注意すること。本剤を含むNRTIの単独投与又はこれらの併用療法により、重篤な乳酸アシドーシス(全身倦怠、食欲不振、急な体重減少、胃腸障害、呼吸困難、頻呼吸等)及び肝毒性(脂肪沈着による重度の肝腫大、脂肪肝を含む)が、女性に多く報告されている。
注)発現頻度には使用成績調査の結果を含む
11.2 その他の副作用
| 10%以上 | 5%〜10%未満 | 5%未満 | |
| 皮膚 | 発疹 | ||
| 消化器 | 悪心 | 嘔吐、下痢、食欲不振 | |
| 精神神経系 | 頭痛 | ||
| その他 | 体脂肪の再分布/蓄積(胸部、体幹部の脂肪増加、末梢部、顔面の脂肪減少、野牛肩、血清脂質増加、血糖増加) | 疲労感、嗜眠、発熱、高乳酸塩血症 |
14. 適用上の注意
14.1 薬剤交付時の注意
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。
15. その他の注意
15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 海外で実施されたプロスペクティブ試験(1956例)において、アバカビルの投与開始前にHLA-B*5701のスクリーニングを実施しない群と、スクリーニングを実施しHLA-B*5701保有者を除外した群における臨床症状から疑われる過敏症の発現頻度が、それぞれ7.8%(66/847)、3.4%(27/803)、皮膚パッチテストにより確認された過敏症の発現頻度が、それぞれ2.7%(23/842)、0.0%(0/802)であり、HLA-B*5701のスクリーニングの実施により過敏症の発現頻度が統計学的に有意に低下する(p<0.0001)ことが示された。また、本試験結果ではHLA-B*5701をスクリーニングしない群において臨床症状から過敏症が疑われた66例中30例、皮膚パッチテストにて確認された過敏症症例23例全例がHLA-B*5701を有していた。
日本人における過敏症とHLA-B*5701保有の関連性については不明であり、HLA-B*5701の保有率は白人では5〜8%、日本人では0.1%との報告がある。[1.1.1-1.1.5、2.1、8.2、8.5、11.1.1参照]
日本人における過敏症とHLA-B*5701保有の関連性については不明であり、HLA-B*5701の保有率は白人では5〜8%、日本人では0.1%との報告がある。[1.1.1-1.1.5、2.1、8.2、8.5、11.1.1参照]
15.1.2 抗HIV薬の多剤併用療法を受けている患者を対象に心筋梗塞の発現頻度を調査したプロスペクティブ観察疫学研究において、アバカビルの使用開始から6ヵ月以内の患者で心筋梗塞のリスクが増加するとの報告があるが、臨床試験の統合解析を実施した結果、対照群と比較してアバカビル投与群の過度な心筋梗塞のリスクは認められなかった。アバカビルと心筋梗塞の関連については、現在のところ結論は出ていない。予防措置として、アバカビルを含む抗HIV療法を開始する場合には、冠動脈性心疾患の潜在的リスクを考慮し、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙等の改善可能なすべてのリスク因子を最小化させるための措置をとること。
15.2 非臨床試験に基づく情報
15.2.1 細菌を用いた試験では変異原性を認めなかったが、ヒトリンパ球を用いたin vitro染色体異常試験、マウスリンフォーマ試験及びin vivo小核試験では陽性を認めた。これらの結果は、in vivo及びin vitroにおいて、本剤の高濃度を用いた場合に弱い染色体異常誘発効果を有することを示している。
15.2.2 マウス及びラットにおける長期がん原性試験において、包皮腺、陰核腺、肝臓、膀胱、リンパ節、皮下組織等に悪性腫瘍がみられたとの報告がある(ヒト全身曝露量(AUC)の24〜32倍。ただし包皮腺(ヒトにおいて該当する器官は存在しない)の腫瘍については6倍。)ので、ヒトに対する潜在的危険性と治療上の有益性を十分に検討すること。
15.2.3 アバカビルを2年間投与したマウス及びラットにおいて、軽度心筋変性が認められた(ヒト全身曝露量(AUC)の7〜24倍の用量)。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
16.1.1 単回経口投与
HIV感染症患者6例に本剤300mgを単回経口投与した場合の血清中濃度推移を図-1に、薬物動態パラメータを表-1に示した。未変化体の血清中濃度は、本剤投与後約1時間で最高濃度に達し、消失半減期は約1.4時間であった。また、アバカビルの投与後8時間までの投与量に対する尿中排泄率は、1.5〜4.2%であった5)。
図-1 血清中濃度の推移(平均値及び標準偏差、6例)
| tmax(h) | Cmax(μg/mL) | AUC∞(μg・h/mL) | t1/2(h) | |
| アバカビル | 1.0±0.6 | 3.9±1.6 | 8.3±3.5 | 1.4±0.3 |
| 5'-カルボン酸体 | 1.2±0.7 | 2.5±1.2 | 6.3±2.4 | 1.6±0.2 |
| 5'-グルクロン酸抱合体 | 1.2±0.7 | 3.7±1.4 | 12.2±4.3 | 1.9±0.4 |
HIV感染症患者9例にラミブジン300mg及びアバカビル600mgを含有する配合剤(エプジコム配合錠)を空腹時単回投与した場合のラミブジン、アバカビルの血漿中濃度の推移を図-2及び図-3に、薬物動態パラメータを表-2に示した6)。
図-2 ラミブジンの血漿中濃度の推移(平均値±標準偏差、9例)
図-3 アバカビルの血漿中濃度の推移(平均値±標準偏差、9例)
| Cmax(μg/mL) | AUClast(h・μg/mL) | AUC0-τ(h・μg/mL) | tmax注1)(h) | t1/2(h) | |
| ラミブジン | 3.58±0.61 | 13.81±3.56 | 16.30±5.058 | 2.00(1.00-3.00) | 2.49±0.55 |
| アバカビル | 5.68±2.04 | 12.56±4.01 | 12.89±4.22 | 1.00(0.50-1.03) | 1.50±0.16 |
HIV感染症患者12例を対象に本剤100、300、600、900、1200mg注)を単回経口投与した場合、Cmax及びAUC∞は投与量に依存して上昇した。未変化体の血漿中濃度は投与約1.5時間後に最高濃度に達し、消失半減期は約1.5時間であった7)(外国人データ)。
図-4 HIV感染症患者における単回経口投与後の血漿中アバカビル濃度
16.1.2 反復経口投与
HIV感染症患者20例を対象に本剤300mgを1日2回投与した場合の定常状態におけるCmaxは約3μg/mL、12時間までのAUCは約6μg・h/mLであった8)(外国人データ)。
HIV感染症患者27例を対象に本剤600mg1日1回投与時と本剤300mg1日2回投与時の定常状態における薬物動態パラメータを比較した結果、細胞内カルボビル三リン酸の曝露は、本剤600mg1日1回投与時の方が大きく、AUC0-24、Cmax及びCτがそれぞれ32%、99%及び18%増加した(外国人データ)。
16.2 吸収
16.2.1 食事の影響
HIV感染症患者18例を対象に本剤300mgを食後単回投与した場合、Cmaxは空腹時単回投与と比べ低下したが、AUC∞に変化はみられなかった9)(外国人データ)。
16.2.2 バイオアベイラビリティ
HIV感染症患者に本剤300mgを単回経口投与した時の生物学的利用率は約83%であった9)(外国人データ)。
16.3 分布
16.3.1 分布容積
16.3.2 脳脊髄液への移行
16.3.3 血漿蛋白結合率
In vitroにおいて、本剤は10μg/mLまでの添加濃度範囲で、ヒト血漿蛋白結合率は49%と一定であった10)。
16.3.4 血球移行性
血液及び血漿中放射能濃度が同じであったことから、本剤は血球に直ちに分布することが示された10)。
16.4 代謝
ヒトでの主代謝物は、5'-カルボン酸体及び5'-グルクロン酸抱合体であった11)(外国人データ)。ヒト肝由来試料を用いたin vitro試験から、本剤は肝可溶性画分により酸化的代謝を受け5'-カルボン酸体を生成したが、肝ミクロソーム画分では本剤の酸化的代謝は起こらなかった。
本剤の酸化的代謝にはCYPではなく、アルコールデヒドロゲナーゼ/アルデヒドデヒドロゲナーゼが関与していた。なお、これらの代謝物には抗ウイルス活性はなかった。[10.2、16.7.1、16.7.2参照]
アバカビルは細胞内で活性代謝物であるカルボビル三リン酸に代謝される。HIV感染症患者20例にアバカビル300mg1日2回投与した時の定常状態における細胞内カルボビル三リン酸の半減期は20.6時間であった(外国人データ)。
本剤の酸化的代謝にはCYPではなく、アルコールデヒドロゲナーゼ/アルデヒドデヒドロゲナーゼが関与していた。なお、これらの代謝物には抗ウイルス活性はなかった。[10.2、16.7.1、16.7.2参照]
アバカビルは細胞内で活性代謝物であるカルボビル三リン酸に代謝される。HIV感染症患者20例にアバカビル300mg1日2回投与した時の定常状態における細胞内カルボビル三リン酸の半減期は20.6時間であった(外国人データ)。
16.5 排泄
HIV感染症患者6例を対象に14C標識アバカビル600mgを単回経口投与後、薬物体内動態を検討した。総放射能の約99%が排泄され、主な排泄経路は尿(約83%)であり、糞中には約16%排泄された。尿中に排泄された放射能の約1%は未変化体であり、約30%が5'-カルボン酸体、約36%が5'-グルクロン酸抱合体であった11)(外国人データ)。
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 腎機能障害患者
腎機能障害患者(GFR:<10mL/min)におけるアバカビルの薬物動態は、腎機能が正常な患者の薬物動態と同様であった12)(外国人データ)。
16.6.2 肝障害患者
16.6.3 小児
アバカビルは経口投与後速やかにかつ良好に吸収され、成人と類似した薬物動態が認められる。生後3ヵ月以上で体重30kg未満の小児における推奨用量は8mg/kg1日2回であり、やや高い血漿中濃度が認められるが、成人に300mg1日2回投与した時に得られる血漿中濃度に相当する(外国人データ)。
なお、2歳から13歳未満の小児HIV感染症患者を対象とした薬物動態試験において、アバカビル8mg/kg1日2回投与した場合のAUC0-24及びCmaxはそれぞれ9.91μg・h/mL及び2.14mg/Lであり、アバカビル16mg/kg1日1回投与した場合のAUC0-24及びCmaxはそれぞれ13.37μg・h/mL及び4.80mg/Lであった(外国人データ)。[9.7参照]
なお、2歳から13歳未満の小児HIV感染症患者を対象とした薬物動態試験において、アバカビル8mg/kg1日2回投与した場合のAUC0-24及びCmaxはそれぞれ9.91μg・h/mL及び2.14mg/Lであり、アバカビル16mg/kg1日1回投与した場合のAUC0-24及びCmaxはそれぞれ13.37μg・h/mL及び4.80mg/Lであった(外国人データ)。[9.7参照]
16.6.4 新生児
生後3ヵ月未満の乳児におけるアバカビルの推奨用量及び用法は、安全性情報が十分に得られていないため明らかにされていない。現在までに得られている成績から、生後30日未満の新生児にアバカビル2mg/kg投与した時には、小児に8mg/kg投与した時と類似あるいは高値のAUCがみられることが示されている(外国人データ)。
16.7 薬物相互作用
16.7.1 In vitro試験
16.7.2 臨床薬物相互作用試験
(1)エタノール
(2)ジドブジン及びラミブジン
HIV感染症患者15例を対象に本剤600mgとジドブジン(300mg)及びラミブジン(150mg)のどちらか1剤あるいは両剤を併用した場合、いずれの併用においても併用薬による本剤血中濃度への影響はみられなかった。一方、本剤と併用したラミブジンのAUC∞及びCmaxは、ジドブジン併用、非併用に関わらずいずれも低下した。また、本剤と併用したジドブジンは、ラミブジン併用時及び非併用時においてAUC∞の上昇がみられたが、Cmaxは低下した。これらの変化は臨床上重要なものではなかった15)(外国人データ)。
(3)リオシグアト
注)本剤の承認された用法及び用量は、「通常、成人には他の抗HIV薬と併用して、アバカビルとして1日量600mgを1日1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜減量する。」である。
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 海外第III相試験(CNAAB3003)(成人)
CD4リンパ球数が100/mm3以上で抗HIV薬による治療経験のない成人HIV感染症患者173例を対象とした二重盲検比較試験において、本剤(300mg1日2回)+ラミブジン(150mg1日2回)+ジドブジン(300mg1日2回)を併用投与した群(本剤併用群)あるいはプラセボ+ラミブジン(150mg1日2回)+ジドブジン(300mg1日2回)を併用投与した群(プラセボ併用群)に、それぞれ87例と86例の患者が無作為に割り付けられた。48週間の治療期間中に、血漿中HIV-1 RNA量が検出限界(400copies/mL)以下であった患者の比率は治療開始8週後より両群間で差がみられ、48週後ではそれぞれ61%と6%となり、プラセボ併用群に比べて本剤併用群の方が高い抗HIV効果を示した。
図-1 血漿中HIV-1 RNA量が400copies/mL以下の患者の比率
また、48週後のCD4リンパ球数の増加量(中央値)は、本剤併用群とプラセボ併用群でそれぞれ150/mm3、164/mm3であった。
本剤併用群の副作用発現頻度は65%(54/83例)であった。主な副作用は、悪心47%(39/83例)、倦怠感/疲労25%(21/83例)及び頭痛24%(20/83例)であった。
17.1.2 海外第III相試験(CNAA3006)(小児)
抗HIV薬による治療経験のある生後3ヵ月〜12歳の小児HIV感染症患者205例を対象とした二重盲検比較試験において、アバカビル(8mg/kg1日2回)+ラミブジン(4mg/kg1日2回)+ジドブジン(180mg/m21日2回)を併用投与した群(アバカビル併用群)あるいはプラセボ+ラミブジン(4mg/kg1日2回)+ジドブジン(180mg/m21日2回)を併用投与した群(プラセボ併用群)に、それぞれ102例と103例の患者が無作為に割り付けられた。その結果、48週間の治療期間中に、血漿中HIV-1 RNA量が10000copies/mL以下又は検出限界(400copies/mL)以下であった患者の比率は、治療開始2週後より両群間で差がみられ、48週後ではそれぞれ10000copies/mL以下が36%、26%、検出限界以下が10%、<1%であり、プラセボ併用群に比べてアバカビル併用群の方が高い抗HIV効果を示した(他剤への変更例を無効とした解析)。
図-2 血漿中HIV-1 RNA量が10000copies/mL以下又は400copies/mL以下の患者の比率
また、48週後のCD4リンパ球数の増加量(中央値)は、プラセボ併用群が−14/mm3と減少したのに対しアバカビル併用群は99/mm3と増加した。なお、48週間を通じてCD4リンパ球数の増加量(中央値)は、アバカビル併用群がプラセボ併用群に比し高値であったが有意差はみられなかった16)。
アバカビル併用群の副作用発現頻度は38%(39/102例)であった。主な副作用は、悪心/嘔吐20%(20/102例)、頭痛6%(6/102例)及び栄養摂取の問題5%(5/102例)であった。
17.1.3 海外第III相試験(CNA30021)(成人)
治療経験がない成人のHIV感染者770例を対象として投与回数を比較する二重盲検比較試験(ラミブジン300mg1日1回とエファビレンツ600mg1日1回の併用による、アバカビル600mg1日1回投与群384例又はアバカビル300mg1日2回投与群386例)を実施した。投与48週後にHIV-1 RNA量が400copies/mL未満であった患者の比率は、アバカビル600mg1日1回投与群、300mg1日2回投与群ともに72%であった。さらに、投与48週後にHIV-1 RNA量が50copies/mL未満であった患者の比率は、アバカビル600mg1日1回投与群が66%、アバカビル300mg1日2回投与群が68%であった(図-3)。
また、投与48週後のCD4リンパ球数の増加量(中央値)は、それぞれ188/mm3、200/mm3であった。
また、投与48週後のCD4リンパ球数の増加量(中央値)は、それぞれ188/mm3、200/mm3であった。
図-3 血漿中HIV-1 RNA量が50copies/mL未満の患者の比率
注1)Roche AMPLICOR HIV-1 MONITOR
注2)治療が中止されることなく血漿中HIV-1 RNA量が50copies/mL未満を達成しかつ維持された患者の比率
なお、本試験における試験成績の要約を表-1に示した。
| 結果 | アバカビル600mg1日1回 + ラミブジン+エファビレンツ (n=384) | アバカビル300mg1日2回 + ラミブジン+エファビレンツ (n=386) |
| レスポンダー注1) | 66%(72%) | 68%(72%) |
| ウイルス学的な治療失敗注2) | 10%(4%) | 8%(4%) |
| 有害事象による中止 | 13% | 11% |
| その他の理由による中止注3) | 11% | 13% |
副作用発現頻度は、アバカビル600mg1日1回投与群で74%(283/384例)及びアバカビル300mg1日2回投与群で72%(276/386例)であった。主な副作用は、浮動性めまい[それぞれ19%(73/384例)、17%(64/386例)]、悪心[それぞれ14%(53/384例)、17%(66/386例)]、異常な夢[それぞれ16%(62/384例)、15%(56/386例)]及び不眠症[それぞれ14%(54/384例)、16%(61/386例)]であった。
17.2 製造販売後調査等
17.2.1 国内製造販売後臨床試験
CD4リンパ球数が500/mm3以下のHIV感染症患者16例を対象とした多施設共同オープン試験において、試験開始時のHIV RNA量の平均値は3.41log10 copies/mLであったが、2週後:1.87log10 copies/mL、4週後:1.69log10 copies/mL、8週後:1.38log10 copies/mL、12週後:1.34log10 copies/mL、16週後:1.34log10 copies/mLと、試験開始時から経時的に減少していることが観察され、試験開始時と最終観察時との差は有意であった(p=0.0010 Wilcoxon一標本検定)。
図-4 血清中HIV RNA量の推移(中央値)
また、CD4数の推移をみると、試験開始時の平均値は243.4/mm3、中央値は223.5/mm3であったが、最終観察時(投与後16週)にはCD4数は平均値320.8/mm3、中央値365/mm3に増加した。
図-5 CD4数の試験開始時からの変化量(中央値)
副作用発現率は87.5%(14/16例)であった。主な副作用は倦怠感、嘔気、疲労及び食欲不振であった5)。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
18.2 抗ウイルス作用
アバカビルのHIV-1に対するIC50値はHIV-1 IIIB株に対して3.7〜5.8μM、臨床分離株に対して0.26±0.18μM(n=8)、HIV-1 BaL株に対して0.07〜1.0μMであった。また、HIV-2に対するIC50値はHIV-2(Zy)株に対して4.1μM、HIV-2 LAV-2株に対して7.5μMであった。In vitroでNRTIのジダノシン、エムトリシタビン、ラミブジン、サニルブジン、テノホビル、ザルシタビン及びジドブジン、非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)のネビラピン、及びプロテアーゼ阻害剤のアンプレナビルとの相加又は相乗作用が認められた18)。また、ヒト末梢血単核球から活性化リンパ球を除いた場合に、より強い抗HIV作用を示したことから、アバカビルは静止細胞でより強く抗ウイルス作用を示すものと考えられる20)。
18.3 薬剤耐性
18.4 交差耐性
2種以上のアバカビル関連耐性変異を獲得したHIV-1株のうち数種は、in vitroでラミブジン、ジダノシン及びザルシタビンに対して交差耐性を示し、一方、ジドブジン及びサニルブジンには感受性を示した19)。
アバカビルとHIVプロテアーゼ阻害剤とは標的酵素が異なることから、両者間で交差耐性を示す可能性は低く、NNRTIも逆転写酵素の結合部位が異なることから、交差耐性を示す可能性は低いものと考えられる。
アバカビルとHIVプロテアーゼ阻害剤とは標的酵素が異なることから、両者間で交差耐性を示す可能性は低く、NNRTIも逆転写酵素の結合部位が異なることから、交差耐性を示す可能性は低いものと考えられる。
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. アバカビル硫酸塩
22. 包装
100錠[10錠(PTP)×10]
23. 主要文献
- DHHS:Guidelines for Using Antiretroviral Agents Among HIV-Infected Adults and Adolescents., (http://www.aidsinfo.nih.gov/Guidelines/)
- 抗HIV治療ガイドライン, (http://www.haart-support.jp/)
- HIV感染症「治療の手引き」, (http://www.hivjp.org/)
- Shapiro RL,et al., Antiviral Therapy., 18, 585-590, (2013) »PubMed »DOI
- 木村 哲ほか, 化学療法の領域, 18, 1664-1678, (2002)
- 矢野 邦夫ほか, 化学療法の領域, 24, 87-98, (2008)
- Kumar PN,et al., Antimicrob Agents Chemother., 43, 603-608, (1999) »PubMed »DOI
- McDowell JA,et al., Antimicrob Agents Chemother., 44, 2061-2067, (2000) »PubMed »DOI
- Chittick GE,et al., Pharmacotherapy., 19, 932-942, (1999) »PubMed »DOI
- Yuen GJ,et al., Clin Pharmacokinet., 47, 351-371, (2008) »PubMed
- McDowell JA,et al., Antimicrob Agents Chemother., 43, 2855-2861, (1999) »PubMed »DOI
- Thompson M,et al., Abstracts of the 12th World AIDS Conference., Abstract 42278, (1998)
- Raffi F,et al., Abstracts of the 40th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy., Abstract 1630, (2000)
- McDowell JA,et al., Antimicrob Agents Chemother., 44, 1686-1690, (2000) »PubMed »DOI
- Wang LH,et al., Antimicrob Agents Chemother., 43, 1708-1715, (1999) »PubMed »DOI
- Saez-Llorens X,et al., Pediatrics., 107, e4, (2001) »PubMed »DOI
- Faletto MB,et al., Antimicrob Agents Chemother., 41, 1099-1107, (1997) »PubMed »DOI
- Daluge SM,et al., Antimicrob Agents Chemother., 41, 1082-1093, (1997) »PubMed »DOI
- Tisdale M,et al., Antimicrob Agents Chemother., 41, 1094-1098, (1997) »PubMed »DOI
- Saavedra J,et al., Intersci.Conf.Antimicrob.Agents Chemother.(ICAAC), 253, (1997)
- Jungmann NA,et al., Expert Opin Drug Metab Toxicol., 15, 975-984, (2019) »PubMed
- DeJesus E,et al., Pulm Circ., 9 (2), 1-10, (2019)
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
グラクソ・スミスクライン株式会社
ヴィーブヘルスケア・カスタマー・サービス
東京都港区赤坂1-8-1
電話:0120-066-525 (9:00〜17:45/土日祝日及び当社休業日を除く)
製品情報問い合わせ先
グラクソ・スミスクライン株式会社
ヴィーブヘルスケア・カスタマー・サービス
東京都港区赤坂1-8-1
電話:0120-066-525 (9:00〜17:45/土日祝日及び当社休業日を除く)
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
ヴィーブヘルスケア株式会社
東京都港区赤坂1-8-1
26.2 販売元
グラクソ・スミスクライン株式会社
東京都港区赤坂1-8-1
その他の説明
■過敏症を注意するカード
(表面)
(中面)
(裏面)