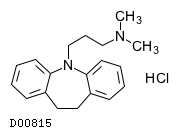医薬品情報
| 総称名 | トフラニール |
|---|---|
| 一般名 | イミプラミン塩酸塩 |
| 欧文一般名 | Imipramine Hydrochloride |
| 薬効分類名 | うつ病・うつ状態治療剤 遺尿症治療剤 |
| 薬効分類番号 | 1174 |
| ATCコード | N06AA02 |
| KEGG DRUG |
D00815
イミプラミン塩酸塩
|
| KEGG DGROUP |
DG01730
非選択的モノアミン再取り込み阻害薬
|
| JAPIC | 添付文書(PDF) |
添付文書情報2024年3月 改訂(第2版)

|
2.禁忌 4.効能または効果 5.効能又は効果に関連する注意 6.用法及び用量 8.重要な基本的注意 9.特定の背景を有する患者に関する注意 10.相互作用 11.副作用 13.過量投与 14.適用上の注意 15.その他の注意 16.薬物動態 17.臨床成績 18.薬効薬理 19.有効成分に関する理化学的知見 22.包装 23.主要文献 24.文献請求先及び問い合わせ先 26.製造販売業者等 |
商品情報 3.組成・性状
| 販売名 | 欧文商標名 | 製造会社 | YJコード | 薬価 | 規制区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| トフラニール錠10mg | TOFRANIL Tablets 10mg | アルフレッサファーマ | 1174006F1078 | 10.1円/錠 | 処方箋医薬品注) |
| トフラニール錠25mg | TOFRANIL Tablets 25mg | アルフレッサファーマ | 1174006F2074 | 10.4円/錠 | 処方箋医薬品注) |
2. 禁忌
次の患者には投与しないこと
4. 効能または効果
○精神科領域におけるうつ病・うつ状態
○遺尿症(昼・夜)
5. 効能または効果に関連する注意
6. 用法及び用量
<トフラニール錠10mg>
<精神科領域におけるうつ病・うつ状態>
イミプラミン塩酸塩として、通常成人1日30〜70mgを初期用量とし、1日200mgまで漸増し、分割経口投与する。まれに300mgまで増量することもある。
なお、年齢、症状により適宜減量する。
なお、年齢、症状により適宜減量する。
<遺尿症(昼・夜)>
通常学童は1日量30〜50mgを1〜2回経口投与する。
ただし、症状および年齢に応じ適宜増減する。
ただし、症状および年齢に応じ適宜増減する。
<トフラニール錠25mg>
<精神科領域におけるうつ病・うつ状態>
イミプラミン塩酸塩として、通常成人1日25〜75mgを初期用量とし、1日200mgまで漸増し、分割経口投与する。まれに300mgまで増量することもある。
なお、年齢、症状により適宜減量する。
なお、年齢、症状により適宜減量する。
<遺尿症(昼・夜)>
通常幼児は1日量25mgを1回、学童は1日量25〜50mgを1〜2回経口投与する。
ただし、症状および年齢に応じ適宜増減する。
ただし、症状および年齢に応じ適宜増減する。
8. 重要な基本的注意
8.1 うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期ならびに投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。[5.、9.1.5、9.1.8、15.1.1参照]
8.2 不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア/精神運動不穏、軽躁、躁病等があらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されている。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。[5.、8.3、8.4、9.1.5-9.1.8、15.1.1参照]
8.4 家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。[5.、8.2、8.3、9.1.5-9.1.8、15.1.1参照]
8.5 投与量の急激な減少ないし投与の中止により、嘔気、頭痛、倦怠感、易刺激性、情動不安、睡眠障害、筋攣縮等の離脱症状があらわれることがある。投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
8.6 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
8.7 無顆粒球症等の血液障害があらわれることがあるので、定期的に血液検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.4参照]
8.8 QT延長、心室頻拍(Torsade de pointesを含む)があらわれることがあるので、定期的に心電図検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.8参照]
8.9 連用中は定期的に肝・腎機能検査を行うことが望ましい。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 開放隅角緑内障の患者
抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。
9.1.2 排尿困難又は眼内圧亢進等のある患者
抗コリン作用により症状が悪化することがある。
9.1.3 心不全・心筋梗塞・狭心症・不整脈(発作性頻拍・刺激伝導障害等)等の心疾患のある患者又は甲状腺機能亢進症の患者(ただし、心筋梗塞の回復初期の患者は除く)
循環器系に影響を及ぼすことがある。
9.1.4 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者
痙攣を起こすことがある。
9.1.5 躁うつ病患者
9.1.6 脳の器質障害又は統合失調症の素因のある患者
9.1.7 衝動性が高い併存障害を有する患者
9.1.8 自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者
9.1.9 副腎髄質腫瘍(褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、神経芽細胞腫等)のある患者
高血圧発作を引き起こすことがある。
9.1.10 低血圧のある患者
高度の血圧低下が起こることがある。
9.1.11 低カリウム血症のある患者
低カリウム状態はQT延長の危険因子と考えられる。
9.1.12 高度な慢性の便秘のある患者
抗コリン作用により症状が悪化することがある。
9.2 腎機能障害患者
9.2.1 重篤な腎障害のある患者
排泄障害により副作用があらわれやすい。
9.3 肝機能障害患者
9.3.1 重篤な肝障害のある患者
代謝障害により副作用があらわれやすい。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。新生児に呼吸困難、嗜眠、チアノーゼ、興奮性、低血圧、高血圧、痙攣、筋痙縮、振戦等の離脱症状を起こしたとの報告がある。動物実験(ウサギ)で催奇形作用(外形異常)が報告されている1)。
9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行する。
9.7 小児等
4歳以上に投与することが望ましい。
9.8 高齢者
少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。起立性低血圧、ふらつき、抗コリン作用による口渇、排尿困難、便秘、眼内圧亢進等があらわれやすい。
10. 相互作用
相互作用序文
本剤の代謝には肝薬物代謝酵素CYP2D6が関与している。また、CYP1A2、CYP3A4、CYP2C19も関与していると考えられている。
薬物代謝酵素用語
CYP2D6
薬物代謝酵素用語
CYP1A2
薬物代謝酵素用語
CYP3A4
薬物代謝酵素用語
CYP2C19
10.1 併用禁忌
| MAO阻害剤 セレギリン塩酸塩 (エフピー) ラサギリンメシル酸塩 (アジレクト) サフィナミドメシル酸塩 (エクフィナ) [2.5参照] | 発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等があらわれることがある。MAO阻害剤の投与を受けた患者に本剤を投与する場合には、少なくとも2週間の間隔をおき、また本剤からMAO阻害剤に切り替えるときには、2〜3日間の間隔をおくことが望ましい。 | 本剤は活性アミンのシナプス内への取り込みを阻害して、受容体の感受性を増強する。 |
10.2 併用注意
| 抗コリン作用を有する薬剤 トリヘキシフェニジル アトロピン等 | 口渇、便秘、尿閉、視力障害、眠気等があらわれることがある。 | いずれも抗コリン作用を有するため。 |
| アドレナリン作動薬 アドレナリン ノルアドレナリン フェニレフリン等 | 心血管作用(高血圧等)を増強することがある。 | 本剤は交感神経末梢へのノルアドレナリン等の取り込みを抑制し、受容体部位へのアドレナリン作動性を上昇させ、作用を増強させる。 |
| アトモキセチン | 相互に作用が増強するおそれがある。 | ノルアドレナリンへの作用を相加的又は相乗的に増強する可能性がある。 |
| 中枢神経抑制剤 バルビツール酸誘導体等 全身麻酔剤 ハロタン等 抗不安剤 アルプラゾラム等 アルコール サリドマイド | 中枢神経抑制作用が増強されることがある。 | いずれも中枢神経抑制作用を有するため。 |
| フェノチアジン系精神神経用剤 レボメプロマジン等 | 鎮静、抗コリン作用の増強があらわれることがある。 | いずれも中枢神経抑制作用、抗コリン作用を有するため。 |
| 選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) フルボキサミン パロキセチン等 | 本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されることがある。セロトニン症候群があらわれるおそれがある。 | これらの薬剤は本剤の肝臓での酸化的な代謝を阻害し、本剤の血中濃度を上昇させると考えられる。また、相互にセロトニン作動性が増強される可能性がある。 |
| セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI) ミルナシプラン リチウム製剤 三環系抗うつ剤 アミトリプチリン クロミプラミン等 トラマドール塩酸塩 リネゾリド | セロトニン症候群があらわれるおそれがある。 | 相互にセロトニン作動性が増強される可能性がある。 |
| 副交感神経刺激剤 ピロカルピン セビメリン | これらの薬剤の作用が減弱されることがある。 | 本剤の抗コリン作用によりこれらの薬剤と拮抗的に作用すると考えられている。 |
| 肝酵素誘導作用をもつ薬剤 バルビツール酸誘導体 フェニトイン カルバマゼピン リファンピシン等 | 本剤の血中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。 | これらの薬剤の肝酵素誘導作用により本剤の代謝が促進されると考えられている。 |
| フェニトイン | フェニトインの作用が増強することがある。 | フェニトインの代謝が阻害され、フェニトインの血中濃度が上昇すると考えられている。 |
| 抗不整脈剤 キニジン プロパフェノン メチルフェニデート シメチジン 黄体・卵胞ホルモン製剤 シナカルセト サキナビル | 本剤の作用が増強されることがある。 | これらの薬剤により、本剤の肝代謝が阻害され、血中濃度が上昇すると考えられている。 |
| 降圧剤 グアネチジン | 降圧剤の作用を減弱することがある。 | 本剤がアドレナリン作動性神経遮断作用を有する降圧剤の交感神経ニューロンへの取り込みを阻害する。また、本剤は交感神経ニューロンへのカテコラミン取り込み阻害作用も有する。 |
| テルビナフィン | 本剤の活性代謝物の血中濃度が上昇するとの報告があるので、併用する場合には用量に注意すること。 | テルビナフィンのCYP2D6の阻害により、本剤又はその活性代謝物の代謝が遅延する。 |
| ホスアンプレナビル | 本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。 | ホスアンプレナビルの活性代謝物であるアンプレナビルは本剤の代謝を競合的に阻害すると考えられる。 |
| インスリン製剤 インスリン スルフォニル尿素系糖尿病用剤 グリベンクラミド グリクラジド | 他の三環系抗うつ剤(ドキセピン)との併用により過度の血糖低下を来すとの報告がある。 | ドキセピンにより低血糖に対する反応性が変化するか、インスリンに対する感受性が増大し、血糖降下作用が増強すると考えられている。 |
| クマリン系抗凝血剤 ワルファリン | 他の三環系抗うつ剤(ノルトリプチリン)との併用によりクマリン系抗凝血剤の血中濃度半減期が延長するとの報告がある。 | 機序不明。 |
| スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 本剤との併用により抑うつが再発又は悪化することがある。 | 本剤の代謝促進又は両剤の受容体レベルでの拮抗作用によるものと考えられている。 |
| QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤 スニチニブ ダサチニブ マプロチリン等 | QT間隔延長、心室性不整脈(Torsade de pointesを含む)等の重篤な副作用を起こすおそれがある。 | いずれもQT間隔を延長させるおそれがあるため。 |
| デスモプレシン | 低ナトリウム血症性の痙攣発作を起こすことがあるので、血清ナトリウム、血漿浸透圧等をモニターすること。 | いずれも低ナトリウム血症があらわれるおそれがあるため。 |
| ゾニサミド | 高血圧、失神、不全収縮、発汗、てんかん、動作・精神障害の変化及び筋強剛等の副作用があらわれるおそれがある。 | 相加・相乗作用によると考えられる。 |
| 電気ショック療法 | 痙攣閾値を低下させ、痙攣状態に陥るおそれがある。 | 本剤は痙攣閾値を低下させると考えられている。 |
11. 副作用
11.1 重大な副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
11.1.1 悪性症候群(Syndrome malin)(頻度不明)
無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行う。
本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇がみられることが多く、またミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害へと移行し、死亡した例が報告されている。
本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇がみられることが多く、またミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害へと移行し、死亡した例が報告されている。
11.1.2 セロトニン症候群(頻度不明)
不安、焦燥、せん妄、興奮、発熱、発汗、頻脈、振戦、ミオクロヌス、反射亢進、下痢等を主症状とするセロトニン症候群があらわれることがあるので、これらの症状が出現した場合には投与を中止し、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。
11.1.3 てんかん発作(頻度不明)
11.1.4 無顆粒球症(頻度不明)
無顆粒球症(前駆症状として発熱、咽頭痛、インフルエンザ様症状等)があらわれることがある。[8.7参照]
11.1.5 麻痺性イレウス(頻度不明)
腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。なお、この悪心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。
11.1.6 間質性肺炎、好酸球性肺炎(いずれも頻度不明)
発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等が認められた場合には投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
11.1.7 心不全(頻度不明)
11.1.9 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(頻度不明)
症状として低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等があらわれることがある。水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。
11.1.10 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
AST、ALT、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
注1)発現頻度は承認後の臨床試験等を含む。
11.2 その他の副作用
| 5%以上 | 0.1%〜5%未満 | 頻度不明 | |
| 循環器 | − | 血圧降下、頻脈、不整脈、動悸 | 起立性低血圧、心電図異常(QT延長等)、血圧上昇、心ブロック |
| 精神神経系 | パーキンソン症状・振戦・アカシジア等の錐体外路障害、眠気 | 運動失調、言語障害、知覚異常、幻覚、精神錯乱、攻撃的反応、激越、躁状態、不眠、不安、焦燥 | せん妄、ミオクロヌス、性欲減退 |
| 抗コリン作用 | 口渇、排尿困難、便秘 | 視調節障害(散瞳等)、鼻閉 | 眼内圧亢進、尿閉 |
| 皮膚 | − | − | 光線過敏症、脱毛 |
| 過敏症 | − | 発疹、そう痒感 | 顔・舌部の浮腫 |
| 血液 | − | − | 白血球減少、血小板減少、紫斑、点状出血、好酸球増多 |
| 肝臓 | − | − | AST、ALTの上昇 |
| 消化器 | 悪心・嘔吐 | 食欲不振、下痢、味覚異常 | 口内炎、舌炎 |
| 内分泌 | − | 体重増加 | 乳房肥大、乳汁漏出、体重減少 |
| 長期投与注2) | − | − | 口周部等の不随意運動 |
| その他 | ふらつき、めまい、発汗 | 倦怠感、脱力感、頭痛、異常高熱、熱感、耳鳴 | 血管痙攣、血糖値上昇、血糖値低下 |
13. 過量投与
13.1 徴候、症状
最初の徴候、症状は通常服用30分〜2時間後に高度の抗コリン作用を主症状として出現する2)。
中枢神経系
眠気、昏迷、意識障害、運動失調、情動不安、激越、反射亢進、筋強剛、アテトーシス及び舞踏病アテトーシス様運動、痙攣、セロトニン症候群
心血管系
低血圧、不整脈、頻脈、伝導障害、ショック、心不全、非常にまれにQT延長、Torsade de pointes、心停止
その他
呼吸抑制、チアノーゼ、嘔吐、散瞳、発汗、乏尿、無尿等
13.2 処置
特異的な解毒剤は知られていない。なお、腹膜透析又は血液透析はほとんど無効である。
症状が重篤な場合には、直ちに入院させ、少なくとも48時間は心モニターを継続する。心電図に異常がみられた患者は、心電図が正常に復した後であっても再発の可能性があるため、少なくとも72時間は、心機能の観察を継続すること2)。
症状が重篤な場合には、直ちに入院させ、少なくとも48時間は心モニターを継続する。心電図に異常がみられた患者は、心電図が正常に復した後であっても再発の可能性があるため、少なくとも72時間は、心機能の観察を継続すること2)。
14. 適用上の注意
14.1 薬剤交付時の注意
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。
15. その他の注意
15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者を対象とした、本剤を含む複数の抗うつ剤の短期プラセボ対照臨床試験の検討結果において、24歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現のリスクが抗うつ剤投与群でプラセボ群と比較して高かった。なお、25歳以上の患者における自殺念慮や自殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65歳以上においてはそのリスクが減少した。[5.、8.1-8.4、9.1.5、9.1.8参照]
15.1.2 三環系抗うつ剤の長期投与でう歯発現の増加を招くことが報告されている。
15.1.3 本剤投与中にコンタクトレンズを使用している場合、角膜上皮の障害があらわれるおそれがある。本剤は抗コリン作用があり、涙液分泌を減少させるため。
15.1.4 主に50歳以上を対象に実施された海外の疫学調査において、選択的セロトニン再取り込み阻害剤及び三環系抗うつ剤を含む抗うつ剤を投与された患者で、骨折のリスクが上昇したとの報告がある。
16. 薬物動態
16.1 血中濃度
16.2 吸収
16.5 排泄
17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験
<精神科領域におけるうつ病・うつ状態>
17.1.1 国内二重盲検試験
二重盲検比較試験11試験における総症例708例中、臨床効果の判定が可能であった673例での有効率は64.2%(432/673)であった。
副作用は、二重盲検比較試験11試験において、副作用が判定可能であった688例中465例(67.6%)に認められ、主な症状としては口渇236件(34.3%)、めまい・ふらつき・立ちくらみ144件(20.9%)、眠気130件(18.9%)、便秘105件(15.3%)、発汗75件(10.9%)、振戦・強剛63件(9.2%)、悪心・嘔吐51件(7.4%)等がみられた。
副作用は、二重盲検比較試験11試験において、副作用が判定可能であった688例中465例(67.6%)に認められ、主な症状としては口渇236件(34.3%)、めまい・ふらつき・立ちくらみ144件(20.9%)、眠気130件(18.9%)、便秘105件(15.3%)、発汗75件(10.9%)、振戦・強剛63件(9.2%)、悪心・嘔吐51件(7.4%)等がみられた。
<遺尿症(昼・夜)>
17.1.2 承認時までの調査(二重盲検比較試験を含む)
承認時までの調査における319例(二重盲検比較試験を含む)中、臨床効果の判定が可能であった304例中での有効率は84.2%(256/304)であった。
副作用は、承認時までの調査において(二重盲検比較試験を含む)、判定可能であった317例中54例(17.0%)に認められ、主な症状としては食欲不振22件(6.9%)、口渇15件(4.7%)、悪心7件(2.2%)等がみられた。
副作用は、承認時までの調査において(二重盲検比較試験を含む)、判定可能であった317例中54例(17.0%)に認められ、主な症状としては食欲不振22件(6.9%)、口渇15件(4.7%)、悪心7件(2.2%)等がみられた。
18. 薬効薬理
18.1 作用機序
抗うつ剤の作用機序は確立されていないが、脳内のセロトニン(5-HT)及びノルアドレナリン(NA)の神経終末への取り込み阻害による受容体刺激の増強が抗うつ効果と結びついていると考えられている。各種抗うつ剤の脳内(ラット)での5-HT及びNA取り込み阻害の比[ED50(NA)/ED50(5-HT)]は下図のとおりで、イミプラミンは両者に作用するが、NA取り込み阻害がより強く、代謝物デシプラミンではNA取り込み阻害はさらに強くなる。9)
19. 有効成分に関する理化学的知見
19.1. イミプラミン塩酸塩
22. 包装
<錠10mg>
300錠[10錠(PTP)×30]
1200錠[10錠(PTP)×120]
1200錠[ガラス瓶、バラ、乾燥剤入り]
1200錠[10錠(PTP)×120]
1200錠[ガラス瓶、バラ、乾燥剤入り]
<錠25mg>
200錠[10錠(PTP)×20]
1000錠[10錠(PTP)×100]
1000錠[ガラス瓶、バラ、乾燥剤入り]
1000錠[10錠(PTP)×100]
1000錠[ガラス瓶、バラ、乾燥剤入り]
23. 主要文献
- Harper,K.H.et al., Arzneimittelforschung., 15, 1218-1221, (1965)
- 社内資料:過量使用時の症状と処置に関する資料
- 浅野 裕 他, 精神薬療基金研究年報, 9, 119-127, (1977)
- Nagy,A.et al., Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol., 290, 145-160, (1975) »PubMed
- Gram,L.F.et al., Clin Pharmacol Ther., 17, 555-563, (1975) »PubMed
- Dencker,H.et al., Clin Pharmacol Ther., 19, 584-586, (1976) »PubMed
- Christiansen,J.et al., Psychopharmacology(Berl)., 11, 255-264, (1967)
- Crammer,J.L.et al., Psychopharmacology(Berl)., 15, 207-225, (1969)
- Waldmeier,P.C.et al., Postgrad Med J., 52, 33-39, (1976) »PubMed
24. 文献請求先及び問い合わせ先
文献請求先
アルフレッサファーマ株式会社
製品情報部
〒540-8575
大阪市中央区石町二丁目2番9号
電話:06-6941-0306
FAX:06-6943-8212
製品情報問い合わせ先
アルフレッサファーマ株式会社
製品情報部
〒540-8575
大阪市中央区石町二丁目2番9号
電話:06-6941-0306
FAX:06-6943-8212
26. 製造販売業者等
26.1 製造販売元
アルフレッサファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号